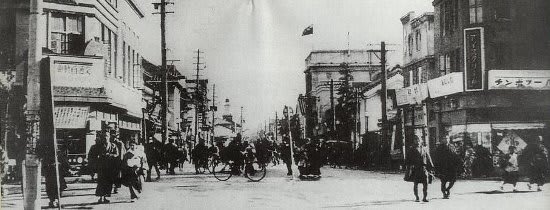先日、国土交通省(山形河川国道事務所)が社会実験中の自転車道(東側に南北双方向)がある国道沿道の3つの商店会に対して提案した案のうち両側に片側通行の自転車道を設置する案についてもすんなりとは承服し難い点が幾つかある。
一つは、車道との境界に「
縁石」を連ねることについてである。
現在の社会実験中は境界にポールを並べている(当初はポールとポールの間に縁石代わりのものを嵌め込んでいた)が、花笠踊りのパレードや初市などの毎年恒例のイベントがある時は外してイベントが広く開催できるようにしていた。
しかし、もし新案にある縁石が外しにくいものだとすると道路利用の
イベント開催は困難になる。CGによる予想図(下の絵図参照)を見る限り、どうもその縁石は固定式であり、外せないもののようである。

二つ目は、現在は車道の西側にバス停を設けていたが、車道の両隣に片側通行の自転車道を設置する場合、
バス停留所の設置は困難になる。なぜなら、バスに乗降する人は自転車道と縁石を跨ぐことになり、危険な思いをすることになるからである。
三つ目は荷捌き車両のために歩道の幅をさらに狭くする箇所が出てくることである。
これでは歩行者に犠牲を強いることになり、商店街のイメージを低下させる。
むしろ渋滞覚悟で車道上に停車帯を設けるべきではないか。現在も西側部分だけに限定であるが、バスは停車できるようになっている。つまり、一方通行二車線のうち一車線の三分の一くらいは荷捌き車両の停車帯としておいて差支えなかろう。
そのためにも、国道ながらも速度制限を20km程度の「ユックリズム国道」にして、
歩行者・自転車優先の国道として全国にアピールしてはどうか。
四つ目は、幅広い自転車道にするためには街路樹をすべて除去する必要があるとしていることである。
いずれの沿道の商店街からは瀟洒な外観の店舗や歴史を感じさせる土蔵造りの店舗が減少する中で駐車場が虫食いのように増殖し、ただでさえ街路景観が殺風景で武骨化しているものの、街路樹の緑だけは街を通る人たちの心に潤いを与えており、そのために沿道商店街の良好なイメージをなんとか保持してくれていたのだが、街路樹がなくなると、沿道の景観はますます殺風景になり、商店街のイメージも低下してしまうのではないか。
また、十二月から一月にかけて街路樹にイルミネーションを飾り、夕刻の商店街を華やかな雰囲気にしているが、それも不可能になる。
自転車道は必要である。とりわけ歩行者の多いこの通りには歩行者の安全のためにも自転車道は必要である。
しかし、自転車道のためにバス停の設置も困難になり、街路樹も撤去されるとすれば、両側に片側通行の自転車道の設置は問題が多いと言わざるをえなくなる。
それゆえ、当面は
現状こそ最良と申すべきかもしれない。
むろん、現状とて自転車道の青いペンキは確かに景観上に好ましくないなど問題点がないわけではないのだが、ともかく、この問題の解決には時間をかけるへきであり、前回も申したとおり、性急に事を進めるべきではない。