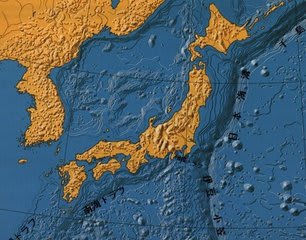2年半ぶりの投稿になりました。
しばらく当シリーズを続けます。

<コロナの数え方>って、そもそもどうなのか?
あまりにも強烈だからといって人格権を与えて1人、2人・・と数えるのも変だし、生物ではないというが、1個、2個・・ではしゃくだ。
コロナ野郎め、こん畜生と思えば、1匹、2匹と数えたくなる。
手指のこまめな消毒が強く叫ばれているが、その手指には果たして何匹がくっついているのか。
1匹~2匹しかくっついていないし、しかも弱まったウィルスでしかないと無害に等しい。
逆に1万匹以上で強毒性だとしたら、消毒薬でごしごし15分も洗って流せば、ほとんどのウィルスは死滅ないし弱体化するであろう。いわば“大虐殺”であり、コロナホロコーストだ。
でも、全世界的には完全死滅はしていない。むしろアフリカ、中南米での蔓延による第三波の襲来が心配される。また、武漢と日本との経済交流も再開されるという報道もあるがマスコミの報道力はあまりにも控えめ。これこそもっとも強力に<要自粛>を呼びかけるべきではないのか。

手指に付着のウィルスが1匹か1000匹かもわからないまま、つまり「無害」「無毒」の可能性が大でも消毒液により店舗や施設に入らねばならないとはコロナ全体主義の帝王(または大総統閣下)がほくそえんでいるわけだ。もし、手指に付着のウィルスがわずか1匹だけでも毒性が強力だとしも、口腔から採取された検体だけでPCR検査には表れない可能性が強い。いくら消毒で死滅させても残存部隊が増殖していれば感染者がゼロになることはないので、政府も自治体も国民も戦々恐々。コロナ様はほくそ笑む。でもいつかは泣きべそをかかせてやりたい。
しばらく当シリーズを続けます。

<コロナの数え方>って、そもそもどうなのか?
あまりにも強烈だからといって人格権を与えて1人、2人・・と数えるのも変だし、生物ではないというが、1個、2個・・ではしゃくだ。
コロナ野郎め、こん畜生と思えば、1匹、2匹と数えたくなる。
手指のこまめな消毒が強く叫ばれているが、その手指には果たして何匹がくっついているのか。
1匹~2匹しかくっついていないし、しかも弱まったウィルスでしかないと無害に等しい。
逆に1万匹以上で強毒性だとしたら、消毒薬でごしごし15分も洗って流せば、ほとんどのウィルスは死滅ないし弱体化するであろう。いわば“大虐殺”であり、コロナホロコーストだ。
でも、全世界的には完全死滅はしていない。むしろアフリカ、中南米での蔓延による第三波の襲来が心配される。また、武漢と日本との経済交流も再開されるという報道もあるがマスコミの報道力はあまりにも控えめ。これこそもっとも強力に<要自粛>を呼びかけるべきではないのか。

手指に付着のウィルスが1匹か1000匹かもわからないまま、つまり「無害」「無毒」の可能性が大でも消毒液により店舗や施設に入らねばならないとはコロナ全体主義の帝王(または大総統閣下)がほくそえんでいるわけだ。もし、手指に付着のウィルスがわずか1匹だけでも毒性が強力だとしも、口腔から採取された検体だけでPCR検査には表れない可能性が強い。いくら消毒で死滅させても残存部隊が増殖していれば感染者がゼロになることはないので、政府も自治体も国民も戦々恐々。コロナ様はほくそ笑む。でもいつかは泣きべそをかかせてやりたい。