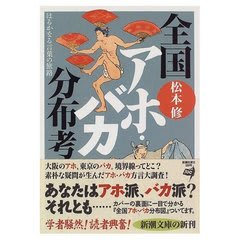
『全国アホ・バカ分布考 -はるかなる言葉の旅路-』(松本修 新潮文庫)
<とんねるず表現>考の記事で「『全国アホ・バカ分布図』を読んでいる」と書きましたが、書名にあやまりがありました。正しくは、
『全国アホ・バカ分布考 -はるかなる言葉の旅路-』(全国アホ・バカ分布地図附)
おくればせながら、読み終わりました。
一テレビマンがものした一般書の文庫としては、異例ともいえる分量のぶあつい一冊。
一気に読了。
いったん読み始めたら、止められませんでした。
「東京出身の妻と大阪出身の夫が夫婦喧嘩をすると、互いにアホ、バカといって傷ついてしまう。そこでふと思った、アホとバカの境界線はどこにあるのか?」
この、一見なんの変哲もない、というかどーみてもアホらしい依頼が、ひとりのテレビプロデューサーのライフワークにまでなってしまうとは。
依頼者は「地味な調査で申しわけありませんが・・・」と謙虚です。
しかし、地味どころか、この一枚の依頼ハガキこそが・・・いや、このひと組の"異文化"夫婦の痴話げんかこそが、「探偵!ナイトスクープ」をしてテレビ界の各賞を総ナメにさせ、日本方言学会での発表につながり、いまや方言学の分野においてひとつの学説を提唱するまでの、壮大な旅をさせることになったのですから・・・
まったく、人生ってわからないものです。
それにしても、著者の松本修さんの情熱には、頭が下がります。
経済学部出身で、職業はテレビプロデューサー。国語学・方言学の分野とはまるっきり縁のなかったはずの彼が、番組をきっかけにアホ・バカ表現の世界にどんどんハマり、のめりこんでゆく。
本書にはもはや素人の趣味の域をはるかに超えた専門知識がつまっていて、正直わたしも、まだ全部理解できているとは言えない。それくらい中身は濃いです。
松本氏の主張を簡単に要約してみましょう。
彼が支持する方言周圏論(蝸牛考)によると、「バカ」は古い京のことばで、京の周辺で流行したあと波紋がひろがってゆくようにじょじょに全国の辺境へと伝わっていった。
その間にあらたに京でうまれた新興の表現が「アホ」である。
しかも、「バカ」以前にはもっと古いアホ・バカ表現が無数にあり、それが流行と衰退をくりかえしながら日本各地にひろまり、方言として定着した。だから、東北や九州・沖縄のアホ・バカ方言は、実は古代の京で生まれたことばの名残りなのである。
松本氏の方言周圏論至上説が、学術的にみてどこまで有効なのかはよくわかりませんが、それよりも、「バカ」と「アホ」それぞれの語源についての松本さんの説明がおもしろかった。素人目にも、従来提唱されてきた説よりも確かに説得力があるような気がしました。
参考:Wikipedia「馬鹿」・「阿呆」
シャーロック・ホームズが言うように、矛盾点をすべて排除して最後にのこる事実がいかに奇異に見えようとも、それこそが真実なのだ。
松本さんはホームズの大ファンだそうで、「探偵!ナイトスクープ」のセットもベーカー街のホームズのアパートをイメージしているらしい。
『全国アホ・バカ分布考』も、見方を変えれば、まるで言語地理学の探偵小説。
松本さんはまさに "素人探偵" として、アホ・バカ方言の大いなるナゾにメスをいれたということでしょう。
ワトソンよろしく松本ホームズを支えたナイトスクープ制作スタッフも、いいキャラしてます。
本を読んでいると、松本さんが在野の研究者としてすこしずつ成熟してゆく過程もよく伝わってきます。
自分の研究は自分だけのものではなく、過去、現在、未来の多くの研究者や協力者がたがいに手をたずさえて成し遂げるものなのだ---
第七章で、鴨長明『発心集』に関する梁瀬一雄氏の論文を読んで松本さんが感動する場面に、わたしも胸が熱くなりました。
研究のおもしろさ。学問の醍醐味。本書はそれを存分に味わわせてくれます。
しかも松本さんは、テレビの制作という多忙な仕事をもちながらここまでのレベルに到達したのですから、その情熱はすごい。方言学、言語地理学をポピュラーにした功績だってあるでしょう。
アホ・バカ表現という、プロの研究者がまともにとりあげる気すら起こさなかった言葉に光をあてたこと。それが『全国アホ・バカ分布考』の最大の功績だと思います。
この本はいまでは大学のテキストとしてもよく使われているようです。
言葉は、生きてるんだなあ。生きているからこそ、どんどん変化してゆく。
「正しい日本語はこうあるべき」なーんて、ちゃんちゃらおかしい。
盛衰をくりかえして生きる言葉こそが、美しい!
松本さんにも、ぜひアホ・バカ表現研究を続けていってもらいたいです。
そしていつの日かまたナイトスクープで大々的に、かつ超アホらしくバカバカしく、その成果を発表してくれることを期待しています。
<とんねるず表現>考の記事で「『全国アホ・バカ分布図』を読んでいる」と書きましたが、書名にあやまりがありました。正しくは、
『全国アホ・バカ分布考 -はるかなる言葉の旅路-』(全国アホ・バカ分布地図附)
おくればせながら、読み終わりました。
一テレビマンがものした一般書の文庫としては、異例ともいえる分量のぶあつい一冊。
一気に読了。
いったん読み始めたら、止められませんでした。
「東京出身の妻と大阪出身の夫が夫婦喧嘩をすると、互いにアホ、バカといって傷ついてしまう。そこでふと思った、アホとバカの境界線はどこにあるのか?」
この、一見なんの変哲もない、というかどーみてもアホらしい依頼が、ひとりのテレビプロデューサーのライフワークにまでなってしまうとは。
依頼者は「地味な調査で申しわけありませんが・・・」と謙虚です。
しかし、地味どころか、この一枚の依頼ハガキこそが・・・いや、このひと組の"異文化"夫婦の痴話げんかこそが、「探偵!ナイトスクープ」をしてテレビ界の各賞を総ナメにさせ、日本方言学会での発表につながり、いまや方言学の分野においてひとつの学説を提唱するまでの、壮大な旅をさせることになったのですから・・・
まったく、人生ってわからないものです。
それにしても、著者の松本修さんの情熱には、頭が下がります。
経済学部出身で、職業はテレビプロデューサー。国語学・方言学の分野とはまるっきり縁のなかったはずの彼が、番組をきっかけにアホ・バカ表現の世界にどんどんハマり、のめりこんでゆく。
本書にはもはや素人の趣味の域をはるかに超えた専門知識がつまっていて、正直わたしも、まだ全部理解できているとは言えない。それくらい中身は濃いです。
松本氏の主張を簡単に要約してみましょう。
彼が支持する方言周圏論(蝸牛考)によると、「バカ」は古い京のことばで、京の周辺で流行したあと波紋がひろがってゆくようにじょじょに全国の辺境へと伝わっていった。
その間にあらたに京でうまれた新興の表現が「アホ」である。
しかも、「バカ」以前にはもっと古いアホ・バカ表現が無数にあり、それが流行と衰退をくりかえしながら日本各地にひろまり、方言として定着した。だから、東北や九州・沖縄のアホ・バカ方言は、実は古代の京で生まれたことばの名残りなのである。
松本氏の方言周圏論至上説が、学術的にみてどこまで有効なのかはよくわかりませんが、それよりも、「バカ」と「アホ」それぞれの語源についての松本さんの説明がおもしろかった。素人目にも、従来提唱されてきた説よりも確かに説得力があるような気がしました。
参考:Wikipedia「馬鹿」・「阿呆」
シャーロック・ホームズが言うように、矛盾点をすべて排除して最後にのこる事実がいかに奇異に見えようとも、それこそが真実なのだ。
松本さんはホームズの大ファンだそうで、「探偵!ナイトスクープ」のセットもベーカー街のホームズのアパートをイメージしているらしい。
『全国アホ・バカ分布考』も、見方を変えれば、まるで言語地理学の探偵小説。
松本さんはまさに "素人探偵" として、アホ・バカ方言の大いなるナゾにメスをいれたということでしょう。
ワトソンよろしく松本ホームズを支えたナイトスクープ制作スタッフも、いいキャラしてます。
本を読んでいると、松本さんが在野の研究者としてすこしずつ成熟してゆく過程もよく伝わってきます。
自分の研究は自分だけのものではなく、過去、現在、未来の多くの研究者や協力者がたがいに手をたずさえて成し遂げるものなのだ---
第七章で、鴨長明『発心集』に関する梁瀬一雄氏の論文を読んで松本さんが感動する場面に、わたしも胸が熱くなりました。
研究のおもしろさ。学問の醍醐味。本書はそれを存分に味わわせてくれます。
しかも松本さんは、テレビの制作という多忙な仕事をもちながらここまでのレベルに到達したのですから、その情熱はすごい。方言学、言語地理学をポピュラーにした功績だってあるでしょう。
アホ・バカ表現という、プロの研究者がまともにとりあげる気すら起こさなかった言葉に光をあてたこと。それが『全国アホ・バカ分布考』の最大の功績だと思います。
この本はいまでは大学のテキストとしてもよく使われているようです。
言葉は、生きてるんだなあ。生きているからこそ、どんどん変化してゆく。
「正しい日本語はこうあるべき」なーんて、ちゃんちゃらおかしい。
盛衰をくりかえして生きる言葉こそが、美しい!
松本さんにも、ぜひアホ・バカ表現研究を続けていってもらいたいです。
そしていつの日かまたナイトスクープで大々的に、かつ超アホらしくバカバカしく、その成果を発表してくれることを期待しています。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます