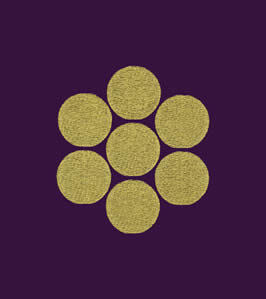◇レッド・ライト(2013年 アメリカ 113分)
原題 RED LIGHTS
staff 監督・脚本・編集・製作/ロドリゴ・コルテス
撮影/シャヴィ・ヒメネス 美術/エドワード・ボヌット 音楽/ヴィクター・レイス
cast キリアン・マーフィ シガニー・ウィーバー ロバート・デ・ニーロ エリザベス・オルセン
◇1974年、ユリ・ゲラー、日本登場
それは、めちゃくちゃ衝撃的な登場だった。
当時、ぼくらが興味を持っていたものといえば、
『エクソシスト』に始まるホラー映画のせいで、人智を超えたなにものか、だった。
ともかく、通常ではありえないようなことに好奇心のアンテナが向いていて、
超常現象だの、UFOだの、幽霊だの、超古代史だのといったムー的世界は、
ぼくの中でかなり大きな部分を占めていた、ような気がする。
そんな中、ユリ・ゲラーがやってきた。
そりゃあ、びっくりもするだろう、だってスプーンが曲がっちゃうんだよ。
それも、ちからを入れないでも、ぐにゃぐにゃに曲がるんだぜ。
たまんないよ、まったく。
しかも、ユリ・ゲラーの凄いところは、テレビに生放送で出演し、
「日本中に念波を送るから、テレビの前の良い子諸君は、
すぐに家の中にある壊れた時計や古くて使ってない時計を持ってきなさい、
送られた念波によって時計の針が動くようになるから」
とかいうんだ。
送ってくるのは、スプーンを曲げるための念波だけじゃなかった。
興奮した。
少なくとも、モハメド・アリ対アントニオ猪木くらいの昂揚はあった。
ぼくは家の中の古い箪笥から、いくつかの腕時計を探し出し、テレビの前に置いた。
もちろん、手にはカレーライスに使ってる大きめのスプーンを握りしめていた。
放送が始まり、ぼくは意識を集中し、一所懸命にスプーンをこすった。
が、曲がらない。
時計の針も動かない。
がっくりした。
けど、こんなはずはないともおもってた。
だって、ユリ・ゲラーは実際に曲げてるんだもん。
びっくりこいたのは、そのすぐ後だ。
クラスの女の子から電話が掛かってきて「曲がった!」と叫んだ。
それだけでなく「時計の針もぜんぶ動いてる!」と電話の向こうで悲鳴を上げてた。
ぼくはスプーンを曲げられなかったことがなんとなく恥ずかしかったけど、
でも、ほんとに念波が届いたんだと驚き、やっぱり嘘じゃなかったんだと確信した。
さらにびっくりこいたのは、翌日のこと。
給食の時間、その子はクラス中のスプーンを次々に曲げ始めたんだ。
教室の中はパニックになり、教師がすっ飛んできて、彼女を職員室に連行した。
「そりゃそうだろう、給食センターになんていって言い訳するんだよ」
という話ではなく、
教師たちは彼女に対し、こういった。
「スプーンがほんとうに曲げられるんなら、先生たちのスプーンも曲げてみろ」
曲げちゃった。
職員室の給食用スプーンは次から次へと曲がり、彼女は疲れ果てた。
学校中が、どえらい騒ぎになった。
同級生の数は320人、中学校の全生徒は1000人にちかい。
えらいこっちゃ、だ。
その日を皮切りに、ぼくらの日々はスプーンと共にあった。
彼女はいとも簡単にスプーンを曲げるが、ぼくも友達もまるで曲がらない。
なにが違うのかはわからないが、どうも超能力というはあるらしいと感じた。
彼女の元へは次々に生徒が集まり、わが中学のユリ・ゲラー現象は頂点に達した。
そんな日々が何日か続いたある日のこと。
あいかわらず彼女の周りには生徒がたかっていたんだけど、
「ね」
と、ひとりの別な女の子が、ぼくに声をかけ、廊下に呼び出した。
いわれるままに廊下に出ると、
いきなり、目の前に給食のスプーンが差し出され、
その子はいとも簡単に、くにゃりと曲げてみせた。
げっとおもった。
眼が点になった。
「内緒だよ」
その子は、にっこりと微笑んで、教室に戻っていった。
今でも、その子の微笑んだ顔は、頭の中にこびりついてる。
で、10年後。
ぼくは、勤め先の会社に、ひとりの青年を招き、とある実験をしていた。
青年は巷ではよく知られた子で、名前はあえていわないけれど、スプーン曲げが出来た。
彼は、会社の会議室で袖をまくり、ぼくが銀座の松屋で買ってきたスプーンを曲げてみせた。
何本も曲げ、何本も捻じり、それどころか折り、いや、弾き飛ばし、
実験に立ち会った女子社員の手に「気」を送り、
自分はまったく触らずに、彼女の持っていたスプーンを飴のように曲げてみせた。
いや、まあ、これもびっくりしたのなんの。
いまでも、立ち会った宣伝部のカメラマンの撮った分解写真が、ぼくの手元にある。
同級生のふたりの女の子にしても、青年にしても、トリックがあったとは到底おもえない。
もちろん、世の中には、トリックでスプーン曲げをしてみせる人間はごまんといる。
けれど、
そのスプーンは、彼が会社へやってくる寸前に、ぼくがまちがいなく買ってきたものだ。
スプーン曲げが超能力かどうかは別にして、信じるよりほかにないだろう…。
まあ、そんなこんなで。
日本に初登場してから30年後、ユリ・ゲラーはまたやってきた。
そう、まるで、この映画のロバート・デ・ニーロ演じるサイモン・シルバーのように。
映画については、すこしだけ、いいたいことはある。
インチキ超能力を暴き続けるシガニー・ウィーバーがどうして前半で死んじゃうのか、
シガニーは「彼は危険すぎるの」と震えるデ・ニーロをまじの超能力者だとおもってたのか、
ふたりの過去にどんな因縁があったのか、
とかいったことで、ほかにもいくつかあるけど、疑問のほとんどは明かされない。
たったひとつだけ、映画の中の真実は、
シガニーの手にしていたカップの中のスプーンが、いつのまにか曲がっていることだ。
映画のスリルは、そこから始まる。
あとは、キリアン・マーフィとデ・ニーロの怒涛の対決に突入していくんだけど、
まあ、それについては予定調和な結末なので、あえて触れる必要もない。
つまりは、たかがスプーン、されどスプーンってことだ。
ちなみに、ぼくは、いまだにスプーンが曲げられない。