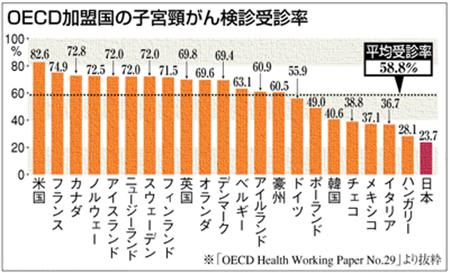コメント(私見):
一昔前までなら、公立・公的病院であっても、常勤の産婦人科医1名の体制で分娩を取り扱うのはごくごく普通のありふれた状況でした。
しかし、長期的に実働の産婦人科医の総数が減り続けて、分娩施設の急減が全国的に問題となり、若い医学生や研修医が専門診療科として産婦人科を敬遠する傾向も顕著でしたので、日本産科婦人科学会も、産婦人科医を増やすためには産婦人科医の勤務環境の改善が急務として3年前に、「ハイリスク妊娠・分娩を取り扱う公立・公的病院は、3名以上の産婦人科に専任する医師が常に勤務していることを原則とする」との緊急提言を発表しました。
最近では、全国的に分娩施設の集約化が進行しつつあり、産婦人科医1~2名体制の公立・公的分娩施設はかなり減ってきていると思われます。産婦人科医1名の体制で分娩を取り扱っている先生方もまだまだ少なくないですが、長年1人医長体制で頑張ってこられた経験豊富な先生方が多いと思われます。今の若い先生方にそれを強要することは絶対に無理だと思います。
日本産科婦人科学会の地道な多方面の努力の成果もあり、最近では「産婦人科を第一に考えています」と元気に答えてくれる若い医学生や研修医の数がだんだん増えてきている印象もあります。多くの大学で産婦人科入局者数が増えているようにも聞いてます。
地域によっては、産婦人科の勤務条件改善の必要性が全く理解されず、1人でも産婦人科医を確保すれば分娩の取り扱いを再開できるという考え方に立って、産婦人科医確保の努力を行っている自治体や病院の事例も、時々報道されています。 もしも、産婦人科の集約化が全く進まないまま、個別の自治体や病院の努力で一人医長体制の産婦人科が復活するだけの状況が続けば、産婦人科の勤務条件はますます悪化するばかりで、母児の安全も確保できませんし、新人産婦人科医も増えないでしょう。 暗黒時代から脱出するために今、我々はどうしたらいいのでしょうか?その一つの回答が日本産科婦人科学会のこの提言だと思います。多くの人に知ってもらいたいです。
緊急提言(日産婦委員会):ハイリスク妊娠・分娩を取り扱う病院は3名以上の常勤医を!
ハイリスク妊娠・分娩を取り扱う公立・公的病院は、常勤産婦人科医3名以上が原則!
平成18年4月7日
都道府県知事
市町村長
公立・公的病院長、病院開設者
各位
日本産科婦人科学会
産婦人科医療提供体制検討委員会
本委員会は、中間報告書の提出に際して、以下の点について緊急の提言を行います。本提言の趣旨をご理解の上、何卒、迅速かつ適切なご対応をお願い申し上げます。
緊急提言
ハイリスク妊娠・分娩を取り扱う公立・公的病院は、3名以上の産婦人科に専任する医師が常に勤務していることを原則とする。
提言の理由
1. 産婦人科医の不足の原因の一つが、その過酷な勤務条件にあることは、既に周知の事実である。しかし、平成17年度の本学会・学会あり方検討委員会の調査においても、分娩取扱大学関連病院のうちで、14.2%が一人医長、40.6%が常勤医2名以下という事実が明らかとなっており、勤務条件の改善傾向は認められていないと考えざるを得ない。
2. それに加えて、地域の病院によっては、産婦人科の勤務条件改善の必要性が理解されず、一人でも産婦人科医を確保すれば、分娩取扱を継続できるという考え方に立って、産婦人科医確保の努力を行っているという現状がある。
3. 産婦人科医を志望する医師および医学生に対して、近い将来の産婦人科医の勤務条件の改善の見通しを提示するためには、この状況を改善する明確な意思を学会が示す必要があると考えられる。
4. 本提言を実効のあるものとするために、各地域の医療現場で働く産婦人科医師は主体的にその活動の場を再編成すべきである。
****** 山梨日日新聞、2009年6月25日
山梨大指導で分娩再開断念 塩山市民病院
「常勤医1人では緊急時対応不十分」
既に予約、市民に不満
医師不足で産婦人科の分娩ぶんべんを中止していた甲州市の塩山市民病院(沢田芳昭院長)が、助産師による正常分娩を始めようとしたところ、同病院に医師を派遣している山梨大から指導を受け、断念していたことが、24日分かった。市民の要望に応えようと早期再開を目指した同病院だが、同大は「常勤医が1人しかおらず、緊急時の対応が不十分」と待ったをかけた。医療関係者は「多くの医師派遣を受ける山梨大の方針に従わざるを得なかったのではないか」と病院側対応に同情するが、市民からは不満の声が上がっている。
同病院によると、産婦人科は当初、山梨大からの派遣医が3人いたが、同大が「小児科医と麻酔科医が確保できない」として全員を引き揚げたため、2007年10月に分娩を中止した。昨年8月、新たに1人が派遣された。
同病院は、分娩を求めた市民ら7万7千人の署名が提出されたことを重視、早期の分娩再開を模索。正常分娩に限り助産師5人が主体的に措置する仕組みをつくり、緊急時は山梨市内の診療所の産婦人科医と、系列の山梨厚生病院の麻酔科医に協力してもらうことが決まった。
今年1月、同病院で検診を受ける妊婦のうち、6月以降の出産予定者を対象に分娩の受け付けを始めた。しかし同大から指導を受けたため、4月に取りやめることを決め、予約者に通知した。
同病院は「診療所は医師1人でお産を扱う。助産師や看護師は多く、正常分娩なら安全と判断した。ただ山梨厚生病院を含め、同大から多くの医師の派遣を受けていて、再開に慎重にならざるを得ない」と説明する。
同大は、同病院を指導したことについて「院内助産でも母体や胎児に異常があった場合、助産師から医師にバトンタッチする。分娩再開には少なくとも常勤医3人が必要」などと説明。常勤の小児科医、すぐに駆け付けられる麻酔科医がいないことも理由に挙げている。
同大が地方病院から医師を引き揚げ、拠点病院に医師の集約を図る背景には医療事故が起きた際の訴訟リスクがあり、「お産に百パーセントの安全を求められる時代。万全な体制で分娩を再開したいが、医師不足で難しい」(同大)という。
ある医療関係者は、県内の多くの病院が、県内で唯一、医師の派遣機能を持つ山梨大に頼っている現状を指摘。「大学の方針に従わざるを得ない傾向を解消するには、医師を増やすことはもちろん、国や県が積極的に大学側へ働き掛けてほしい」と注文する。
分娩を予約した山梨市上之割の村松幸恵さん(36)は「地元で産めると思って喜んだのに残念」と肩を落とす。分娩再開の署名活動を進めた「子育てネットこうしゅう」の坂野さおり代表は「再開してもすぐに中止されては困る。一日でも早くお産ができる環境を整えてほしい」と訴えている。
(山梨日日新聞、2009年6月25日)
****** 毎日新聞、山梨、2009年6月12日
周産期医療:“減床”の波紋/上 NICU
新生児や妊婦の命を守る周産期医療。実は山梨県は全国でもトップレベルの水準を維持している。しかし、国立病院機構甲府病院の新生児集中治療室(NICU)の病床数が6から3に削減される見通しとなり、県内の周産期医療の環境は大きく変わりそうだ。【沢田勇】
県は病床数維持の方針
「スタッフ増やさねば意味なし」
「ピーピーピー……」
県立中央病院(甲府市)の「総合周産期母子医療センター」のNICUでは、アラームが頻繁に鳴る。その都度、看護師が慌ただしく保育器に駆け寄り、異常がないか確認する。透明なカバーに覆われた保育器の中では、手のひらに乗るほどの小さな赤ちゃんが手足を動かしていた。人工呼吸器を付けられた、体重わずか500グラムの未熟児だ。
部屋に9台の保育器が並ぶ。窓のカーテンは日中も閉められたまま。薄暗くして胎内にいるような安心感を新生児に与えるためだ。
新生児はナースコールを押せない。医師と看護師が常に注意を払わなければならず、張りつめた空気が漂う。
夜間の当直医は1人だが、容体の悪い新生児がいる場合は、6人の医師全員が未明まで残ることもある。
「帰れば赤ちゃんが死んでしまうかもしれない。居ざるを得ないのです」。同センター新生児科の内藤敦医長は話す。
看護師も同じだ。加藤京子・同病院主任看護師長は「NICUは高度の技術や知識が要求される。多くの機器に気を配り続けるのは心身共に緊張を強いられます」と話す。
NICU9床の稼働率は95%。常に満床に近い状態だ。現在非常勤1人を含む医師6人と看護師34人が24時間体制で勤務する。
◇ ◇
厚生労働省の人口動態統計によると、山梨県の周産期死亡率は07年3・0(1位)、08年3・2(2位)と、全国トップクラスの低さを誇る。だが、00年代初めまではずっとワーストレベルだった。それが06年(3・7)に3位に急浮上。以降、トップレベルを維持するようになった。
県医務課の山下誠課長は要因として、この総合周産期母子医療センターが設置されたこと、他県に比べ人口当たりのNICU病床数が多いことを挙げる。
同センターは01年開設。NICUに加え、母体・胎児集中治療室も備えた県内唯一の施設だ。これで県内のNICUは一気に9床増え、15床となった。
国立甲府病院も04年に3床増床し、市立甲府病院(3床)を合わせて県内18床となった。07年の厚労省の調査によると、人口や年間出生数が山梨とほぼ同じ佐賀県は3床、福井県は9床しかない。
ところが、5月27日、国立甲府病院のNICUが6床から3床に削減されることを横内正明知事が明らかにした。日大医学部から派遣されている医師2人が9月末に大学に戻されるためだ。
これを受けて県は周産期医療協議会を開いて対策を検討。県立中央病院を3床増やすことで、県全体のNICUベッド数を維持する方針が決まった。
しかし、同病院の内藤医長は「ベッドが増えるなら、スタッフも増やさなければ意味がない」と指摘する。
==============
◇周産期死亡率
周産期(妊娠満22週から生後7日未満)の胎児・新生児の死亡数を年間の総出産数(死産と出産の合計数)で割り、1000例当たりで換算した値。母子保健の重要な指標となっている。
(毎日新聞、山梨、2009年6月12日)
****** 毎日新聞、山梨、2009年6月13日
周産期医療:“減床”の波紋/下 態勢
医師らの確保が生命線
「床数だけ増やされても…」
甲府市の県立中央病院・総合周産期母子医療センターは01年9月に設置されて以降、一度も受け入れを拒否したことはない。
一方で、県内で出産できる医療施設は減少の一途をたどっているにもかかわらず、同センターの新生児集中治療室(NICU)の態勢(非常勤1人を含む医師6人と看護師約40人)は開設以来、ほとんど変わっていない。同センターの負担は大きくなる一方だ。
にもかかわらず、トップレベルの周産期死亡率の低さを維持できる背景について、同センター新生児科の内藤敦医長は、医師や看護師の経験の豊富さと病院間の連携を挙げる。
周産期医療が同センターに集中するため、必然的に医療スタッフは多くの経験を積むことになる。
一方で、満床の場合は他病院に引き受けてもらうなどして医療レベルを確保してきた。特に6床のNICUを持つ国立甲府病院とは「両輪」の関係にある。内藤医長は「誰か来たら誰かを追い出すのでは、救急病床とはいえない」と言葉に力を込める。
しかし、10月からはその国立甲府病院の6床が3床に減り、その分同センターが増床される見込みだ。
国立甲府病院の減床は、3人いたNICU担当医が1人になるためだ。しかし、県立中央病院の医師の増員については、今のところ「医師を派遣してもらっている山梨大医学部の協力が得られるかどうか」(県医務課)と、不透明な状況だ。
「床数だけ増やされても対応できない」。5月28日に開かれた県周産期医療協議会で、県立中央病院の永井聖一郎・母性科主任医長はそう訴えた。新生児科の内藤医長によれば、増床で12床になれば、最低でも常勤医は7人必要という。
一方、文部科学省は、NICUのない山梨大学医学部付属病院に12年までにNICUを最低6床設置する方針を示している。
しかし、最終的にはベッド数よりも医師や看護師の確保が生命線となる。
内藤医長は「今ある山梨の素晴らしい周産期医療をどう維持していくのか、医師だけでなく社会全体で考えていかなくてはならないと思います」と話している。【沢田勇】
(毎日新聞、山梨、2009年6月13日)
****** 読売新聞、山梨、2007年11月2日
産科激減 近くで産めない不安
「オンギャー、オンギャー」
井出ときみさん(30)は笛吹市内の自宅で、生後1か月の長女、杏理(あんり)ちゃんを慈しむようにあやす。「出産を手伝ってくれた先生方には本当に感謝しています」
杏理ちゃんは9月20日に塩山市民病院(甲州市)で生まれた。10月から産科を停止した病院にとって“最後”の赤ちゃん。分娩は、当番の産婦人科スタッフ全員で見守った。古明地文子産婦人科婦長(49)は「(安産で)ほっとした反面、『ああ、これで最後なんだなあ』とさみしさがこみ上げてきた」と話す。
同病院の分娩数は309件(2006年度)。ここ4年で約120件も増えた。山梨大医学部から派遣された産科医3人、助産師8人、看護師5人の態勢が敷かれ、県立中央病院や市立甲府病院が受け入れなかった産婦人科救急が回ってくることもあった。07年度は350件に達することも予想して、助産師や看護師は期待と緊張感を抱いていた。
ところが昨年末、産科医から、「病院を離れることになった」と告げられた。常勤麻酔科医がいないことが理由だった。唐突な知らせに、沢田芳昭院長(67)もしばらく言葉が出なかった。
病院は1月、新規分娩の受け付け中止を伝える張り紙を張った。受け付けを断られ、肩を落とす妊婦を見て、涙を流すスタッフもいた。「『受け入れられない』と言うのは、心が張り裂ける思いだった」。古明地婦長はそう言って声を詰まらせる。
県内で分娩を扱う病院は激減している。県医務課によると、10月末現在、県立中央、市立甲府など甲府を中心に8病院だけ。ここ3年で塩山市民を含む6病院が産科医の派遣元大学への引き揚げなどを理由に中止した。医師不足の中でも、産科は深刻な診療科の一つ。都留市立病院でも来年度の存続が困難な状況だ。
塩山市民病院については、地元の母親らが団体をつくり、存続を求める7万7000人分の署名を田辺篤・甲州市長に提出した。代表の坂野さおりさん(38)は「2人分の命がある妊婦は不安が多い。『近くで産める』安心感は大きい」と訴える。
産科中止は、他の産婦人科施設に影響を与える。同じ峡東地域にある中村産婦人科医院(山梨市)は先月、分娩数の増加を懸念して「分娩制限」を始めた。同医院は年間260件ほどを扱うが、今年は約300件と予測。中村雄二院長(47)は「(塩山市民病院の中止で)近くで出産したいと思う地域の妊婦がうちに来ているのでは」と分析する。だが、取り扱える分娩数には限界がある。
塩山市民病院の2階。かつての産科病棟には、妊婦用の個室や分娩室、新生児室などが残ったままだ。
「いつまでも放置はできない。しかし、別の科にしたら、分娩がなくなることが確定してしまう」
沢田院長は、苦悩の表情を浮かべながら言った。【越村格】
(読売新聞、山梨、2007年11月2日)
****** 読売新聞、山梨、2007年11月6日
分娩取り扱う病院 激減
関係者に聞く
県内で分娩を取り扱う病院が激減している。県内唯一の医師派遣機関である山梨大学は、お産のリスクへの対応が万全でない病院から医師を引き揚げている。一方、自治体や地域病院は、地域バランスへの配慮を訴える。産科の集約化が必要とみる星和彦・同大医学部付属病院長と、来年3月で産科医派遣中止を通告された都留市立病院の大原毅名誉院長に聞いた。
【地域バランス配慮】
大原毅 都留市立病院名誉院長
――県東部唯一の産科が開設以来6年でなくなるのか。
都留市立病院では、分娩予約を8月9日から休止した。集約化するなら地域バランスに配慮すべきと、市長や市議会が10月18日に山梨大医学部付属病院長と横内知事に、分娩継続を求める市民2万15人分の署名を添えて要請書を提出した。18歳以上の市民の87%を占めた署名数の重みは市民以上に十分認識している。
一方で、分娩を扱う態勢について、大学側が安全面で万全を求めることも医師として理解でき、ある意味では板挟みになっている。私の両親は都留市出身で、自分も戦時疎開で小学2年から中学卒業まで過ごした都留は第二の故郷。やむを得ず休止にしたことに非常に胸が痛む。
――山梨大が分娩を継続する条件の一つとしている常勤麻酔科医確保の見通しは。
大学の医局から確保するのは極めて難しい状況と言わざるを得ない。全国的に麻酔科医の数は増えているが、手術の件数も増えており、どこの病院でも不足している。当院は民間、公立の病院を問わず勤務医をあたっている。しかし、麻酔科医は決まった病院に勤務せずに複数の病院と契約するケースも多く、4000万~5000万円の収入を得ているとも聞く。地域医療を守るため、フリーではなく勤務医を探している。
――なぜこれまで常勤の麻酔科医を確保してこなかったのか。
麻酔科医は、当院開設の1990年から非常勤医で対応してきた流れがある。また、帝王切開で緊急手術が必要な年間約10件の重篤患者は、甲府市の県立中央病院に救急搬送するという2次医療圏の病院の役割を支障なく果たしてきたからだ。06年度の分娩数は396で、隣接の大月と上野原の分が140件を占めている。
――医師の派遣元は分散していないのか。
山梨、自治医科、千葉、群馬、東京女子医科、順天堂の6大学から常勤医19人、非常勤41人が派遣されており、分散はしている。最大の派遣元は山梨大で、常勤医は産科の3人を含む9人で非常勤医は36人。非常勤の麻酔科医13人も全員山梨大からの派遣だ。
助産師は今3人いるが5人以上にして安全性を充実させたい。都市と地方の医療の地域格差は歴然だ。医師のリスクが回避されないと地域医療は守れないとの側面は否定できない。
――分娩予約を休止した。余波とアフターケアは。
「地元で産めないのはとても不安だ」などの声が当院に直接寄せられている。8月8日までに予約された方は、昨年度並みの350人ほどいるが、このままでは来年3月20日以降は出産はできなくなる。出産予定がそれ以降の30人ほどの妊婦については、受け入れ可能なほかの病院について責任を持って個別相談と紹介に応じている。(聞き手・林浩也)
【産科集約 やむを得ず】
星和彦 山梨大医学部付属病院長
――県内の産婦人科医不足の原因は何か。
産婦人科医は勤務がきつく、厳しい。高い緊張感を伴うことなどから3Kとも4Kともいわれる。他の診療科より訴訟件数も多く、若い医師が、こうしたリスクが高い科を避けることはある。そして、2004年に福島県内で産婦人科医が逮捕された大野病院事件が起きたのが大きかった。一生懸命やった医師には故意でもなく悪意もないのに。若い医師が産婦人科を希望しなくなったのは当然だ。
さらに、学生が研修先を選べる新医師臨床研修制度が04年に始まり、研修医が大都市の有名病院に集中して、地方には残らない状況となった。その結果、山梨大に04、05年に入った産婦人科医はゼロ。06年は2人、07年は1人だけだった。
山梨大学にきて12年になるが、県内の産婦人科の勤務医は、年平均で3人が退職する。ここ4年間で県内の勤務医は12人前後減少したのに、3人しか補充されていないという計算になる。
――山梨大学医学部の状況は。
産婦人科には一時期、医局員が30人いたこともあるが、新研修制度の導入のころから雲行きが怪しくなった。地域に派遣する医師数の維持に努めてきたが、大学では17人まで減少した。分娩、手術、教育、研究を十分にカバーするには、実際は24、25人は必要なので、今以上に減らすことはできない。
――都留市立病院から産科医を引き揚げざるを得ない理由は大学の事情か。
それもあるが、一方で、各病院には前々から訴訟を避けるため、万全の態勢を敷いてくれとお願いしてきた。都留市立は難しかったようだ。産科では、急に赤ちゃんの心音が聞こえなくなったり、母胎の出血が止まらなくなったりするなど、緊急事態が起きる。15~30分以内に赤ちゃんを出してあげることが必要な時もある。特に、大野病院事件が発生して以来、常勤の麻酔科医や小児科医がいて、助産師もそろっている態勢でないと大変であるとの認識を強く持った。それが整わなければ、医師の生活と健康を守るために、産科の中止を通告せざるを得なかった。
――今後の産科医療はどうあるべきか。
病院の拠点化・集中化を図るしかないのでは。例えば3病院に3人ずつ医師がいるより、1病院9人のほうが、1日当たりの医師の負担は増えても、当直は9日に一度で済む。郡内では、分娩を扱っている3病院を1~2病院にすべきと考える。もし3病院の医師を集約して産婦人科を立ち上げることができたら、素晴らしい診療科になると思う。
また、産婦人科医の維持には給与など、待遇の改善が必要だ。現行の医療保障制度を改め、医師側に過失がなくても患者側に補償金が支払われる無過失補償制度を早急に整備すべきとも考えている。(聞き手・林英彰)
◆大野病院事件 福島県大熊町の県立大野病院で04年12月、帝王切開手術を受けた女性が失血して死亡。同県警は06年2月、業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反の容疑で担当した産婦人科医を逮捕した。医師は起訴され、現在、福島地裁で公判中。
◇ここ3年間 6病院中止
県内で分娩を取り扱っているのは8病院。県医務課によると、ここ3年で、大月市立や上野原市立、白根徳洲会など計6病院が取り扱いを中止した。
一般の救急医療や入院医療サービスを提供する2次医療圏別にみると、分娩を扱う病院は甲府市などを含む中北に5病院、富士・東部に3病院。峡南、峡東の両医療圏はゼロという状況だ。
厚生労働省によると、県内の産婦人科医の数は2000年末には88人だったが、02年、04年はそれぞれ87人、85人と微減傾向にある。一方、山梨大で勤務する産婦人科医の数は、1998年の22人から01年には30人にまで増加。しかし、その後は減少を続け、05年に20人を切った。07年は17人にまで減っている。
◇求められる現実直視◇
医師を守る立場の大学も、市民のために産科存続を目指す地域病院も、医師不足にあえいでいるのは同じだ。星院長、大原名誉院長とも互いの事情を知り尽くしており、インタビューでは相手への気遣いともとれる発言が目立った。
そもそも、9月いっぱいで分娩の扱いを停止した塩山市民病院や、都留市立病院が産科を始めたのは、地域での産科医療の強化の必要性を感じた星院長が医師を派遣したからだ。星院長にとって、医師の引き揚げが苦渋の選択であることは想像に難くない。
現状のままであれば、医師の集約化が不可避と言えそうだ。各自治体は、県内の医師不足の現実を直視し、そのうえで地域として最良の選択は何かを、考える必要があると思う。(英)
(読売新聞、山梨、2007年11月6日)
****** 毎日新聞、山梨、2007年11月22日
お産難民のゆくえ:求められる「助産師」像/上
分娩体制崩壊の危機
産婦人科医の確保に限界
全国的に産婦人科医不足が進み、県内でも分娩(ぶんべん)できる医療機関が激減する中、妊婦が安心して身近な施設で出産できない「お産難民」が現実になりつつある。県は医師確保に奔走する一方、助産師の存在に着目し、妊婦の健診を行う「助産師外来」の検討に入った。ただ、県内の医療機関における助産師の充足率は全国最低レベルという問題を抱える。助産師はお産難民を救えるのか――。可能性を探った。【吉見裕都】
県東部で唯一出産ができる都留市立病院(都留市)の関係者らが10月中旬、市民約2万人の署名を携えて山梨大医学部付属病院(中央市)の星和彦病院長を訪れた。きっかけは、都留病院の産婦人科に医師を派遣している付属病院が示した08年4月からの引き揚げ方針。付属病院の医師不足が理由だが、都留病院は同3月から分娩中止に追い込まれるため、関係者が医師の派遣継続を付属病院に訴えた。
集まった署名は、約1カ月で18歳以上の市民の9割近く。短期間での盛り上がりに、市議会の藤江厚夫議長は語気を強めた。「市民も切羽詰まっている証拠だ」
同様の理由で、9月末で分娩を取りやめた甲州市の塩山市民病院でも、医師の派遣継続を求めて約7万7000人が署名した。
30年にわたり甲府市下石田2で開業している「杉田産婦人科医院」(杉田茂仁院長)も、10月から分娩を取りやめた。1人で対応してきた杉田院長(70)は「365日24時間働き、人間的な生活はできないと覚悟してきたが、年齢的に厳しくなった」と話す。長男(40)は千葉の病院で産婦人科医として勤務するが、「医師1人の開業は安全面で懸念を持っているようだ」とした。
県内の分娩可能な医療機関はここ10年で半数以下の17カ所に減少。うち9カ所が甲府市内に集中している。
× × ×
困窮の度合いを増すお産現場の改善に向け、分娩場所の拠点化や医師の集約化が議論に上っている。国立病院機構甲府病院の外科系診療部長で産婦人科医の深田幸仁医師(44)は「若い医師が安全に安心して働ける勤務環境を整えないと産婦人科医は増えない」と訴え、この動きを支持する。
受け入れ病院が決まるまでの照会件数は、消防庁によると、県内は04年のゼロから06年は▽1回1件▽3回2件▽5回1件――と急増した。集約化により、既に分娩場所のない峡南地域など都市部以外の妊婦に、さらなる長距離移動を強いることにつながりかねないとの指摘もある。
県産婦人科医会の武者吉英会長は「2、3年後には県内の分娩体制が崩壊する恐れがある」と警鐘を鳴らす。県は、県内で医師として働くことを条件にした奨学金制度の導入などに着手したが、限られた産婦人科希望の学生を全国で奪い合う構図に「限界がある」との声も漏れる。
そんな中、横内正明知事は9月議会で助産師外来設置の検討を表明した。病院によっては1人の医師が1日で70人もの妊婦に行う健診を助産師に担ってもらい、医師の負担を減らすのが狙いだ。医師不足をカバーしようと、同医会も助産師を養成しやすい仕組み作りを行政に働きかけ始めた。「医師が一人前になるには何年もかかる。助産師養成の方が早く、頼もしいパートナーになり得る」。武者会長も期待を寄せる。
………………………………………………………………………………………………………
助産師 保健師助産師看護師法(保助看法)で定められた国家資格。助産師になるには、大学の看護学科で学んだり、看護師資格を取得して「養成所」に1年間通った後、国家試験に合格する必要がある。保健指導や正常分娩の介助、子宮収縮の状態を調べる「内診」などの助産行為にあたることができる。
(毎日新聞、山梨、2007年11月22日)
****** 毎日新聞、山梨、2007年11月23日
お産難民のゆくえ:求められる「助産師」像/中
助産師主導に賛否両論
医療事故時の対応に課題
「生まれた赤ちゃんをすぐに母親の胸に置くと、赤ちゃんは慣れ親しんだ心音を聞き、泣きもせずに静かに過ごします。へその緒も急いで切る必要はなく、1時間もすると自分でおっぱいに吸いつく。この時間が母子にかけがえのないきずなを築かせるんです」
今月2日、甲府市内で行われた講演会。自然分娩(ぶんべん)を中心に行っている上田市産院(長野県上田市)の広瀬健副院長は、分娩のあるべき姿として熱っぽく語った。
一方で、一般的な病院での分娩は「訴訟に対する『医師の安全』を優先している」と疑問を表明。妊娠から分娩、産後まで長期的に助産師が主導し、異常出産時に産婦人科医がバックアップする体制の確立を訴えた。
ただ、助産師が分娩まで行う助産院は、県内に2施設しかない。その一つ、韮崎助産院(韮崎市富士見1)を訪れると、甲府市善光寺2、主婦、田中真理さん(30)が助産師の雨宮幸枝さん(65)と紅茶を飲みながらくつろいでいた。「病院での分娩は不自然さを感じます。本来人間に備わっている力でお産をしたい」。田中さんは助産院を選んだ理由をこう話し、雨宮さんに絶対の信頼を置いている様子だった。
出産をスムーズに行うため、病院分娩では陣痛促進剤がよく使われ、会陰切開も少なくなく、赤ちゃんは母親と離れて数日間、新生児室で過ごす。助産師による自然分娩を望む妊婦もいるが、甲州市のサークル「子育てネットこうしゅう」の坂野さおり代表(38)は「妊婦と病院で産みたいスタイルにズレがあるが、出産施設の減少で選択肢がない」と妊婦の悩みを代弁する。
一方、医師側は「助産師主導」の早期展開に懐疑的だ。県産婦人科医会の武者吉英会長は、情報化の進展で妊婦は高度な出産知識を持っているとして、「助産師に妊娠から産後まで任せるといっても、医療事故まで受け入れられないだろう。仮に妊婦にその気持ちがあっても、夫や両親といった周辺は納得しない」と分析。韮崎助産院でも分娩直前に家族に促され、最終的には病院でお産をする妊婦も時折いるという。
国立病院機構甲府病院の産婦人科医、深田幸仁医師(44)は、さらに「リスクを背負うことになり、助産師自身が主導を望んでいるかどうか」と指摘する。今年2月には新生児の死亡は助産師の過失が原因として、横浜市の医院が慰謝料など5320万円を求められる訴訟が起こされ、06年には栃木県の助産所の助産師が新生児の死亡事故で提訴され、3700万円で和解している。
武者会長は「医師の厳しい勤務環境が続く中、助産師に仕事が流れるなどという思いはなく、助産師の活躍の場が広がるのをむしろ歓迎する」と話す。ただ、深田医師は「助産師主導」について、「検討する前に、妊婦と助産師の意向を確認する必要がある」と述べ、前のめりの議論にくぎを刺した。【吉見裕都】
(毎日新聞、山梨、2007年11月23日)
****** 毎日新聞、山梨、2007年11月26日
お産難民のゆくえ:求められる「助産師」像/下
医師との分業体制
“ダンス踊れる”連携必要
「スタッフがついてこれるか、いつも気にしています」
助産師外来を導入している渕野辺総合病院(神奈川県相模原市)の尾崎信代看護師長は10日、甲府市であった県母性衛生学会で講演後、参加者の質問にこうもらした。
助産師外来とは、妊婦への健診や保健指導を助産師が行い、分娩(ぶんべん)は医師の責任下に置く分業体制で、同病院は05年10月に開設。尾崎さんは「異常の発見ではなく、お産が正常に進むように妊婦の『セルフケア』を誘導していくのが助産師の役割」と述べ、医師との分担の必要性を説く。
課題は「マンパワー」。同病院の常勤助産師8人のうち外来は4人で担当しているが、実際は尾崎さんが8割を担う。長く医師のサポート役だったこともあり、助産師が責任を負う外来に行きたがらないという。
助産師のかかわり方として、▽助産師主導の分娩▽病院の助産師外来▽地域で開業した助産師が健診、分娩は病院――などさまざまな方法が考えられ、医師の仕事量が減るのは間違いない。これにより、激務のため敬遠していた医学生が産婦人科医を志す可能性は高い。
しかし、医師と同様、絶対数が少ないのは助産師も同じだ。助産師の数は全国でピーク時5万人を超えていたが、今は2万人台で、県内も158人(06年12月末)と減少傾向。日本産婦人科医会によると、県内の助産師の充足率(06年3月)は診療所が16・28%と全国ワースト2位、病院も71・33%で同4位と低水準に陥っている。
県内で助産師になるには、県立大看護学部か山梨大医学部看護学科で学ぶしかないが、枠は十数人分しかなく、何人かは県外へ出てしまう。他県には看護師を対象に1年間で助産師資格が取れる「養成所」があるが、県内にはない。県立大の伏見正江准教授(助産学)は定員や教員の増加を訴え、県産婦人科医会の武者吉英会長は行政による養成所設置を提案する。
助産師の熱意の醸成も重要だ。活躍の場が広がることを期待する助産師ばかりではないが、韮崎助産院(韮崎市富士見1)の助産師、雨宮幸枝さん(65)は訴える。「妊婦さんにはいい状況といえないが、助産師が見直されるチャンス。母子の命を守る厳しい仕事だが、お産の喜びはたまらないはず」。尾崎さんも「自分の技術でお金をもらうんだからプロ意識を持って」と強調する。
県内でも、医師と助産師が連携する動きが出てきた。近くの産婦人科医、中島達人医師(58)や国立病院機構甲府病院の深田幸仁医師(44)と連携する雨宮さんは「恥をかいてもいいから早めの相談。状況が悪くなってからではお医者さんも困るでしょう」と相互連絡の“ツボ”を話す。
ただ、深田医師は懸念する。「新生児集中治療室(NICU)のある病院がない郡内地域では医師もバックアップできない。そもそも忙しい医師が十分に助産師を支えられるのか」。医師確保も重要というわけだ。
自分の体験も踏まえ、雨宮さんは医師との協力関係をたとえた。「医師と助産師はチークダンスを踊れるような関係じゃないといけないんですよ」【吉見裕都】
(毎日新聞、山梨、2007年11月26日)
****** 毎日新聞、長野、2009年6月25日
小諸厚生総合病院:産婦人科診療を再開
常勤医復帰で--来月1日から
常勤医の病気療養に伴い4月以降の分娩受け入れを中止していた小諸市の小諸厚生総合病院が、常勤医が復帰したことから、7月1日から産婦人科の診療、妊婦検診を再開することになった。23日からは、合併症がなく正常な分娩に限定して8月以降の予約の受け付けを始めた。
常勤医1人が病気で休んだ後、もう1人の産科医師が5月に退職したため、信大病院などの医師2人が週2回、小諸厚生総合病院の婦人科の診療を担当。4~9月の分娩予定の約160件は、これまで佐久市の病院などに紹介してきた。
今後は当面、月10~15件の出産を予定。医師の確保ができ次第、順次態勢を整えていくという。
【藤澤正和】
(毎日新聞、長野、2009年6月25日)
****** 信濃毎日新聞、2009年6月23日
小諸厚生総合病院 8月から条件付きで分娩再開
4月以降、出産の受け入れを見合わせていた県厚生連小諸厚生総合病院(小諸市)は23日から、出産予定日が8月上旬以降で、合併症がなく出産リスクも低い妊婦に限り、分娩の予約を再開する。3月から病気療養していた産婦人科の常勤医1人が復帰するためで、7月1日からは妊婦健診など産婦人科の診療も再開する。
同病院では3月以降、十分な数の医師を確保できなかったため、4~9月の出産予定者のうち150人余を佐久市立国保浅間総合病院などに紹介していた。4月末にはもう1人いた常勤医が退職し、5月からは信大病院(松本市)と県厚生連篠ノ井総合病院(長野市)の医師2人が非常勤で婦人科に限り診療をしてきた。
分娩は復帰した医師が担当し、受け入れ件数は1カ月当たり10~15件から始める。今後の対応は医師確保の状況などで判断していく。リスクのあるケースは近隣の病院に紹介する。小諸厚生の中村みゆき助産師長は「病院として受け入れが可能か、状況や経過を把握する必要があるので、お産を希望する人は来院前に必ず電話をしてほしい」と話している。
(信濃毎日新聞、2009年6月23日)