


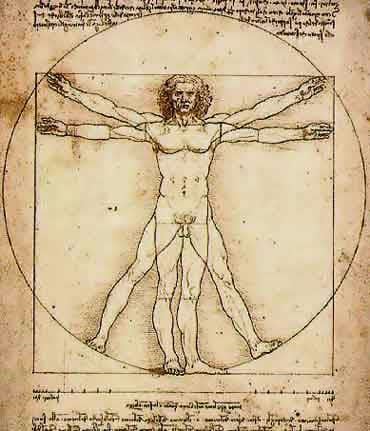
由良三郎 (1921-2004)は晩年になって小説を書き始めた推理作家である。処女作「運命交響曲殺人事件」で第二回サントリーミステリー大賞 (1984)を受賞した。その他、『ある化学者の殺人 』( 1985)、『象牙の塔の殺意』(1986), バイアグラ殺人事件 (1999)など多数の作品がある。本名は吉野亀三郎。東京銀座生まれで、旧制第一高等学校から東大医学部に進学した。卒業後は、横浜市大教授を経て、東大医科学研究所ウイルス学教授をつとめ、1982年に定年退官している。れっきとした医科学者であった。
この人の著に『ミステリーを科学したら』というエッセイ集がある。推理小説に登場する殺人などのトリックを話題にまとめたものである。この中に「権威」という掌編があり、読んでみると東大医学部教授の悪口がたくさん述べられている。以下引用する。
『平成二年三月八日の新聞を読んでいたら、驚くべき記事にぶつかった。それは、厚生省の中央薬事審議会が、唾液腺ホルモン注射剤パロチンの老人性白内障などに対する効力を再検討した結果、無効と断じたので、この薬の製造販売は中止され、一ヵ月以内に製品は回収されることになったという発表である。唾液腺ホルモンというのは、故東大名誉教授O博士が発見したもので、氏はその化学構造も決定し、さらにそれが骨の生成を助けるなどの生理的作用があることも見出だし、それら一連の発見により昭和十九年に帝国学士院賞恩賜賞、昭和三十二年には文化勲章を受けられているのである。その製品はパロチンという名で発売され、国内のどの病院でも採用され、広くいろいろな方面に応用されていたはずである。それが全然無効だというのだ。これが驚かないでいられようか!もっとも、この薬に関しては、どうも理解できないことが多々あった。その一つは、それだけ立派な発見であるのならば、当然世界中の医学教科書に紹介されていなくては嘘なのだが、それから五十年近く経った今日までどんな外国の医学書にも出ていない。外国の病理学の専門家に訊いても、誰も唾液腺ホルモンというものの存在を知らないのである。あまり変なので、昔O博士と共同研究をしていたK博士に尋ねてみた。K博士はO博士の指導を受けて唾液腺ホルモンの骨生成促進作用を研究し、連名で論文を発表している。そのK博士は、「唾液には気を付けなくてはいけないよ。昔から怪しい話は眉に唾を付けて聞けと言うじゃないか。私としてはそれ以上は教えられない」と答えられた。なんだか釈然としない話である』(以上引用)
ここに出てくるパロチン(parotin)は耳下腺から唾液とともに分泌されるペプチドホルモンで、骨の発育、白内障の予防、老化防止などの作用を持つといわれていた。これの発見と薬の開発は緒方知三郎 (1883-1973)、すなわちO教授であった。緒方洪庵の孫で1954年にパロチンなどの成果で文化勲章を受けた。当時の内分泌学界での最高権威であった。昔に発見された薬で20年以上生き残るものは少ない。新しい薬が開発されるためもあるが、「権威」者が亡くなったころに、童話の「裸の王様」に出てくる子供達のような医者が「効かない、役に立たない」と言い始めるからである。しかし、この緒方の弟子というK博士の話は本当だろうか?由良の『権威』の中には、他にも効かない薬として、やはり東大医のT博士とA博士が開発した強心剤Vの話などが出ている。なんとも情けなくなってくる。
由良はさらに『教授会』というエッセイでも東大医学の教授の悪口を露骨に述べている。教授会での人事選考におけるK教授の信じられない発言記録である。。
私も決戦投票ではAに一票を入れようと考えていた。彼の業績が他の二人より優れていると判断したわけではない。私にはそんな判断は無理だった。ただなんとなくそう決めたのである。強いて理由を挙げれば、Aを個人的に知っていたことと、他の二人には面識がなかったというだけのことだ。恥ずかしながら、こちらもあまりまっとうではなかった。そのときK教授がさっと手を挙げて発言を求めた。彼の言葉をできるだけ忠実に再現してみよう。それはこうだった。「どうも皆さんはAくんを推しているようだがね、僕はあいつみたいな人格劣等な男を、この教授会の一員に迎えることには、絶対に反対なんだ」これには一同もびっくり。さすがに議長が厳しいロを利いた。人格劣等とは聞捨てならないが、どういうことからそう言うのかと。するとK教授が眉間にしわを寄せつつ、ではお話ししましょう、と言って語ったことを聞いて、一同はまたまた驚いた。
「あいつが大学を出て、ここの助手として就職してきた直後だった。今から二十年も前の話さ。ここで恒例の秋の運動会があった。そのと特も最後の種目は全員参加の紅白玉入れだ。用意ドンで、一方は白、もう一方は赤の玉を宙吊り瞳に投げ入れる。そして、何十秒かの後に、止めの合図の空砲が鳴った。さあそのときだよ、諸君! ……Aはこそこそと簸に近付いて、手にした赤い玉を二つも簸に放り込んだのだ。……審判員が一人ずつ赤白の龍に付いて、龍から玉を出すと、皆が声を揃えて数える。なんと、その結果は、赤が一個多くて、赤の勝ちだった。僕は白だったので、実に残念だった。そのときの悔しさは、今でも忘れられないよ」
面食らってきょとんとした議長が、人格劣等説の根拠はそれだけか、と念を押して質ねると、K教授はしかつめらしい顔でうなずいた。さすがに、どの教授も、この話には付いて行けなかった。そして投票の結果は、Aが当選した。Aの名誉のために断っておくが、彼は稀に見る人格者であって、どんな人にも愛想がよく、その点大学教授としては例外的と言ってもいいくらいだ。むしろ、どっちかと言ったら、K教授のほうがよっぽどおかしかった。だがそのK博士も亡くなられてからすでに久しい。ついでに追加すると、K博士は日本で最初にある学会を創設した功労者で、その道では世界的にも有名な学者だったのである』(以上引用)
1960年代の大学紛争の頃、団交で大学教授が世間の常識に外れた発言をするので、学生は彼らを「専門バカ」と呼んだが、パロチンの話は「専門もバカ」だったのではないかと思わせる。しかしながら当時においても、東大の先生だけがバカだったわけはなく、他の大学の先生はもっとバカだったのだろう。ただ、東大というそびえ立つ「権威」のために、世間や学会に与えた迷惑も大きかったようだ。こういった「権威者」が死んでいなくなるまで、効かない高価な薬を飲まされつづける一般庶民こそ、いい迷惑だった。

ベンジャミン・ウォレス『世界一高いワイン「ジェファーソンボトル」の酔えない事情-真贋をめぐる大騒動』
(原題 「The Billionaire’s Vinegar」) 佐藤桂訳 早川書房 2008年
この書は、ニューヨーク在住のルポライターによるワインの偽物にまつまわるドキュメントである。1985年、ロンドンのクリスティーズで一本の赤ワイン「シャートー・ラフィット1787」が競売にかけられた。この瓶には「Th J」と刻印があり米国第3代大統領トーマス・ジェファーソンが購入したワインであるとされていたが、10万5000ポンド(当時の為替で約3000万円)でアメリカの実業家キップ・フォブズにより落札された。ワイン一本での、この記録はいまだ破られていない。その提供者はドイツ人のハーディー・ローデンストックという著名なワイン収集家であった。何本ものジェファーソンボトルが、パリの古いビルにあるレンガの壁に囲まれたワインセラーの中で、発見されたとローデンストックは言う。ローデンストックはワイン業界のセレブであり、ワイン愛好家の文化人とも多数の交流があった。この書の前半は、ワイン好きだったジェファーソンやビィンテージワインを収集するアメリカの成金などの話が続く。しかし、後半はローデンストックに焦点を当て、ページが進むにつれてこの人物が偽ワイン造りのとんでもない詐欺師ではないかと思わせる展開となる。なにか推理小説を読むような雰囲気である。
ローデンストックを疑って、敢然と挑戦したのはビル・コークというアメリカの実業家である。彼もオークションやディラーを経てローデンストックから何本もの怪しげなビィンテージを掴まされていたのである。コークは金に糸目をつけずに、これらが本物か偽物かを調べはじめた。放射性元素のセシウム137を調べる分析方法も試したが、決定的な証拠は得られなかった。しかし瓶の刻印の削り跡を顕微鏡で観察すると、それは当時の器具を用いてできたものではなく、最近の電動工具を使ったものであることが判明した。瓶の中身を化学的に調べなくても偽物であることが、はっきりとわかったのである。ローデンストックの他のジェファーソンボトルも全くの偽物だった。コークは、かくして2006年にマンハッタンの連邦裁判所に訴訟をおこした。本書の経緯を読むと、訴訟の勝敗は簡単につくと思われたが、ローデンストックもしぶとく反撃したようで、裁判は灰色の決着のようであった。ローデンストックは2018年5月 19日に亡くなった(https://www.winereport.jp › archive)。
1991年ごろ、ローデンストックはミュンヘンでアンドレアス・クラインという人の家を借りていた。建物の半分には家主のクラインの家族が住んでいた。ここでローデンストックは「絶対に借りて欲しくない借家人」の典型的な行動をとる。以下、訳本から抜粋して紹介(一部省略)。
『ローデンストック夫妻は建物の半分を使い、1997年からはクライン夫妻がもう半分に入居して、薄い壁一枚を共有して暮らしはじめた。アンドレアス・クラインから見たローデンストックは奇想天外な男だった。話をすれば、出しぬけに「友人の」フランツ・ベッケンバウアーやゲアハルト・シュレーダー首相、ヴオルフガング・ポルシエ、ミック・フリック(メルセデスーベンツの一族)といった名前がいつも出てくる。あまりにも知り合い自慢が過ぎるので、ローデンストックは自分というものに自信がないのだろうと強く印象づけられた。
ときおりローデンストックがワインを一本譲ってくれることがあった。そんなときは、必ずなんらかの頼みごとをされた。あるときは、一階の部屋ににおいが入りこむから裏庭でのバーベキューをやめてもらいたいと言った。またあるときは、壁から音が筒抜けなので、階段の昇り降りをもう少し静かにやってくれと頼まれた。静かに歩けるようにと、南スペインで買ったスリッパを一足くれたこともある。クライン夫妻のほうが、ローデンストックが発する音に対して寛容だった。在宅時は地下室の方向
から何かを叩く音がよく聞こえてきた。
やがて、共同で使っている屋根裏部屋にカビが生えるという困りごとが発生し、クライン夫妻は2001年、雨漏りする屋根を葺きなおし、屋根裏部屋も新しく作り変えることに決めた。ドイツの法律では、借主の許可も取る必要があった。それなのにローデンストックは、最初は協力すると言ったにもかかわらず、そのうち金銭や賃貸料の値引きを要求しはじめた。
クラインとローデンストックは法廷で争うことになった。カビの件でローデンストックは一時的に近くの高級住宅地にある高額な賃料のペントハウスヘ移り住んだが、家具などの所有物はほとんど残したまま、クラインヘの家賃の支払いを止めていた。ローデンストックは明け渡しには15万ユーロの費用が生じるとクライン夫妻に告げ、そのうえ裁判では証拠を提造した、とクラインは言う。ある時点で、書類上の家主であるクラインの義理の母へ宛てた手紙のコピーを法廷に提出したが、それを公然と、しかしながら不注意な日付に改京していた。手紙の住所に、日付の時点では存在しなかった郵便番号が書かれていたのである。
裁判は長引いた。クライン夫妻はふたりの幼い子どもを抱え、まともな屋根のない、壁にカビが生えた家に住んでおり、長引く訴訟を戦い抜くのは厳しかったが、いまのところ裁判所はローデンストックを立ち退かせることも改装に取りかかることも許可しようとしなかった。悪夢のような借家人をどうやって追い出そうかと困り果てていたクラインは、予定している改装工事は、どちらにせよ留守がちなローデンストックにはなんの迷惑もかからないと主張していた。ローデンストックはそれに対し法廷で、自分のほかの家は休暇用のアパートメントにすぎず、本拠地はミュンヘンであると証言した。アンドレアス・クラインは、おそらくドイツの税金を払っていないローデンストックが居住地はミュンヘンだと断言したことを当局が知れば、大変な関心を寄せるに連いないと思った。クラインはローデンストックの法廷証言のコピーを税務当局へ提出した。
情報を流してから三年近くがすぎた2004年12月、ようやく税務警察が訪ねてきて、ローデンストックがすでにこの家に居住していないことを確認したいと申し出た。税務警察はすでにローデンストックに関連する住所の一覧を作りあげ、現地当局と共同で捜索をはじめていた。ローデンストックの事務所となっていたアパートメントは、すぐ近所にあり、クラインは税務当局が車三台ぶんもの書類を持ち去るのを見ていた。捜索の三日後、そして裁判がはじまってからまる三年後、ローデンストックは比較的少額である15000ユーロの立ち退き料と引き換えに、ようやくクライン夫妻の家を退去することに同意した』(以上)
この引用部は、クラインが訴訟を知ってローデンストックの悪口を書いた手紙(メイル)をコークに送ったものを資料にして書かれている。悪口の効用の一つはfree rider『ただ乗り野郎』の情報を広めて、おたがいに被害に合わないための社会的な知恵である。これは借家問題といった些細な事件とはいえ、一事が万事ということもある。これを世間の人が知っておれば、ローデンストックの贋ワインにひっかかる事もなかったのではないだろうか。少なくとも無防備に信頼する事はなかったはずだ。
この本にはビル・コークという執念の人が登場し、ローデンストックを最終的には監獄に送ろうと訴訟を繰り返す。民事訴訟は消耗戦で結局金の多い方、すなわち弁護士費用を最後まで払える余裕のある方が勝つ。だから貧乏人はどんなに正義や理非が通っていても勝てない。盗人にも三分の理といって、相手はなんだかんだと言うのである。両方の弁護士はその構造を知っているので、どちらもどこで手を打つかは訴訟の最初から計算してやっている。裁判官も同じ穴の狢でその辺の事が分かっており、適当に双方が消耗したときに、和解を提案するのである。しかし、コークは大金持ちで、ワインの購入費以上の費用を使って訴訟を継続し、「趣味」の一つとしてローデンストックに挑戦した。一種のサイコパスといえる人物であるが、それでもはっきりした勝利は掴めなかった。
町山智浩 『アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない』文芸春秋 2008
アメリカは自由の国だ。考えられないようなバカな事をする自由も堂々と許されている。これは’00年代における、アメリカで観察されたおバカを町山智浩が特集した一冊である。悪口がたくさん並べられているが、その内のいくつかを要約して紹介する。作者の町山智浩は1962年、早稲田大学法学部卒業、映画評論家、バークレー在住とある。映画評論の他に社会評論も多い。

● GMのおバカさん
GM(ゼネラルモーターズ)は20世紀の終わりに、10億ドルもかけてEV1(電気自動車)の開発•販売を行っていた。カリホルニア州のZEV「ゼロ排ガス自動車計画」に応じたもので、時代を先取りする画期的なプロジェクトであった。EV1は1000台製造され、リースされたが、評判はすこぶるよかった。都市の環境に良い(ただし発電所のある田舎が犠牲になっている)、静かで、速く、乗り心地満点というわけだ。ところが、21世紀に入ってGMは全てのEV1を回収し、スクラップにしてしまった。その理由はバッテリーの安全性に問題があるというものだった。しかし本当の理由は別にあった。それは、当時のブッシュ大統領が石油業界と組んで、ZEVを撤廃させたのである。ガソリンを使わない車なんて、とんでもないというわけだ。GMはかわりに、高価でガソリンを食うばかでかいSUV(スポーツ多目的自動車)の製造販売に力を注いだ。その後、石油の高騰とユーザーの大型車離れで、GMの売れ行きはガタ落ちとなり、2009年6月ついにこの巨大企業は倒産した。時代を見すえて、地道に電気自動車の開発を続けておれば、GMはいまでも世界のトップランナーで居続けていたかもしれない。
● ポラロイド倒産と社員の悲劇
インスタントカメラの代名詞だったポラロイドはデジタルカメラに負け、2001年に約9億4800万ドルの負債を抱えて経営が破綻した。日本では、例えば富士フィルムなどがカメラのデジタル化に備えて、多角経営に路線転換したのに対して、ポラロイドの経営陣は適切な対応をしなかった。97年には60ドルだった株価はタダ同然に暴落した。わりをくったのは、ポラロイドの社員と元社員だ。彼らはESOP(従業員持ち株制度)により給料の8%で自社株を買わされていた。しかも、社員は株を売ることを許されていなかった。一方、破産管財人は、社員の株を社員の承諾を得ずに売却することができた。ポラロイドの社員と元社員6000人の株は、1株9セントでたたき売られた。社員によっては2000万円も失った人がいる。さらにポラロイドは破産法に基づき、年金と健保の支払い義務を放棄した。アメリカには厚生年金はなく、各企業が独自に年金を運営しており、健康保険も民間の高い保険しかないので、企業が保険料を一部補助している。ところが経営負担になるそれらの福利厚生費を、破綻した会社は削減することが破産法で許されているのだ。民間の保険会社は医療費のかかる老人を加入させないので、すでに引退した高齢の元社員は苦境にたたされた。ポラロイドは02年にOEP(ワン・イクイティ・パートナー)社に買い取られた。OEPは、年金や保険の支払いを放棄して身軽になったポラロイドからさらに赤字部門を切り捨てた。2年後、そのライセンスを受けていたミネソタの会社がポラロイドを買収した。金額は4億2600万ドル。OEPが買った値段の2倍だ。株価は12ドル8セント、ポラロイド社員が無理やり売らされた9セントの134倍になっていた。こういった不条理はポラロイドだけでなく、全米に拡大している。ブッシュ政権になってからアメリカを代表する大企業の経営が次々に破綻した。自動車会社のビッグ3、GM、フォード、クライスラーは倒産するか虫の息だ。頼みの綱のPBGC(年金支払保証組合)は、すでに4500億ドルの赤字を抱え、もはやこれ自身が崩壊状態である。ポラロイドの元社員4000人は、年金や保険料の支払い拒否をした会社を訴えた。幸いに彼らは裁判で勝った。そして、30年以上働いてきたポラロイドの元社員たちが、その代償として受け取ったのは、わずか47ドル(約5000円)だった。
●サブプライムローンと懲りない人々
ヨーロッパからアメリカに移住してきた人々の「アメリカン・ドリーム」は、まず自分の家を持つことだった。ブッシュ大統領が2004年に提唱した低所得者の住宅購入支援政策も「アメリカン・ドリーム・イニシアティヴ」という。そして01年から05年まで空前の不動産バブルが吹き荒れた。引き金を引いたのはITバブル崩壊である。このとき株式市場が暴落した。政府は景気活性化のために金利を史上最低レベルに引き下げた。ローンの金利も下がったので、そこから住宅購入ブームが始まった。マイホームを求める人だけでなく、株に代わる投資対象を求める投資家も住宅市場に殺到した。2002年ごろから、住宅ローンのハードルが急激に低くなった。年収400万円でも4000万円のローンが組めるようになった。頭金なし、金利の低い変動ローン、利息のみローン、書類審査なしの自己申告ローンなど、いわゆるサブプライム(低信用ローン)で低所得者を誘惑した。もちろんこういうローンはリスクが高い。変動ローンは金利に合わせて利子率が変わる。利息のみローンは5年目以降は元本返済が上乗せされる。自己申告ローンは収入を多めに申告すれば払い切れないローンを抱える。でも、このまま不動産価格が上がれば、その差額で儲かるから返せるはずだ。借り手も貸し手も、みんなそう信じていた。このデタラメな貸付のウラでは、投機筋が動いていた。ITバブル崩壊後、投資銀行は住宅ローンをデリバティブとして証券化したのだ。そして住宅ローン業者に「どんどんローンを発行すればいくらでも買うぞ」とけしかけた。需要があるからローン業者はデタラメに貸しまくった。投資銀行は、リスクの高いローンを細かく分散させて他のローンに混ぜて「薄めて」売った。それが世界中に広がった。資産のない24歳の移民青年に、2億円も貸し付けた例も知られている。しかしバブルがはじけて、サブプライムの崩壊は金融危機にまで拡大し、リーマンショックを引きおこした。ドルは下落し、世界中の株は一斉に暴落した。サブプライムの借り手は、全体の30%以上もいて、多くが返済できずに家を差し押さえられホームレスになった。結局、このバブルで儲かったのは不動産屋と売り抜けた一部の投機筋だけだった。それでも懲りずに、アメリカ人はまた別の夢を膨らましているならしい。一説によると現在のアメリカ経済はリーマンショックの直前と同じ様相を呈しているらしい。
解説
カリホルニア在住の著者(町山)が、'00年代のいかれたアメリカをさんざんこき下ろしているが、日本にもそのおバカが伝染した。まさにアホのグローバリゼーションである。おバカが伝染するのは、おバカそのものではなく「金もうけ」の仕組みを真似る輩がいるからである。おバカはその結果なのである。最近の金融庁の年金2000万円問題は、政府自民党のマッチポンプだが、もともとの話は投資で老後の自助努力をせよという、ブッシュ時代の政策を模倣したものにすぎない(騒ぎが大きくなり選挙に不利とみた安倍総理は知らんふりしている)。年金を破産させたブッシュ大統領は当時、「オーナーシップソサエティー」政策を唱え、定年後は投資でもうけて自活せよと言ったそうだ。 投資信託なんてものは、情報のない素人が手をだせば失敗するにきまっている。なけなしの退職金をむしり取る合法的な金融詐欺みたいなものである。かく言う庵主がその犠牲者で、リーマンショックで大損をこいた。某信託銀行の勧誘員は資産状況をお客から聞き出して、その商品が失敗しても、飢え死にしないように、心やさしく投資額を調整してくれた。客が自分の会社の商品で破産して、自殺されると社会問題になり、その会社が弾劾されるからだ。このありがたい日本的心遣いのおかげで、庵主はホームレスにならずなんとか生活している。閑話休題。
こんなアホで間抜けなアメリカがどうして崩壊もせずに体面を保っているのか不思議な話だが、多様性の力と数%の輝く良心の人々が存在するからである。本書にも、アメリカの良心が数人でてくる。その一人が、ジョン・マケイン元上院議会委員 (1936-2018)である。マケインは共和党であったが、ブッシュ政権が進めた国民の盗聴、捕虜虐待、移民の締め付けなどの政策に敢然と反対した。また自分を捕らえ拷問したベトナムとの国交正常化を成し遂げた。マケインは、自分の葬儀にトランプ大統領をだささないようにと言い残したそうだ。さらに反体制映画監督のマイケル・ムーア、80歳を越えてもホワイトハウス記者として「何も罪もないイラクの人々に爆弾を落とすのは何故ですか」とブッシュに質問したヘレン・トーマス、記者クラブの晩餐会でブッシュを面前にほめ殺しスピーチをした、スティーブン・コルベアなど。こういった良識派は、中間層を背景に存在するのだが、アメリカでは中間層が没落しつつある。今日のアメリカは明日の日本である(昨日のアメリカは今日の日本というべきか)。
なお標題の「アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない」は、情報を自由に取得できるアメリカ人が意外と物を知らない事、それが政府の理不尽な政策の背景にもなっている事を皮肉っぽく表現している。この本の続編は「99%対1%ーアメリカ格差ウオーズ」2012年講談社」であるが、少し町田のトーンが落ちていた。
付記:チャールズチャールズ・ファーガソン 『強欲の帝国ーウォール街に乗っ取られたアメリカ』藤井清美訳 早川書房 (2014)はリーマンショック以前の腐敗したアメリカ金融業界の様子を仔細に報告した希有なドキュメントである。著者のファーガソンはこれをもとに「インサイド・ジョブ』を制作監督した。
他人に対する否定を程度の強さで分類すると次のようになる。{評論ー批判ー悪口ー誹謗ー罵詈ー唸声}
評論は客観的に物事や人の価値・善悪・優劣などを論じることである。これは人の事績を中心にしており、その人格や行為の価値判断にはほとんどふれることはない。批判も評論に似ているが、人の評価がかなり入ってくる。学会の発表後の質問で「もう少し観測値を増やすことが望ましい」などと言われることがある。これには、少ないデーターで結論を出す発表者の性急さや未熟さが、やんわりと非難されている。
悪口になると、対象とする人そのものの批判や否定がかなり大きな要素をしめてくる。ただ、その理由をある程度述べているので、表現の仕方によっては、センスやウイットがあるものにもなるし、後味の悪いものにもなる。話者の知性と表現力が試されるものだ。悪口は面とむかって相手に言うことよりも、共通の知り合いにいうことが多い。
そして、誹謗となるともう99%が相手の人格否定を目的にするもので、多くは虚偽を交えた文言の羅列に終止する。目的は、人や集団に対する中傷で、聞いているほうも引いてしまう。これをおおやけの媒体でやると名誉毀損で訴えられる可能性がある。次の罵詈は口汚いののしり。罵詈雑言と四字熟語で言う。
最後の唸声(ねんせい)とは、耳慣れない言葉だが要するに唸り声である。動物がストレスにさらされると、相手を威嚇するために唸り声をあげる。排外主義的なヘイトスピーチやインターネットの書き込みは、悪口といえば悪口であるが、知性やウイットのかけらもない。欲求不満のはけ口にすぎない。中国の若者は共産党の「愛国教育」により反日の唸り声をあげ、日本の若者はブラック労働のストレスで反中•反韓の唸り声をあげている。若者が唸る国はおおむね衰退する。
悪口を言う理由はいろいろあるが、多くは怨恨である。人にバカにされたり、侮辱されたりすると、人はだいたい忘れずに復讐してやろうと思う。あんなバカは相手にせず無視すればいいと、理性が心の中でつぶやくが、凡俗はなかなかそうはできない。第三者に悪口を言って代償することになる。悪口を昇華して批判に転化せよとのたまう人もいるが、たいていはエスカレートして誹謗にいたる。人はなかなか君子にはなれないものなのだ。

参考図書
和田秀樹氏『悪口を言う人は、なぜ、悪口を言うのか』 (2015) ワック株式会社
追記 (2020/08/13)
村松友視『悪口のすすめ』 日本経済新聞出版社 2012によると「悪口」には「愛」がふくまれていなければならないそうだ。
『妻昼寝トドに毛布をかけてやる』
なるほど。
島田市には御陣屋稲荷神社(悪口稲荷神社)がある、ここでは「愛するあなたへの悪口コンテスト」が毎年行われる。

中国文学者の高島俊男氏は博覧強記の人で、豊かな学識と文才を背景に多数の評論やエッセイーを著している。『本が好き、悪口言うのはもっと好き』(文春文庫 1998)はそれまでの評論や随筆を収集したものだ。ここに収められた作品の一つ「ネアカ李白とネクラ杜甫」(1995年第11回講談社エッセイ賞受賞)は何度読み返しても面白い。この本を最初から読むと、それほど悪口は書かれていない。国語辞典の不備(「ボウゼンたるおはなし」)、NHK囲碁番組のおかしい言葉づかい(「握りまして先番」)、漢字の不適使用(「わが私淑の師」)などは正当な批判が縷々展開されているが悪口ではない。本のタイトル「本が好き」はよいとしても、「悪口言うのはもっと好き」はおかしいのではないかと思いつつ、さらに読み進めると、最後のほうの随筆「つかまったら何より証拠」で超弩級の悪口にぶちあたった。いか紹介する。
話の舞台は国鉄時代の渋谷駅である。高島氏は切符の販売窓口で職員の態度に腹を立て、仕切りのプラスチックの窓をたたいてヒビを入れてしまう。彼はその場で鉄道公安官に取り押さえられて、駅構内の一室で取り調べられるはめになる。そして落語の「ぜんざい公社」に出てくるような尋問を何時間も受けて、調書をとられる。とられた調書の記載は「私は駅員の態度に腹を立て、日本国有鉄道の財産たる窓ロプラスチック板を拳で強打して損壊したのであります」とたったこれだけだったそうだ。
さらに話は続く。以下は本文からの抜粋。
『いや、自動販売機の横にこう書いてあり、向いの売店では……」と縷々説明しても、「だからつまりこういうことじゃないか」とそれ以上は書いてくれない。そのあと声を出して読み聞かせながら手を入れてゆく。これがまた一々欄外に何宇抹消とか何字追加とか書きこむので手間がかかる。そのころにはこちらは疲れ果てて、もう何でもいいや、とにかく早くこの挟い部屋から出してもらいたい、と完全に屈服してしまった。それが終ると彼はごく気軽な調子で「じゃあ渋谷警察に四五日泊ってもらおうか」とったので、飛びあがるほどびっくりした。「国有財産損壊は重いからな。学校はもちろんクビだ。前科がついたらつぎの勤め先をさがすのも容易じゃないだろう」そんなひどいことになるのかとしょげかえっていると、「どうだ、示談にしてやろうか」と言う。「どうするんですか」「金で解決するんだよ」「そうしてください。お願いします」と一も二もなく頭を下げた。「よし待ってろ」と茶色セーターの男は出て行った。しばらくしてもどって来て、「これだけでいいと言っている」と小さな紙片を見せた。誰がいいと言っているのかわからないが、それより金額に驚いた。私も遠くから数日の予定で出てきているからには多少の金は持っているが、とても足りない。そんなに持てないと言うと、誰かに借りられるだろうと言う。手帳を調べたらK君が一番近そうだ。電話を借りてかけたらK君は不在でお母さんが出た。茶色セーターの指示通り、「詳しいことはあとで話す、これだけの金を持って渋谷駅のどこそこへ来てほしい」と頼んだ。またもとの事務室にもどされて一人で待った。よほど経って茶色セーターがあらわれて、示談が成立したから帰ってよい、と言った。』
そんな馬鹿なと思える話である。高島氏が過失であれ故意であれ、駅でプラスチックの窓を破損すれば、取り調べを受けるのは当然であろうが、その場で示談などと言って、職員が現金を受け取るなどはあり得ない。そのような事をすれば、恐喝を含んだ国鉄職員の犯罪である。どうして国鉄あるいはその後身であるJR東海が、この文章の作者を名誉毀損で訴えなかったのか不思議だ。「あとがき」によると、これの初出は大修館書店の発行の「しいか」という雑誌で、1991年4月〜1994年3月にかけて掲載された『湖辺漫筆』の一部だそうだ。さらに書き出しには「もう二十年も前のことだが」とある。国鉄が民営化されたのは1987年のことで、初出の4-7年も前の事である。名誉毀損の告訴の時効(3年)をこえていたのかも知れない。あるいは、あまりにバカバカしい話なので無視したのか。
もっとも高島氏はよっぽど口惜しかったのか、最後で次のように述べている。
「国鉄が解体されて民営会社になった時は快哉を叫んだものだ。もっともあの悪辣な駅員や公安官どもは、新しいJRのどこかで、本性変らず同じように陰険な弱いものいじめをやっているのかもしれないが」
高島氏のさまざまな評論を読むと、その分野では最高の知性を備えた人物のようである。様々なテーマで、学者を含めたあまたの有象無象の無知蒙昧をバッタバッタと切り倒している。たとえば、外国語の翻訳書でまちがいを徹底的にこきおろした評論を読むと、翻訳者でなくても身がすくむ。ただ、たまに散見する高島氏の生活のエピソードを読むと、まるで未熟な幼児のようなところがあり、不思議な違和感をおぼえる。彼は、この事件の直後、所属する大学の法学部教授のところに相談にいき、さんざん馬鹿にされたそうだ。
参考図書
高島俊男 『漢字検定のアホらしさ』(お言葉ですが...別巻3 ) 連合出版 2010
高島俊男 『母から聞いたこと』(お言葉ですが...別巻5) 連合出版 2012
高島俊男 『兵站 入営』-これでいいのか本づくり(お言葉ですが...別巻6 ) 連合出版 2014
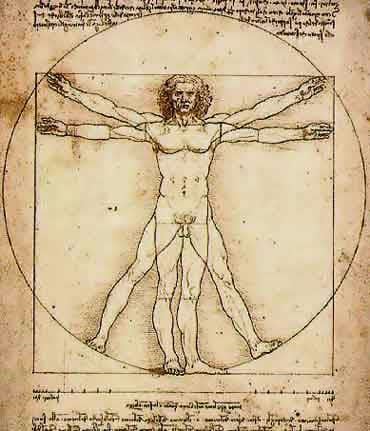
R. M. Dunbar (Liverpool大学)という学者の論文(Gossip in Evolutionary Perspective: Review of General Psychology 2004, Vol. 8, No. 2, 100–110)によると、霊長類における毛づくろいの替わりに、ヒトでは音声言語によるコミュニケーションが発達したという。そして初期の会話の内容の大部分はゴシップ、特にfree rider(ただ乗り野郎)に関する情報交換だったのではなかったかと議論している。
初期人類の会話情報の多くは、Dunbarの言うような他人のゴシップではなくて、おそらく食糧、外敵、危険に関するものであったろう。ゴシップが会話の主流になったのは、集団が定着して余裕が出来てからと思える。他者に関する情報交換は、個体同士の信頼関係を高め、政治的なグループの形成を促進したと思う。
現在でも統計によると、人がおしゃべりしている時間の65%はゴシップに費やされているらしい。学会の懇親会に出席しても、学術的な話題よりもゴシップ話が多いのは驚かされる。
『A先生は、苦節30年の研究成果を大学の紀要にやっとまとめたようですな』とかいう地味な話はまれで、『B先生は、どうも秘書とできているようで、この学会にも奥さんに内緒で二人で来てるらしいよ』とかいう話の方が多い。情けない事に、こっちの話題の方が圧倒的に面白い。
昔も今も、集団やグループ内での他人の情報は自己の行動や方針を決定するための重要な要素である。集団の中に礼儀や規範を無視する乱暴者が出現したとき、そんなのにうっかりつき合って、被害を被らないために情報は重要である。とんでもない奴とプロジェクトを組んで、ただ乗りされたり横取りされてはたまったものではない。
参考文献
小松正 『いじめは生存戦略だった!?』 秀和システム 2016
ユヴアル・ノア・ハラリ 「サピエンス全史」河出書房新社 2017
亀田達也 『モラルの起源ー実験社会科学からの問い』岩波新書 1652, 岩波書店 , 2017
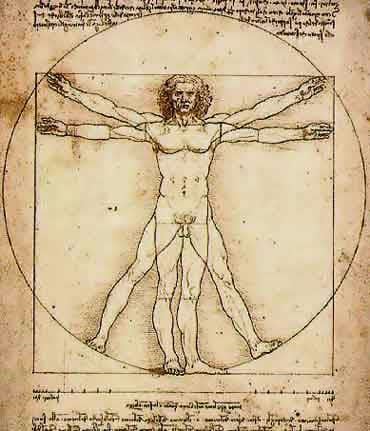
今ではどうか知らないが、日本の大学や研究機関で一時、『文理融合』という言葉がはやったことがある。地球環境関連のある国立の研究所でも、その発足当時、理系と文系のメンバーを混ぜて、プロジェクトチームを作らせた。初代研究所長の目論見は、それによって「いろいろの具材を混ぜてチャーハンのような味わいの成果を得る」というものであった。その目的が達成されたかどうかは評価が分かれるところであるが、ここでの文理融合は理系の人間にとってはとても忍耐力の要るものであったと記憶している。どこで忍耐が要求されるのかは、いろいろあったが一番必要なのは、共同の研究会や報告会においてである。ほとんどの文系の研究者の口頭発表は面白くない。まず内容が聞き手に理解させようという一切の努力がなされていない(ように思える)。もっとも、これはこちらの勉強不足で不明のいたすところかもしれないし、文系人にとっても理系の発表は不親切なものだろうと思い、これは我慢出来る。
しかしながら問題はその発表の形式である。ほとんどの人は原稿の棒読みで何の工夫もない。常々そのような感想を抱いていたが、米国の有名な進化生物学の権威であるスティーヴン・ジェイ・グールド(Stephen Jay Gould: 1941-2002)も、文系の発表に対してズバリ同様の悪口を述べているので紹介する。それは「梯子図と逆円錐図ー進化観を歪める図像 」(『消された科学史』渡辺、大木訳、みすず書房 1997)というエッセイで、少し長いが、以下その部分を引用する。
『たとえば、どんな分野の学者でも経歴を築くうえで重要な足がかりとなる、学会での口頭発表について考えてみよう。私にはとんでもなく皮肉なことに思えるのだが、科学と人文学では、その発表様式に二つの大きなちがいがある。世間の紋切型の常識によれば、科学者が話す内容は経験的なものではあるが、たいていは洗練された言葉づかいやコミュニケーションの巧みさに欠けるのに対し、脂が乗っている人文学者は、少なくとも「えもいわれぬ表現」で聴衆を驚嘆させるのだという。しかしながら、両者間における二つの大きなちがいは、言葉づかいやコミュニケーションの方法において科学者の直観力のほうが優れていることを示している。これを皮肉と言わずして何と言おう。まず第一に、人文学者が発表する際には、ほとんど例外なく書いた原稿を読む(そしてたいていの場合、お粗末にも顔を原稿に埋めんばかりの姿勢で一本調子で読むという、およそ口頭発表にふさわしからぬやり方をする)。科学者は、原稿を読むようなことはまずない。われわれは議論の順序や論理をとくと考え、概略を描いてメモを用意し、即興で話をする。こちらのまさに本物の口頭発表のほうが優れているのは自明であると私は思う。なによりも実際問題として、科学者の戦略のほうが、きちんとした準備にかかる時間が少なくてすむ(人文学者が用意する原稿の多くは、講演後に出版の予定があるわけでもなく、労力のむだである)。
第二に、たいていは、原稿をそのまま棒読みするよりは、即興のスピーチのほうが断然おもしろく、ついつい引き込まれてしまうものである。もちろん原稿を読み上げるにしても上手な人はこの問題をいくつかの簡単なルール(たとえば一文ずつ憶えて聴衆のほうを見ながら話すというような)で克服しているが、実際問題としてうまく読み上げられる人はめったにいない。しかも、下手な朗読がつのらせる退屈度は、即興の講演に不慣れなせいで生じる文法の乱れによる聞き苦しさよりもはるかに救いがたい。私がにらむところ、多くの人文学者は恐怖心から、かねて用意の原稿を読み上げるという戦略を採るのかもしれない。なにしろ何といっても文法的に正しいことが彼らにとっての至高善である。無意識のうちに動詞の活用をIつまちがえるくらいなら、終始単調で退屈で聴衆に理解すらされなくてもかまわないのだろう。その点、科学者はスピーチが文法的に正しいかどうかで同僚から評価されることはまずないため、多少のミスは覚悟のうえで、より良いコミュニケーションの方法を選ぶ。
そして第三に、これが最も重要な点なのだが、同じ英語とはいえ、書き言葉と話し言葉はまったくの別物である。人文学者たるもの、何よりもこのことを心得るべきである。講演用に用意された原稿は、たいていそのままでは活字にはならない(マーティン・ルーサー・キング牧師の「私には夢がある」という例の演説は二〇世紀最高の演説だが、リズミカルな繰り返しを基調とした口誦向きの詩であるため、文章として読むにはまるで適さない)。両者のちがいは多々ある。一つだけ挙げるなら、口頭での話は周到に計算された循環構造をもっていなければならない。発表は一方向に進むだけで、聴衆には前の部分に戻って参照することができないからである。それに対して、書かれた文章はもっと直線的で重複はないほうがいい。読者は途中で前のページにもどって読み返せるからである。このような顕著なちがいは、明らかに視覚的な対象について人文学者が話をするときにも見受けられる。(中略)視覚的な像はわれわれの生活の中心をなしている。生物学用語を使うなら、霊長類は哺乳類のなかで典型的な視覚の動物である(人間の脳が創造した「ホムンクルス」の標準的な図像を一目見れば、大脳皮質が視覚系にいかに奉仕しているかがわかるだろう)。社会的な問題におけるわれわれの判断の多く、とくに感情的なものは像によって左右される。自由の女神像、アメリカ独立を描いたウィリアムズの絵画「一七七六年の精神」、「スラバキ山頂の国旗掲揚」などがなかったとしたら、愛国心は何を拠り所にすればいいだろう。あるいは地下鉄の換気口の格子上に立つマリリン・モンローぬきで現代のアメリカ文化を理解できるだろうか(以上)。
グールドは、このエッセイにおいて文系の進歩のないプレゼンを主題にしたわけではなく、「規範的な図像」(例えばサルが人類に進化する様子など)がどれだけ人々の概念を間違って規定しているかを述べたかったのである。その頭出しに、テーマに関係ない文系の退屈な発表について3ページにもわたって悪口を展開している。日頃、よほど気になっていたのであろう。グールドは文系の講演内容の質については、遠慮して述べていないが、庵主は思うに、言語という「空」を糸巻きの芯にして、それに言葉の糸をグルグルと巻き付けているような話が多い。難しい用語がつぎつぎ続くので、立派な事を述べているように聞こえるが、本人も分かっているのだろうかと思うことがしばしばある。大学における「文系学部廃止」の暴論がでるのには、このような背景があるのではないか。
追記(2019/12/20)
中村輝太郎 『英語口頭発表のすべて』丸善株式 1982でも同じ議論がされている。「読む講演 」でも要点を記したメモ程度にしておくのがいいそうだ。
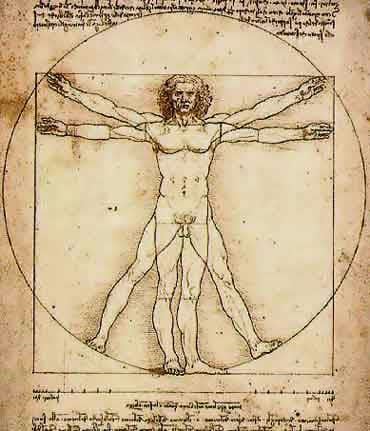
池田清彦氏(1947年生)はウィキペディア記事 (2019/04/25)によると「 日本の評論家、生物学者。早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授。東京都立大学理学博士」となっているが、生物学者の間では構造主義生物学の論客の一人として知られている。構造主義生物学とは、今は流行らない観念論の一種で、エンテレキーを前提にした妄説である。すなわち、生物の「かたち」を支配しているものは、物理学的・幾何学的な形態形成場であり、それは生物であるか無生物であるかを問わず、普遍的なジェネリックな「生成的空間」によるものであるとする。物質世界でも生物世界にも、目に見えないある構造が元々あって、森羅万象はそれに従って存在が規定されると主張する。ジグソーパズルにたとえていうと、個々のピースが進化の過程でランダムにできて、折り合いをつけて生物世界が出来上がったのではなく、もともと台(世界)にはめ込み型のようなパターンが存在し、生物はそれに合わせて出来上がっているという。誰がそんなはめ込みパターンを作ったのかという話になると、もちろん誰にも分からんので生気論にならざるを得ない。この学説の人達はモーリス・エッシャーの絵の反転画像にだまされているようなものだ。日本では柴谷篤弘(1920- 2011)がこの説のオピニオンリーダーであった。
池田氏はヒメギフチョウやヒオドシチョウの個体群生態学を本職としていたようだが、単著や共著の多くの著書がある。その中の池田氏、養老孟司、奥本大三郎との鼎談をまとめた『三人寄れば虫の知恵』(新潮社 1996)はまことに愉快な昆虫談義で、庵主の本箱に並んでいる。その後書きで南伸坊さんが書いているように、三人とも虫と虫好きの人の話を、時に脱線し冗談とユーモアを交えて談笑しており読んでいて楽しい。
この池田氏の著作に少し古いが、幾つかのエッセイを集めた『科学は錯覚である』(洋泉社 1996)がある。最初は宝島社から出版 され、後に洋泉社で新版が出されたようである。後書きに「この本はネオダーウニズムや分岐分類学の悪口がかれている」としている。エッセイ集なので様々なテーマが混ざっているが、それなりに面白い問題提議があって、批判的に読むには良い本である。ところが、途中の「おまけ」という部分でK.T(池田の本では実名)というエッセイストの著書に関してぶっ飛びの悪口が展開されている。その部分を幾つか抜粋する。Tはドーキンスの利己的遺伝子の説を俗流に解釈して、いくつか本を出している女性作家である。
「Tの著作を題しか知らずに論評するのもあんまりと思い、その著書を読んでみた。私は驚嘆し、Tをドーキンスの亜流だとばかり信じ込んでいた自分の不明を恥じた。Tの略歴には、京都大学理学部卒業後、同大学院に進み、博士課程を修了と書いてある。京大の大学院の博士課程という所は、論理的な思考能力が全く欠如していても修了することができるのだという事実に、私はいたく感動し、しばらく天を仰いで動けなかった」
「ここに(Tの複数の著書に)見られるのは自分の政治的な意見を、遺伝子の利己性仮説に論証抜きで妥当しようとするヒステリックな意志と妄想だけであると言ってよい。もしかしたら、Tのこの本は、精神病理学者が扱うべき1症例として読むのが正しいかも知れない」
「Tの肩書きは、動物行動学者ということであるが、私にはどうみてもただのアンポンタンとしか思われない」
今までおとなしく酒を飲みながら気持ちの良い会話をしていた紳士が、急に豹変し目が三角になって、「お前はなんだよ」と言って、相手にからみはじめたような雰囲気である。悪口の要件にはまず品がなければならぬ。あるいは少なくとも品を装ったものでなければならない。あまりに露骨な悪口は、聞いている方が白けてしまう。
最後に池田氏はこの章を次のように締めくくっている。「それにしても、Tに完全無欠のスーパースターと言われたドーキンスや、百年先を読んでいたと褒められたダーウィンはいい面の皮という他はない。ダーウィンは死んでしまたので口をきけぬが、ドーキンスが日本語に練達であれば、オレをほめ殺すのはやめてくれ位の事は言うに違いないと思われる。そこで私の希望としては、Tに最大級の賛辞でほめ殺されているもう一人の人物、Tの師であるT. H(これも実名で出ている。現在は物故の京大名誉教授)のT評を是非聞きたいものである。まさかHもTと同じ穴の狢という訳ではないだろうね」と。敵は本能寺にありという事のようであった。