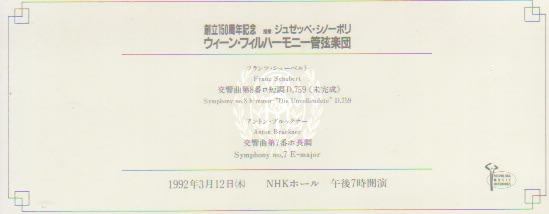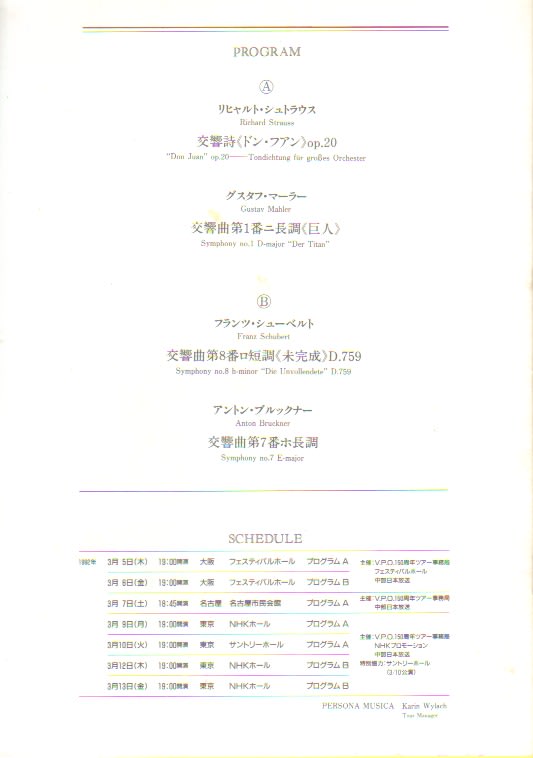『この国ではベートーヴェンの《第九》を「忠臣蔵」と並ぶ歳末行事に仕立てた。それを嘲う人もいるが、欧米、特にヨーロッパの人々にとっても、古来《第九》はやはり思い入れの深い別格の音楽であった。バイロイト祝祭劇場定礎式、ベルリンの壁崩壊時など、歴史の節目にはよくこの曲が演奏された。こめられた感動が〈音〉になって迸るとき、作曲者・演奏者・聴き手を貫く魂の共鳴が生まれる。音楽だけが持つ異常な力である。
フルトヴェングラー《バイロイトの第九》は、戦禍で中断していたバイロイト音楽祭の復活記念コンサート(1951年7月29日)のライヴである。平和到来の喜びの背後には、ナチズムとワーグナー思想(反ユダヤ主義)の関わり、フルトヴェングラー自身のナチ協力疑惑(裁判の結果無罪)など、複雑にして微妙な問題が潜んでいた。音楽が再現芸術である以上、「空前」であっても「絶後」の名演はありえないはずであろうが、背景にあるこうした事情を考えてみると、この演奏から得られる以上の感動がこの地球上で再現される可能性は、限りなくゼロに近い。
第一楽章の深沈たるテンポ、第三楽章の諦念を湛えた透明感、終楽章にみられる狂瀾怒涛の自己投入―ベートーヴェンの音楽を「思想」としてとらえ、無限の共感を強靭な構想力をもって演奏し、生きることの苦しさと歓びを極限まで歌いあげた―崇高な魂の記録がここにある。ベートーヴェンは生涯を通じて理想を追い続け、人間存在そのものをテーマに音楽を書いた。”そのこと”が、フルトヴェングラーの演奏を聴けば心の底から納得できると思う。』
文春新書069・クラシックCDの名盤/宇野功芳・中野雄・福島章恭著/文芸春秋刊より、
中野雄氏のコメント。
何しろ54年前の録音なので、録音だけを比べれば今よりも貧弱なのですが、それでもOTAKEN盤を聴くと、この演奏記録がそんな昔のものだとは全く分からないほど、豊かな音ですね。それに比べて今の演奏にはここに記録されている感動は絶対にありませんね。ただ、私も5年間程第九の合唱体験があり、師走のNHKホールに立って実際にこの第九を歌いましたが、それは大変な感動がありました。その体験のおかげで終楽章の合唱が全て聞き分けられるのですが、実際、良いものです。ソプラノのパートは大変なんですよね~。
さて、《第九》の決定的演奏といわれているのが《バイロイトの第九(1951年盤)》であり、その決定的CDがこのOTAKEN盤といえるでしょう。前回記事で紹介したCDはフルトヴェングラーが指揮台へ歩く足音が入っているもので、しばらく決定盤といわれていたものです。私もバイロイトの第九のCDを4枚持っていたのですが、つい先日、OTAKEN盤を入手して聴いたところ、軍配がこちらに上がった次第です。クラシック音楽を聴いたことの無い人は是非一度聴いてみて! 凄いですよ~♪