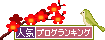11月19日(火)妻と二人で調布市の深大寺へ行って来ました。
新宿から京王線特急に乗ると僅か15分で調布駅へ到着です。
駅から電通大学キャンパスの横をまっすぐ北へ歩いて行き、武蔵境通りの深大寺入口交差点を右折すると「深大寺通り」になります。

ここから参道までは深大寺そばの名店がずらりと並んでいます。
写真は「湧水」(ゆうすい)で深大寺で1,2を争う人気蕎麦店です。
平日の10時半過ぎにも拘らず、御覧の通りの行列です。

「深大寺水車館」です。
現在、水車館の敷地となっているところには、明治時代後半から水車小屋がありました。
周辺には雑木林が茂り、豊富な湧き水を水源とする逆川(さかさがわ)が流れ、水車の回る音が響いていました。
逆川では鰻がとれ、沢がにが住み、近くの田んぼではホタルが飛びかっていました。
調布で最後まで残っていたこの水車も、電動モーターの普及などによって、昭和30年頃には使われなくなりました。
市内で最後まで残っていた水車を復活させたいという地元の方々の運動により、平成4年7月1日に、オープンしました。

いよいよ参道の入口に到着。
門前の両側には蕎麦屋、土産物店などが並んでいます。
右手に「鈴や」と「門前」、左手に「鬼太郎茶屋」(きたろうちゃや)と「元祖嶋田家」。

「鬼太郎茶屋」は「ゲゲゲの鬼太郎」をモチーフにしたユニークなお店です。
目玉おやじの栗ぜんざい、ぬり壁のみそおでんなど、妖怪にちなんだ甘味や軽食が味わえるそうです。

「元祖嶋田家」文久年間(1861~1864)創業の深大寺そばの元祖。
そばをさらす水は「湧水」とこだわり、コシの強い最高のそばに仕上げているとのこと。
粉は熱と空気を嫌うので、機械は使わずに昔ながらの石臼でひいた粉を使用しているそうです。

「山門」は参道より一段高い寺の敷地の入口に立つ正門で、正面には「浮岳山」の山号額を掲げています。
慶応元年(1865)の火災の際にも常香楼とともに被災をまぬがれた建物で、現在、山内で一番古い建物です。
屋根裏にあった棟札には、「元禄8年(1695)に1,000人の寄進者・人足によって、このあたりの地形と山門の普請が行われた。」と記されています。

文政12年(1829)に建てられた旧鐘楼は、今の大師堂裏の高台にありましたが、幕末の大火で消失し、その後、明治3年(1870)に、山門を入った右手に位置を移して再建されたのが今の鐘楼です。
重要文化財に指定された古い梵鐘は平成になって、ひびが見つかり、平成13年に新しく鋳造され釣り替えられました。
今も、毎朝・昼・夕の3回撞かれています。

関東有数の古刹である深大寺は幕末の慶応元年(1865)の大火で主要堂舎を焼失し、現在の本堂は大正7年(1918)に再建されました。
本尊は宝冠阿弥陀如来を奉安しており、頭部に宝冠を戴くもので、主に天台密教に伝わる金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)に描かれている特徴的なお姿で、大変貴重なお像です。

深大寺のご祈願本尊である「元三大師堂」(がんざんだいしどう)は平安時代に活躍した比叡山の高僧、元三大師を祀るお堂です。
元(1)月3日に縁が深いことから、元三大師の通称で親しまれており、大師には悪魔調伏(じょうぶく)の力があると信じられていたので「厄除け大師」として多くの信仰を集めています。
元三大師像は座像にして高さ2mに近い大像ですが、秘仏となっており平時に拝観することはできません。
25年に一度、御開帳の行事が行なわれ一般にも公開されるそうです。

「開山堂参拝道」という道標があったので坂道を登って行きました。

「開山堂」(かいざんどう)は昭和58年の開創1250年大法会記念事業として新築された奈良時代様式の堂宇です。
本尊に薬師如来、脇侍に弥勒菩薩、千手観音を安置し、深大寺を開いた満功上人(まんくうしょうにん)、宗派を天台宗に改めた惠亮和尚の尊像を奉安しています。

深大寺境内の散策を一通り終えたので、400年余りの歴史を持つ「深大寺そば」を食べることにしました。
山門の近くには清水比庵(しみずひあん)の歌碑がありました。
門前の 蕎麦はうましと 誰もいふ
この環境の みほとけありがたや
江戸時代、土地が米の生産に向かなかったため小作人が蕎麦を作って、蕎麦粉を深大寺に献上しました。
それを寺側が蕎麦として打ち、来客をもてなしたのが始まりといわれます。
深大寺の総本山である上野寛永寺の門主第五世公弁法親王はこの蕎麦を非常に気に入っており、「献上蕎麦」でもありました。
また、徳川第三代将軍徳川家光は、鷹狩りの際に深大寺に立ち寄って蕎麦を食べ、褒めたとされています。
今でも門前の参道には20軒あまりの蕎麦屋が並び、大変な賑わいを見せています。

深大寺に来たのは初めてなので、どの店が美味しいのかという知識もありません。
そこで参道に来ると最初に目に入った「 鈴や」という店に入りました。
店内からは有名な「鬼太郎茶屋」や「元祖嶋田家」など参道の賑わいを眺めながら食べることが出来そうです。

妻は「もりそば」(700円) 私は「天ぷらそば」(1000円)を食べました。
細い麺で、なめらかな喉ごしの美味しいそばでした。
妻は蒸したてのそば饅頭も土産に買って帰りました。

最後に開山堂の裏手の北門から都立神代植物公園を通って、「植物会館」横のカフェでコーヒーを飲んだ後、公園正門前から調布駅北口行きのバスに乗り、帰路に就きました。
久しぶりの楽しい東京散歩でした。
ランキングに参加中です。クリックして応援お願いします。
↓↓↓