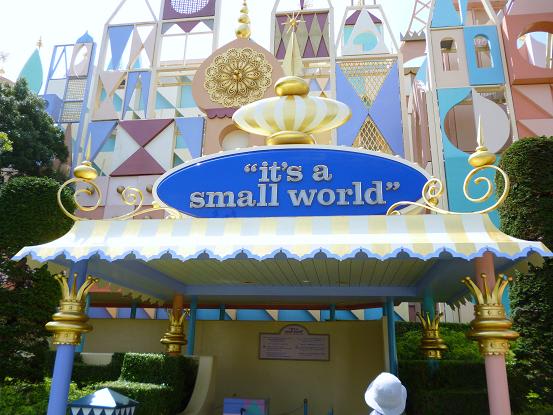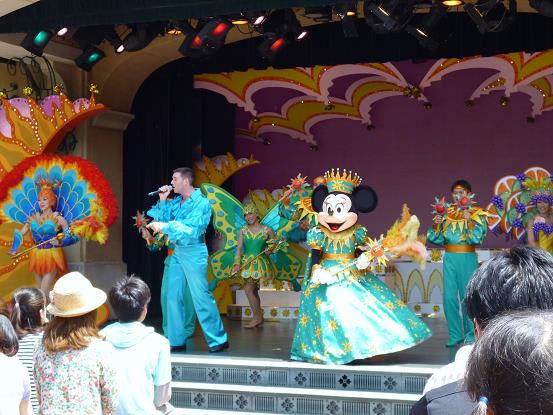4月9日(月)妻と二人で鎌倉の極楽寺周辺を散策した後、極楽寺駅から再び江ノ島電鉄に乗り江ノ島へやって来ました。

春の心地良い潮風に吹かれながら「江ノ島弁天橋」を歩いていきます。
「江ノ島弁天橋」は片瀬海岸と江の島を繋ぐ橋で、長さは389m。
東京オリンピック開催にともない、自動車専用道路の「江の島大橋」が昭和37年に並行して開通したのを境に、それまで取っていた渡り賃は廃止されたそうです。

江ノ島に近づいてきました。
江ノ島温泉アイランドスパ(えのすぱ)の建物が異国情緒を誘います。

江の島の玄関口「青銅の鳥居」です。
この鳥居は文政4年(1821年)に建てられたものだそうです。

「青銅の鳥居」をくぐって参道を歩いていきます。
干物や海苔、相模湾の海の幸はもちろん、夫婦饅頭や羊羹、貝細工の土産物店をはじめ、老舗旅館や懐かしい射的場もあります。

老舗旅館の「岩本楼本館」です。
800年というときの中で、寺院から旅館として移り変わってきた岩本桜。
葉山御用邸が完成するまでは、宮内庁御用達として、皇族の方々も利用され、古くは、将軍や大名も宿泊し、福沢諭吉や伊藤博文、山下清、早川雪州といった多くの名士も訪れたそうです。

テレビ、ラジオ、雑誌等でおなじみの、イイダコをそのままプレスした100%タコだけの丸焼きタコせんべいの店「あさひ本店」です。
鉄板でタコを焼きつぶす音が耳を引く豪快なせんべいだそうです。
平日でもご覧の通りの行列です。

参道奥の鳥居をくぐり、急な階段を上って江島神社にお参りします。
階段がきつい人にはエスカー(エスカレーター)が有料で利用できますが、デパートでも階段しか利用しない妻の前では、心筋梗塞も覚悟のうえで上るしかありません。(笑)

竜宮城を模して造られたもので「瑞心門(ずいしんもん)」と呼ばれています。
清々しい心で参拝していただけるようにと命名されたそうです。
門の両脇には唐獅子画が飾られています。

江島神社は島内にある辺津宮・中津宮・奥津宮の3宮の総称で、「辺津宮(へつみや)」はその本社で源実朝が建永元年(1206)に創建しました。
海の守護神・田寸津比賣命(タギツヒメノミコト)が祀られています。
写真のように「茅の輪(ちのわ)」があり、ここをくぐってから参拝します。
具体的な方法ですが、この輪を左回り、右回り、左回りの順で「∞」の字を描くように3回くぐり抜けて参拝するそうです。

次に行ったのが「中津宮」です。
「中津宮」は、3女神のうち市寸島比賣命(イチキシマヒメノミコト)をお祀りしており、創建は仁壽3年(853年)であり、現在の朱色鮮明な社殿は、平成8年に大改修されたものです。
境内には、江戸時代に歌舞伎関係者により奉納された石灯籠や梅・桜などがあります。
当社の弁財天は日本三大弁財の1つで、七福神の弁財天として、また芸能を司る妙音天女としても崇敬され、江戸時代は庶民、歌舞伎役者、武士と幅広い階層から信仰を集め、大変賑わったそうです。

江ノ島サムエル・コッキング苑や展望灯台の横の遊歩道を行くと「奥津宮」に到着です。
ここは多紀理比賣命(タギリヒメノミコト)をお祀りしています。
多紀理比賣命は、三人姉妹の一番上の姉神で、安らかに海を守る神様といわれています。
養和二年(1182年)に、源頼朝により奉納された石鳥居や、江戸の絵師・酒井抱一が拝殿天井に描いた、どこから見てもこちらを睨んでいるように見える「八方睨みの亀」が有名です。

「奥津宮」の境内から伸びる山道に少し入ると、「龍恋の鐘(りゅうれんのかね)」という名所があるようなので、ミーハーな二人は寄り道してみることにしました。
相模湾を望む「恋人の丘」と言われる高台にありました。
その昔、海にすむ五頭を持つ邪悪な龍が、島に現れた天女に恋をし、改心の末に結ばれるという島の伝説(天女と五頭龍)があり、ここで愛する人と一緒に鐘を鳴らすと幸せになれると言われています。
しかし、妻はなぜか一人で鐘を鳴らしていました。
特に深い意味はないのでしょうが・・・(笑)

「江ノ島岩屋」や「稚児ヶ淵」なども見たかったのですが、時間もなくなってきたので、もと来た道を帰ります。
途中、「中津宮」付近からヨットハーバーや灯台を見下ろしたところです。
その向こうに鎌倉の海が広がります。
まさに絶景です。

時間が1時過ぎになっていたので昼食を食べることにしました。
江ノ島駅から歩いてくる途中に目をつけていた「紀伊国屋お食事処」へ入り「海鮮丼」を注文しました。
「この海鮮丼には15種の魚貝類が入っているんですよ」と綺麗な仲居さんが教えてくれました。
味は絶品で味噌汁と生姜とドリンクバーが付いて1500円ですから大いに満足でした。
あまりに美味しそうなので食べることに夢中になり海鮮丼の写真を撮るのを忘れてしまいました。(笑)
そういうことで、この写真だけはインターネットから拝借したものですので、ごめんなさい、悪しからず。
実物もこの写真のとおりで間違いないです。