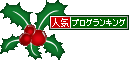10月1日(日)妻と二人で川越に行き、「旧山崎家別邸」を見てきました。
「埼玉モダンたてもの散歩」で川越市には2014年5月19日に行ったのですが、この建物だけは保存修復工事の為に唯一見ることが出来なかったのです。
それが2016年4月から一般公開されていたと聞いたので遅ればせながら見学した次第です。
信州中野出身の初代・山崎嘉七が1783年に川越に創業した菓子屋が『亀屋』ですが、「四代目山崎嘉七」は1867年に川越藩の御用商人となり明治期に「第八十五銀行」と「川越貯蓄銀行」の2つの頭取を兼ねる豪商となり、当時の川越経済界を主導する存在となりました。
そして旧山崎家別邸は、その跡を継いだ「五代目山崎嘉七」の隠居所として大正14年に建てられました。
設計は建物から庭園まで埼玉りそな銀行川越支店や旧山吉デパートを設計した保岡勝也によるものです。

主屋は、木造モルタル仕上げの洋風屋根葺きの洋館で、その奥には数寄屋造りの和室等と融合している和洋折衷の住宅です。
これは、この建物が隠居所であると共に、皇族方をお迎えする目的で計画されたことによります。
洋館の正面玄関からは入ることができず、屋内には和館の内玄関(写真左奥)から入館します。

屋内に入る前に東側から回って庭を眺めると「茶室」がありました。
茶室は京都の仁和寺の遼廓亭を模したと言われています。

茶室付近から洋館を眺めたところです。

内玄関から愈々屋内へ入りました。
階段の踊り場に据え付けられたステンドグラスは、小川三知の「泰山木とブルージュ」と云う作品で、カラフルな鳥が描かれています。

応接室の窓にもステンドグラスが・・・・これは別府七郎と言う人の作品です。
壁紙やカーテンは当時のままのものだそうです。

ダイニングルームです。
この邸宅は山崎家の社会的地位も踏まえ、プライベートな接待所としての役割も兼ねて建設されたようです。
比較的小さな邸宅ですが、軍事演習に参加した皇族の宿泊所として七回に渡って使われているとのことです。

和室に移ると数寄屋造りの素敵な客室があります。
それほど広くはありませんが、凝った造りの床の間と床脇がきらびやかでいながら、しっとり落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

この客間には畳敷きの広縁があり、座布団が敷かれています。
その座布団に座って眺めた和風庭園です。
当時の庭に対する新しい考え方である家族本位の実用性と、鑑賞を考慮した設計です。
特に芝生や児童遊技場、温室、花壇など、この時代の典型的な要素が見られます。

茶室が見えます。
庭園は枯山水と茶庭からなる庭園で、建築と相まって和風庭園の事例として国登録記念物名勝地となりました。
なだらかな高低差のある庭園が広がり、石灯籠や手水鉢、畳石などがアクセントになり、木立の先の茶室が風情を添えています。

8畳ある居間は最も使用された部屋で、扉付きの仏壇があります。

居間のアーチ型の壁の向こうは和室のベランダです。
和洋折衷の創りで、サンルームの役目をします。
普段は窓を開け放ってベランダとして使用していたそうです。

ベランダの隣は児童室です。
遊びに来る孫のための部屋だそうです。

建物から出て、客人を迎える洋室の玄関前を見ました。
1階は吹付モルタル塗り、2階は細い横目地の磨き壁となっています。
袖壁には鮮やかなステンドグラスが見えます。
玄関の正面がプラットホームのようになっているのは人力車をつけるためだそうです。

階段踊り場から見た小川三知の「泰山木とブルージュ」を玄関前から見た写真です。

同じく蔵入口と階段の間にある水辺の植物の意匠のステンドグラスを玄関前から見た写真です。

右手に真っすぐに伸びた松の木がありますが、これが「お手植えの松」です。
旧朝鮮王族だった王垠(りおうぎん)殿下が昭和4年に植えたものだそうです。
以上で旧山崎家別邸の見学を終わります。
以前は期間限定での公開で、建物の中にも入れませんでしたが、今は建物の2階を除いてすべて見学できますので、ぜひ皆さんもお出掛けください。
ランキングに参加中です。クリックして応援お願いします。
↓↓↓