
11月15日(土)妻と二人で愛車プリウスに乗って、群馬県桐生市まで行ってきました。
最初は「JR東日本・駅からハイキング」のコースを歩くつもりでしたが、本町通りの「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」を見て歩くほうが面白そうなので、群馬大学工学部までの本町通りを往復しました。
桐生駅前から末広通りを歩き、本町五丁目の交差点を左折して本町通りに入るとすぐ左手に見えてきたのが「金善(かなぜん)ビル」です。
「金善ビル」は群馬県内の鉄筋コンクリート建造物では最古級であり、平成18年に、国の登録有形文化財となっています。
ビルの名称は織物業を営んだ金居善太郎の屋号に由来し、金善ビルは金居善太郎の長男である二代目の金居常八郎によって、大正10年頃に建築されたそうです。

「金善ビル」の横の小路を入ると「糸屋通り」という本町通りの裏通りなのですが、ここに「芭蕉」という正真正銘の古民家レストランがあります。
昭和12年にビルマ大使館の調理人として腕を磨いた先代の小池魚心さんが開いた異国料理店です。
多くの文人墨客も押し寄せ、シャンソン歌手の石井好子やイベット・ジロー、版画家の棟方志功も訪れたそうです。

再び本町通りに戻ると鰻の香ばしい匂いがしてきました。
「蒲焼 泉新(いずしん)」です。
桐生で185年続く(創業天保元年1829年)老舗鰻店。
何と今の店主で六代目という歴史のあるお店です。
初代は越後出身で、江戸後期に故郷を出て、横浜で『うなぎ屋』をしていたところ、桐生の生糸を扱う関東三大富豪の一人、九代目・佐羽清右衛門が、そのうなぎ屋の味に感動し、是非桐生でと懇願され、天保元年に桐生で泉屋新蔵が開業されたのだそうです。

さあこれから「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」に入ります。
本町二丁目の南端に位置する「有鄰館(ゆうりんかん)」と「矢野本店店舗及び店蔵」からです。
二代目矢野久左衛門が寛永2年(1749)現在地に店舗を構えて以来、桐生の商業に大きく寄与してきた土蔵等建物群です。
酒・味噌・醤油を醸造し、保管するために使用されていた江戸時代から昭和時代にかけての11棟の蔵群が、舞台や展示、演劇、コンサートなど様々な用途に使用されています。
多くの人が訪れ、プロアマを問わず、それぞれの目的によって自ら会場を作り上げて行く独特の活用方法で「文化を発信する場」として、また、周辺に残る歴史的建造物や近代化遺産などと一体となった街並み保存の拠点にもなっています。

「花のにしはら」(旧書上商店)
母屋で無頼派作家・坂口安吾が晩年(昭和27年~30年)を過ごしたという明治期の桐生を代表する買継商「書上文左衛門」の商店店舗です。
隣に「坂口安吾往還の碑」が立っています。

「旧平田商店」 - 国の登録有形文化財
大正3年建造で、左半分が倉庫としての蔵であるのに対して右半分は店舗としての蔵「店蔵」 と言われています。
しっくい仕上げの壁と重厚な扉が美しさをいっそう引き立てています。

「中村弥市商店」は 大正11年建造で 国の登録有形文化財です。
本町通りの東側で、幅約12メートル、奥行き約82メートルの敷地北寄りに、表から店、文庫蔵(新座敷)、奥座敷が直列し、南辺に浴場、石蔵が建ち並んでいます。
この短冊状の屋敷地は、桐生新町町立て当時の規模をそのまま伝えているそうです。

「無鄰館」は旧北川織物工場の現在の名称で国の登録有形文化財です。
現存する鋸屋根工場は、大正5年に建築され、昭和35年頃まで操業していました。
現在は、建築設計事務所のほか彫刻家、画家たちの創作工房として利用されています。

「森合資会社」は大正3年に金融業の建物として建てられた木造平屋建て、瓦葺の建物で、国の登録有形文化財です。
当時の洋風建築の要素を取り入れつつ、玄関庇や窓の小庇は格式の高い和風にするなど和様混在の擬洋風建築の形式です。
隣接する土蔵は2階建て、切妻、瓦葺きで事務所より早い明治時代初期の建物で事務所との対比が印象に残ります。

事務所北側にある「森家住宅石蔵(穀物蔵)」です。
これも登録有形文化財です。
現在は「天然染色(そめいろ)研究所」として使われています。
ざくろ、どんぐり、びわ、バラ、ローズマリーなどを使って草木染めができます。
織り機もあり、機織り体験も可能だそうです。

本町一丁目バス停の前にある石造りの可愛らしいお店が「和ざかな工房」です。
旧早政織物の工場事務所棟に出来たガラスアクセサリー・とんぼ玉のお店です。

「和ざかな工房」の隣が、銭湯「一の湯」。
「一の湯」は当初隣接する織物工場で働く従業員のための浴場として建築され、近隣住民に利用されていたそうです。
現在も市内に数少ない銭湯として営業しています。

本町通りの次の信号を右に入ると、イギリス積みのレンガ造りのノコギリ屋根工場の建物が見えてきました。
「ベーカリーカフェ レンガ」と言い、大正8年に建てられ、国の登録有形文化財として残された旧金谷レース工業㈱の工場がベーカリーカフェとして生まれ変わったものです。
事務所棟は、昭和6年に建築され、木造二階建てスクラッチタイル張りで、窓や細部に至る意匠に昭和初期の洋風建築の特徴が見られます。

もう一度本町通りに戻ると、「桐生天満宮」が左手に見えてきました。
現在の桐生市街は、「桐生天満宮」を基点として成立しており、天満宮鳥居前が本町一丁目となっています。
桐生市は多くの高校が存在するため、受験シーズンには多くの参拝者が訪れるそうです。
この日は七五三の参拝客で賑わっていました。

本町通りの最後は「群馬大学工学部の同窓記念会館」です。
大正5年創立の桐生高等染織学校の本館で玄関の一部と講堂が同窓記念会館として残っています。
建物は木造二階建瓦葺、ハンマービームと呼ばれる独特の屋根構造を持ち、内外装から金具・調度品に至るまで建築当初の姿を残しており、教会堂のように厳粛でありながら華やいだ空間を創り出しています。
NHk連続テレビ小説「花子とアン」で花子が通う女学校「修和女学校」での撮影ロケ地は、この同窓記念会館で撮影されました。
他にも、平成18年に放映されたNHK連続テレビ小説「純情きらり」や14年に公開された映画「突入せよ!あさま山荘事件」でもロケ地となったそうです。

「桐生新町重要伝統的建造物群保存地区」を見終えて、末広通りに戻り、「デニーズ」で昼食を食べたので「さあ帰ろうか」と言うことになったとき、”ミーハー好き”の妻が「もうひとつだけ・・西桐生駅を見たい・・・」と言うので付き合いました。
「西桐生駅」は上毛鉄道上毛線の駅です。
開業当時からの駅舎で、マンサード屋根の洋風建築の建物になっています。
ただし宿直室は和風の畳部屋、隣の台所は三和土の土間であり全体としては和洋折衷の建物になっているので「織物の町桐生市内に開設当時から残る保存が望まれる駅舎で機織りが体験できる駅」という理由で、関東の駅百選の第2回選定対象となったそうです。
松本清張ドラマ『球形の荒野』や森村誠一原作の連続ドラマ『人間の証明』、更に映画『少年H』や『君に届け』それに『人のセックスを笑うな』等等の・・・ミーハーには堪らないロケ地なのでした。
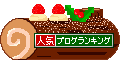




















そういえば昔、桐生高校も野球が強かったですよね。
甲子園に出た桐生高校を私もまだ幼かったから「トウセイ高校」と呼んでいましたよ。