ある私立大学の児童教育シンポジウムに出ていたら、教師をめざす大学生から教育の鉄人と呼ばれるパネラーの現役小学校教師たちに「教材をつくるためには日頃どんなことをすればいいのか」という質問があった。パネラーの多くが、テレビでは「エンタの神様」、雑誌では「少年ジャンプ」を推薦していた。こどもにものを教えるにはこどもと文化を共有する必要があるのだそうだ。教材開発のヒントを得ることもあるとか。そのためにトレンディなテレビ番組を見て、はやりのマンガを読むらしい。話題が合うとこどもとの距離がぐっと縮まるとの意見。話題のテレビゲームもしなくっちゃいけないという話だ。しかし、これはビジネスマンでもある意味では似ているともいえる。下着開発担当者なら、男性でも女性の下着売り場にしょっちゅう通うだろう。便器の開発者ならお尻や肛門に日頃からただならぬ関心を示すかもしれない。その世界に浸って、問題意識を常に持っていることが、教育でもビジネスでも重要なのだ。
最新の画像[もっと見る]
-
 大学スポーツコンソーシアムKANSAI『大学スポーツの新展開』晃洋書房
6年前
大学スポーツコンソーシアムKANSAI『大学スポーツの新展開』晃洋書房
6年前
-
 ハラリ、ギャロウェイ、ガブリエル他『欲望の資本主義3 偽りの個人主義を越えて』東洋経済
6年前
ハラリ、ギャロウェイ、ガブリエル他『欲望の資本主義3 偽りの個人主義を越えて』東洋経済
6年前
-
 良品計画『無印良品の業務標準化委員会』誠文堂新光社
6年前
良品計画『無印良品の業務標準化委員会』誠文堂新光社
6年前
-
 河田剛『不合理だらけの日本スポーツ界』ディスカヴァー21
6年前
河田剛『不合理だらけの日本スポーツ界』ディスカヴァー21
6年前
-
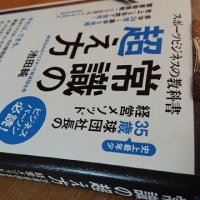 池田純『常識の超え方』文藝春秋
6年前
池田純『常識の超え方』文藝春秋
6年前
-
 丸山俊一『AI以後』NHK出版新書
6年前
丸山俊一『AI以後』NHK出版新書
6年前
-
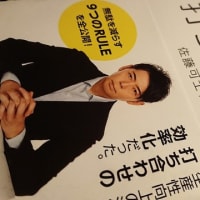 佐藤可士和『佐藤可士和の打ち合わせ』日経ビジネス人文庫
6年前
佐藤可士和『佐藤可士和の打ち合わせ』日経ビジネス人文庫
6年前
-
 倉田剛『日常世界を哲学する』光文社新書
6年前
倉田剛『日常世界を哲学する』光文社新書
6年前
-
 ジェラルド・ガーニー他『アメリカの大学スポーツ 腐敗の構図と改革への道』玉川大学出版部
6年前
ジェラルド・ガーニー他『アメリカの大学スポーツ 腐敗の構図と改革への道』玉川大学出版部
6年前
-
 村上春樹/安西水丸『夜のくもざる』新潮文庫
6年前
村上春樹/安西水丸『夜のくもざる』新潮文庫
6年前









