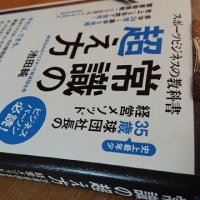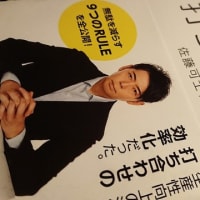経営コンサルティングの仕事を実際にやると、MBAの「経営ごっこ」やわけのわからない横文字のフレームワーク、学歴などが通用しないことがわかったと冨田氏はいう。
冨田氏は東大現役時代に司法試験に合格し、卒業後スタンフォードのMBAを取得し、BCGに入社した。それが中小企業の再建に関わり、自身が中小のコンサルティング会社に転職し、のちに社長になり、バブル崩壊の時期に倒産の危機にも遭遇した。
冨田氏のコンサルティングの経験では、東大出身の大企業幹部や省庁の官僚はその制度で上り詰めたので、この制度を壊そうとしないし、ビジネスが儲かるか儲からないかより、リスクを取らない方法を必死で探し、穏当に処理したいとまず考えるのだそうだ。およそ学歴が評価されない現場の人々のほうがひたむきに働くし、ベンチャー企業のほうが意思決定が早く、ビジネスを成功させるのに向いているらしい。カネボウの再建でも現場の女性が売れる仕組みを必死で考えたのが成功の要因だという。
会社の修羅場でこそ、人間の本性が見える。倒産するか立て直すかという土壇場でこそ、その人の人間性が見えてくるというのは慧眼だ。しがみついてでも再建に尽力する人、昨日までのライバル会社にさっさと転職する人、出向先に戻ることばかりを優先する人など様々らしい。
再建のポイントは次の3つを知り、自社に当てはめ、何を優先してすべきかを戦略(仮説)として立てることだ。
①その事業の経済状況、消費者を知る
②競合状況を知る
③経済の仕組み(成功するビジネスモデル)を知る
これをもとにPDCAで何がどこまで到達したか、何が間違っていたのかをフィードバックする。「組織は戦略にしたがう」のでも「戦略が組織にしたがう」のでもなく、戦略はあくまで仮説であり、そので合理と情理を尽くした人々により変えていくものなのだ。
組織では人がすべてであり、人が何を感じ、何を考え、何によって働こうと思うのかが需要なのだ。それを良い方向にもっていくことこそマネジメントだという。
部長になるとパフォーマンスが下がるのが日本の現状だという。調整のために人と話をする時間が長く、書類に適当に判子を押して、会議で威張り散らすというような人が多い。そうならないためには、若い人に部長を譲るか、老兵は去るか(会社から出るか)、それを避けるためには人並み以上の研鑽に励むか。
冨田氏は東大現役時代に司法試験に合格し、卒業後スタンフォードのMBAを取得し、BCGに入社した。それが中小企業の再建に関わり、自身が中小のコンサルティング会社に転職し、のちに社長になり、バブル崩壊の時期に倒産の危機にも遭遇した。
冨田氏のコンサルティングの経験では、東大出身の大企業幹部や省庁の官僚はその制度で上り詰めたので、この制度を壊そうとしないし、ビジネスが儲かるか儲からないかより、リスクを取らない方法を必死で探し、穏当に処理したいとまず考えるのだそうだ。およそ学歴が評価されない現場の人々のほうがひたむきに働くし、ベンチャー企業のほうが意思決定が早く、ビジネスを成功させるのに向いているらしい。カネボウの再建でも現場の女性が売れる仕組みを必死で考えたのが成功の要因だという。
会社の修羅場でこそ、人間の本性が見える。倒産するか立て直すかという土壇場でこそ、その人の人間性が見えてくるというのは慧眼だ。しがみついてでも再建に尽力する人、昨日までのライバル会社にさっさと転職する人、出向先に戻ることばかりを優先する人など様々らしい。
再建のポイントは次の3つを知り、自社に当てはめ、何を優先してすべきかを戦略(仮説)として立てることだ。
①その事業の経済状況、消費者を知る
②競合状況を知る
③経済の仕組み(成功するビジネスモデル)を知る
これをもとにPDCAで何がどこまで到達したか、何が間違っていたのかをフィードバックする。「組織は戦略にしたがう」のでも「戦略が組織にしたがう」のでもなく、戦略はあくまで仮説であり、そので合理と情理を尽くした人々により変えていくものなのだ。
組織では人がすべてであり、人が何を感じ、何を考え、何によって働こうと思うのかが需要なのだ。それを良い方向にもっていくことこそマネジメントだという。
部長になるとパフォーマンスが下がるのが日本の現状だという。調整のために人と話をする時間が長く、書類に適当に判子を押して、会議で威張り散らすというような人が多い。そうならないためには、若い人に部長を譲るか、老兵は去るか(会社から出るか)、それを避けるためには人並み以上の研鑽に励むか。