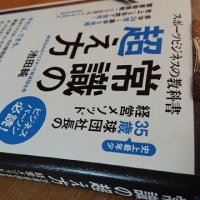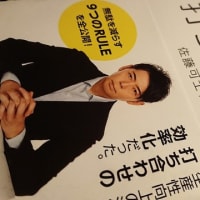王陽明の言いたいことがやっとわかってきた。
この本は王陽明の『伝習録』現代日本語版である。
ほんとうに凡人でもよく理解できるように訳してある。
著者は解説の最初でこう書いている。
「王陽明が繰り返し述べているのはただ一つのことである。性善説、つまり人間の本質は本来完全であるから根源的に悪の世界からすでに救われているという確信に根ざした、自力による自己実現・自己救済に他ならない。これを基本的視覚に据えてこそ、はじめて『伝習録』の一つ一つの語録の主旨が明白になると言っても過言ではない」
意識とは具体的な客体なしにははたらくものではない。・・・意識を誠のままにしようと思ったならば、意識がはたらきかけている具体的な対象に即して主客関係を正しくし、意識が誠のままにはたらくのを妨げている欲望を昇華して、本来の天理の発現にゆだねたならば、良知はこのような主客関係においては、さまたげられることもないので、本来の自己を発揮することができる。
p.39
解説では、こう書かれている。
王陽明は朱子学の格物論の物を、外在する客観物が内在する理法と誤解しているが、主体者と他者との社会関係を正しくすることが格物と理解した。そのため、格物を「主客関係を正しくする」としている。正しくする主体が良知・明徳である。良知=主体の客体に対する働きかけが「意」。はたらきかけが主客関係(物)を生む。この意に良知が発現してその完全さを実現することが「誠意」。格物・致知・誠意はひとつのことなのである。
主体の客体への働きかけを「感」、客体が自らの本質を主体に顕現することを「応」という。主客関係の緊張とはこの感応のこと。
また、弟子が「私は書類整理や訴訟処理がとても煩雑困難なので、学問しようにもできません」と言ったら、王陽明はこう言ったそうだ。
役人としての仕事を遂行する中で学問をしなさい。それでこそ主客関係を正しくするということなのです。・・・被疑者の態度が横柄だからと言って怒ってはいけないし、彼らの陳述が如才ないからと言って喜んでもいけない。・・あなた自身がいささかでも平衡を失って他人の是非を抑圧しないことが、主客関係を正して良知を発揮することです。実践の場を離れて学問するというのでは現実逃避です」p.88
良知についても、王陽明の言葉からなんとなくわかる。
良知=是非
良知とは、正しいことは正しい、正しくないことは正しくないと判断する主体者のことに他ならない。・・・それをうまくやれるかはその人いかんによる。
P.252
七情(喜怒哀懼愛悪欲)を善か悪かと決めつけることはできない。しかし執着することがあってはいけない。七情が執着するとそれを欲という。それが良知を蔽うのである。良知がそれに気づけば蔽いはなくなり、本来の姿を回復する。p.256
素質の優れた人なら、本源に視点を据えて、人心の本体はもともと微塵の汚染もない明澄なものである、もともと「未発の中」であることをストレートに覚醒する。その次の素質の人は、習心がどうしても身についてしまうから本体は蔽われてしまう。そのためにとりあえず意念の場で着実に善を実現し悪を排除させるのである。その努力が成果を生み、汚染物がすっかり除去されると本体はもとどおりすっかり明澄になる。P.315
子どもが先生や年長者を畏敬することをわきまえることなども、子どもの良知がそうするのである。進んでお辞儀して尊敬の念を表すのも、子どもが主客関係を正しくして、良知を発揮したことなのである。P.338
中国の思想は今ひとつよくわからない。
これは西洋思想でも似ているが用語の定義が人によって違うからだろう。
いや用語=概念の理解の仕方によって思想を発展させていると言ってもいいかもしれない。孔子の人間の本性を巡る孟子の性善説も、陸象山、王陽明へと発展しているのだろう。
王陽明が当時の朱子学に対して、本を読んで賢くなるのが人生の目的ではなく、また仏教のように山にこもって悟りをひらくのではなく、現実の世界の中で人間が本来持っている善の世界を実現しようとしたことはよくわかる。それが権威主義批判になり敵をつくったことも王陽明にすれば仕方がないことだったのだろう。
この思想と三島由紀夫の割腹自殺との関係についてはよくわからないが。いろんな読み方ができる思想なのかもしれない。
幕末の志士に影響を与えたのは王陽明のこういう言葉だろう。
きみが本当に聖人になってやるぞという志があるなら、良知はすっかり発現するのである。それ以外の考えが良知にまといついているようでは、ぜひとも聖人になってやるぞという志ではないのだ。p.189
この本は王陽明の『伝習録』現代日本語版である。
ほんとうに凡人でもよく理解できるように訳してある。
著者は解説の最初でこう書いている。
「王陽明が繰り返し述べているのはただ一つのことである。性善説、つまり人間の本質は本来完全であるから根源的に悪の世界からすでに救われているという確信に根ざした、自力による自己実現・自己救済に他ならない。これを基本的視覚に据えてこそ、はじめて『伝習録』の一つ一つの語録の主旨が明白になると言っても過言ではない」
意識とは具体的な客体なしにははたらくものではない。・・・意識を誠のままにしようと思ったならば、意識がはたらきかけている具体的な対象に即して主客関係を正しくし、意識が誠のままにはたらくのを妨げている欲望を昇華して、本来の天理の発現にゆだねたならば、良知はこのような主客関係においては、さまたげられることもないので、本来の自己を発揮することができる。
p.39
解説では、こう書かれている。
王陽明は朱子学の格物論の物を、外在する客観物が内在する理法と誤解しているが、主体者と他者との社会関係を正しくすることが格物と理解した。そのため、格物を「主客関係を正しくする」としている。正しくする主体が良知・明徳である。良知=主体の客体に対する働きかけが「意」。はたらきかけが主客関係(物)を生む。この意に良知が発現してその完全さを実現することが「誠意」。格物・致知・誠意はひとつのことなのである。
主体の客体への働きかけを「感」、客体が自らの本質を主体に顕現することを「応」という。主客関係の緊張とはこの感応のこと。
また、弟子が「私は書類整理や訴訟処理がとても煩雑困難なので、学問しようにもできません」と言ったら、王陽明はこう言ったそうだ。
役人としての仕事を遂行する中で学問をしなさい。それでこそ主客関係を正しくするということなのです。・・・被疑者の態度が横柄だからと言って怒ってはいけないし、彼らの陳述が如才ないからと言って喜んでもいけない。・・あなた自身がいささかでも平衡を失って他人の是非を抑圧しないことが、主客関係を正して良知を発揮することです。実践の場を離れて学問するというのでは現実逃避です」p.88
良知についても、王陽明の言葉からなんとなくわかる。
良知=是非
良知とは、正しいことは正しい、正しくないことは正しくないと判断する主体者のことに他ならない。・・・それをうまくやれるかはその人いかんによる。
P.252
七情(喜怒哀懼愛悪欲)を善か悪かと決めつけることはできない。しかし執着することがあってはいけない。七情が執着するとそれを欲という。それが良知を蔽うのである。良知がそれに気づけば蔽いはなくなり、本来の姿を回復する。p.256
素質の優れた人なら、本源に視点を据えて、人心の本体はもともと微塵の汚染もない明澄なものである、もともと「未発の中」であることをストレートに覚醒する。その次の素質の人は、習心がどうしても身についてしまうから本体は蔽われてしまう。そのためにとりあえず意念の場で着実に善を実現し悪を排除させるのである。その努力が成果を生み、汚染物がすっかり除去されると本体はもとどおりすっかり明澄になる。P.315
子どもが先生や年長者を畏敬することをわきまえることなども、子どもの良知がそうするのである。進んでお辞儀して尊敬の念を表すのも、子どもが主客関係を正しくして、良知を発揮したことなのである。P.338
中国の思想は今ひとつよくわからない。
これは西洋思想でも似ているが用語の定義が人によって違うからだろう。
いや用語=概念の理解の仕方によって思想を発展させていると言ってもいいかもしれない。孔子の人間の本性を巡る孟子の性善説も、陸象山、王陽明へと発展しているのだろう。
王陽明が当時の朱子学に対して、本を読んで賢くなるのが人生の目的ではなく、また仏教のように山にこもって悟りをひらくのではなく、現実の世界の中で人間が本来持っている善の世界を実現しようとしたことはよくわかる。それが権威主義批判になり敵をつくったことも王陽明にすれば仕方がないことだったのだろう。
この思想と三島由紀夫の割腹自殺との関係についてはよくわからないが。いろんな読み方ができる思想なのかもしれない。
幕末の志士に影響を与えたのは王陽明のこういう言葉だろう。
きみが本当に聖人になってやるぞという志があるなら、良知はすっかり発現するのである。それ以外の考えが良知にまといついているようでは、ぜひとも聖人になってやるぞという志ではないのだ。p.189