
【原文】
万の咎あらじと思はば、何事にもまことありて、人を分かず、うやうやしく、言葉少からんには如かじ。男女・老少、皆、さる人こそよけれども、殊に、若く、かたちよき人の、言うるはしきは、忘れ難く、思ひつかるゝものなり。
万の咎は、馴れたるさまに上手めき、所得たる気色して、人をないがしろにするにあり。
万の咎は、馴れたるさまに上手めき、所得たる気色して、人をないがしろにするにあり。
【現代語訳】
何事でも失敗を避けるためには、いつでも誠実の二文字を忘れずに、人を差別せず、礼儀正しく、口数は控え目でいるに越したことはない。男でも女でも、老人でも青二才でも同じ事である。ことさら美男子で言葉遣いが綺麗なら、忘れがたい魅力になろう。
様々な過失は、熟練した気で得意になったり、出世した気で調子に乗って人をおちょくるから犯すのだ。
様々な過失は、熟練した気で得意になったり、出世した気で調子に乗って人をおちょくるから犯すのだ。
◆鎌倉末期の随筆。吉田兼好著。上下2巻,244段からなる。1317年(文保1)から1331年(元弘1)の間に成立したか。その間,幾つかのまとまった段が少しずつ執筆され,それが編集されて現在見るような形態になったと考えられる。それらを通じて一貫した筋はなく,連歌的ともいうべき配列方法がとられている。形式は《枕草子》を模倣しているが,内容は,作者の見聞談,感想,実用知識,有職の心得など多彩であり,仏教の厭世思想を根底にもち,人生論的色彩を濃くしている










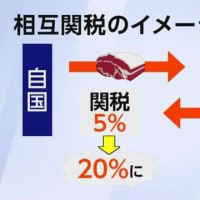









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます