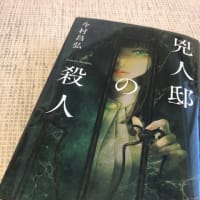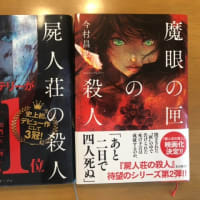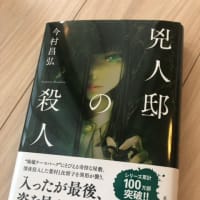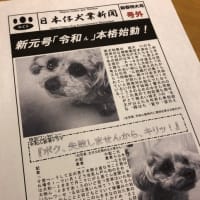毎年5/2・5/3に行われるという地元のだんじりを見るために街に出た。去年は仕事で見ることができなかったが、今年はがっつり夜まで、だんじりに張り付いて巡行の様子を追ってみた。

途中、主要幹線道路やバス道を通行したり横断したりするのだが、そもそも公共交通機関の通るみちなんざ、このお祭りの起源よりずっとあとのもの。警察官やガードマンさんが体を張って交通整理をしてくださるおかげで、滞りなく巡行は進められていくのだ。

大きな道路だけでなく、だんじりが往来できる限りのおよそ幅員4m以上の道路を進み、御花代を寄贈したお宅の前で止まり、表札に「御花御礼」というお札を貼り、更には

だんじりの片輪を持ちあげて、御礼の意思を伝える儀式を行うのである。

地域のほぼ全てを急峻な坂道で構成されているにも関わらず、辻毎に右折左折を繰り返しながら、また方向転換を繰り返しながら巡行は続くのである。だんじり自体の動力源は青年以上の老若男子、それに先行する形で未成年女子と幼年期男女が綱を引き、大きく元気な掛け声で地車を先導していくのである。

中には、こんな小さな子もいる。(↑顔出し了承済みナリ)
休憩時間には子供用のジュースを配布したり、おトイレの世話をしたり、綱を持つ子供たちの間隔を調整したり、子供たち同士で喧嘩をしたりしないように配慮したり、泣きそうな子供たちに愛情を注ぐ女形世話人の若い女の子たちがいる。それぞれの年代のそれぞれの立場の人がそれぞれの役割を課されていて、それぞれの役目を果たしている姿が輝かしく思える。何と言うか、こういう地域で生まれ育っていない私としては、近年稀にみる超地域密着型のお祭りやなあと、とても羨ましく感じるのである。

ちなみに、今年は5/2の地車巡行は雨で中止に、5/3は途中で小雨が降りだすも、だんじり用の雨具が装備されており、途中で手順よく装着されて巡行は続行された。

車一台通るのがやっとであるような坂道も登って行く。その間、地車から奏でられるチンドンのリズムに乗って子供たちの元気な「押せ!」「押せ!」というお囃子が街中に響き渡る。

重量のある地車の通った後には必ずこんな轍が残る。何の変哲もない辻なのに最低2回、ここを往来したことになる。

やがて、河内国魂神社春季大祭に参加している「上野」「五毛」「畑原」「篠原」の4地区の地車が上野中学校の南側に集結し、そのまま神社参道となる通り目がけて巡行していく。だんだんと人の密度が濃くなり、祭の様相を醸し出してくる。

普段はここが本当に参道なのかどうなのかもよくわからない一住宅地の道路。いたって普通に民家が並んでいる。ここが2日間にわたり歩行者天国になり屋台が並ぶ。

そして、この屋台の軒先ギリギリの空間を縫うようにして地車が一気に駆け上がってくるのである!!

クライマックスへの突入前、地車の提灯に灯りが灯される。少し空が暗くなってきたタイミングで第1陣の「上野」の地車が参道の坂道を駆け上がる。しかも前輪を持ち上げたままのウイリー状態でのハイパーダイナミックワイルド走行である。各地区ごとに地域のカラーが違っていて、一気に駆け上がるところもあれば、掛け声を大切にして地道に上がるところもあるし、また、ゆっくりゆっくり歩きなかなか上がって来ないのもある。地車が通れないところに屋台の軒先が出てしまっている場合は、もちろん屋台が譲歩して、テントの一部を撤去したり移動させたりしていて、そういうことの1つ1つが私には新鮮に思えた。

地車は神社の境内には入らずに入り口の大階段の前で脇道で待機したりパフォーマンスをしたりする。中でも大迫力だったのが「畑原」のパフォーマンス。境内前の小さな辻のど真ん中で大きな地車の片輪を持ちあげたまま何度もグルグルと高速で回転するのである。

いやあ、ど迫力やったよ。

全ての地車が境内前に集結することで、全ての地車が「宮入り」を果たしたことになる。このあと、各地区の地車は各地区の地車の格納庫に帰って行く。「五毛」の地車はこの神社の脇にいつも格納しているのだが、何故か「篠原」の地車を追うようにして進んで行くのである。地域の人の会話に耳を澄ましてみると、隣接する地域にある厳島神社の「篠原」と河内国魂神社の「五毛」は昔からの付き合いがあり、お祭りごとに呼ばれ呼び合いをしている中なのだとか。
ちょうど神社同士の結界の境となる杣谷川にかかる橋の西の袂には「五毛天神(※)」の幟(のぼり)が、東の袂には「厳島神社」の幟(のぼり)が立てられているのだが、「篠原」の地車がその橋を「厳島神社」界側に渡り切って停止し、「五毛」の地車は橋を渡らず「五毛天神」界側に留まり、「五毛」の地車が別れを惜しむかのように片輪を持ちあげて惜別の意を伝えると、「篠原」の地車はそれに呼応するがごとく東進を始め、また「五毛」の地車も西進を始めるのである。それぞれの地車が人格を持っているかのような心温まる儀式である。
※:河内国魂神社は五毛天神という名でも呼ばれている。由緒についてはここでは省略する。

篠原の地車を送り届けた五毛の地車は無事、河内国魂神社に帰りつき、

所定の場所に格納され、

大歓声・大喝采の中で大祭を終えたのであった。

「畑原」の地車がグルグル回った後。確か、去年もこの場所にこんな跡があったように思うけど、まさかあんなに激しく回しているとは思わなかったし、なるほどマンホールを中心軸にして回していたんだあと妙に納得。本当にぶれないで綺麗に回していたもんなぁ。。。

「五毛」の子供たちはみんな鈴をジャラジャラさせて綱を引いているのだけれど、最後まで残っていた子供たちに、ご褒美(?)の色のついた鈴が1個ずつ配られる。何年も参加している子供は幾つもの鈴を持っていて、それがある種のステータスみたいになっている。
そんなこどもたちが徐々に大きく成って行って、巡行の休憩中には地車乗らせてもらって、祭の無い日常の日々も地域の大人と子供が見えない絆で守られていて、いずれはその中の何人かの子供たちが地車の担ぎ手となったり世話役になったりしながらこのコミュニティは形成されていっているのだなあと思うと、とても羨ましく思うし、半ば部外者の私には、ちょっぴり寂しく思えたりするのである。
巡行中にこどもたちが、ふざけて危ないことしていたら、法被を着た世話役のおじさんたちは子供がビビる剣幕で怒っていて、でもそれでいて、大人目線でみると、すごく愛情のある叱り方に見えたものである。私にはあんな高度な叱り方は出来ないなあと思ったし、それをみたときに「あぁ、いいなぁ、この子たちは真剣に怒ってもらって」と思ったものである。