 そんなにコロコロ教科書の記述が変わるなら、何の為に学習しているのか。
そんなにコロコロ教科書の記述が変わるなら、何の為に学習しているのか。
私達は「大化の改新」が「乙巳の変」になっただけで十分カルチャーショックだし
聖徳太子の絵や足利尊氏の絵が全部偽物だからーーという話にもかなりショックでしたし、これ以上やめてーーと思っていたら、今度は「鎖国」が消えるそうです。
 「鎖国」=「幕府の対外政策」
「鎖国」=「幕府の対外政策」
 はあ?覚えにくいと思うでしょ。でもこの時代、日本はオランダなどと貿易をしていたからという理由らしい。
はあ?覚えにくいと思うでしょ。でもこの時代、日本はオランダなどと貿易をしていたからという理由らしい。
でも、貿易してたのは長崎の出島だけで・・・と思ったら、薩摩など3か所が国を開いていたらから・・・という理由らしい。
でもわかりにくいんじゃないの?
 幕府の対外政策で海外貿易はオランダや中国などに限り長崎の出島に限定しました。
幕府の対外政策で海外貿易はオランダや中国などに限り長崎の出島に限定しました。
っていう書き方。全然「何で?」「どうして?」が浮かんでこない。
こんな歴史の教科書、変だよっ
確かに「鎖国」という言葉を当時は使っていなかったと思います。
じゃあ、幕末の「開国」はどうなるんですかね?鎖国してないのに開国するの?
開国をやめて明治政府の対外政策にするんでしょうか?
何をもって「鎖国」というか・・・・それは貿易云々って話だけではありませんよね?
今回のトランプ政策のように、一旦、国を出た者が日本に帰って来た時に受け入れられないっていう話でしょう?国を出る事も帰国する事も許されないから「鎖国」なんじゃないでしょうか?
(いや、アメリカが鎖国政策をとっているなどという気はありませんが)
これでさらに日本史のテスト勉強はやりにくくなり、興味を持つ人が減る。そしたら中韓に謝りっぱなしかあ。さすが文科省です。
 「聖徳太子」=「厩戸王」(聖徳太子)
「聖徳太子」=「厩戸王」(聖徳太子)
 これまた、当時、用明天皇の第一王子にして、推古天皇の摂政を「聖徳太子」と呼んでいたわけではありませんよね。
これまた、当時、用明天皇の第一王子にして、推古天皇の摂政を「聖徳太子」と呼んでいたわけではありませんよね。
では「厩戸王」と呼ばれていたの?「うまやどのおう」「うまやどのおおきみ」どっち?
私はてっきり「厩戸王子」だと思っていましたけど

聖徳太子は後の「尊称」なわけで間違いではないと思いますが。
最近じゃ中大兄皇子を葛城王子というらしいし、大海人皇子は中大兄皇子より年上だったーーっていうのはガチっぽいし。
でも「古事記」より「日本書紀」の方が先に書かれたという事はまだ教科書には載っていないようですけどね。
去年、講演会の為に山川の教科書を買い、一生懸命に読んだのですが、実はさっぱり意味がわからなくて。
曖昧な記述が多すぎるし「だからどうなの?」的なものも多くて、結局結論は何?ってものばかりで。全然これじゃテスト勉強にもならないし、日本史を専攻する人が減るんじゃないかと心配になりました。
世界史の方はそんなに記述は変わってないし覚えやすい。
日本史だけがこんなにころころ名称が変わったりするのはおかしいのでは?










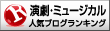


















一般の感覚はそんなもんなんですね。
山川の教科書、私は分かりやすいと思いましたが。現に、大学受験では山川を読み込めば大丈夫と言われてましたし。
それでもキリスト教宣教師+武器商人+奴隷商人のセットで日本に切り込むつもりが、そんなことよりまともに貿易した方が遥かに儲かることがわかり、出島でオランダは貿易するように成ったのですね~って言われていますが…昔もので釈然としませんね(笑)…
でも、研究が進めば進むほどこれまでの言い方は間違っていた、言い方が適切ではなかった、事実にそぐわなかったとなって教科書の記述も変わっていきます。
教科書の記述がコロコロ変わるのは、それだけ今日進月歩で、日本史研究が進んでいるということの裏返しでもあります。
士農工商、鎖国、大化改新、これまで通りの意味でその時代に歴史事実として「あった」とは言えない。それは確かだ、となったから記述が変わっているのです。
正しくなくても(士農工商も鎖国も、大化改新もこれまで通りの意味では正しくない=事実ではないです)、勝手な定義を作っても(1192作ろう鎌倉幕府が消えたのは、いつをもって幕府が開かれたと定義するかについての議論が始まったからです。逆を言えば、昔は頼朝が征夷大将軍になった、ということぐらいしか確かなことがなかったけれど、現在では色々な文書が出てきてなにができたのか、支配はどこまで及んでいたか、朝廷との関係は、などについても考えることができるようになったのです)、いいとするならそれはふぶき様の嫌いな韓国歴史と同じですよ。
私としては研究の流れを追い、確かだとなれば(確かだと確定するスピードが昔と比べ速くなっているのは事実です。扱う史料が増えたことなどで多方面から一つの事実を示せるようになったので)速やかに改訂する山川は非常に良心的な出版社だと思っています。
ついでに、世界史が昔と比べ変わらないのは日本史と比べ浅く広くで明白な事実(〜条約が結ばれた。その内容は〜と書かれている)を述べるに止まっていることや、公文書の扱いが日本とは違い残っていることが多いので、事実を追いやすかったりするためです。でも、ジャンヌダルクに関する記述などはアップデートされていますよ。
教科書の知識を元に史料を読み解く問題や時代の流れ、背景を踏まえどうしてそのようなことが起きたか、など論述する問題が増えています。昔と比べ、年号や名前の暗記よりも流れを抑え、それを踏まえどう考えるかということが大切にされています。
歴史という教科の姿勢が変わったと捉えられてはいかがでしょうか。昔より暗記偏重でなく、面白い教科になっていると思いますよ。
日本の根本的な本質は日本人として脈々と続いているとは思うのですが、たゆまない研究によって新たな史実がわかる事は面白いと思います。左とか右とかにとらわれすぎるずに、事実を淡々と視るのも必要かと。
それがなぜ、記述が変わる=勉強をする人がいなくなって中韓云々の話になるのか…直ぐにそういう方向に持っていきたがるのですね。新しい事実が判明しても、記述を変えるなということですか?それでは学問として進歩しませんよ。新しいことを受け入れたくないということは、歳をとった証拠では?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天正15年(1587年)6月18日、豊臣秀吉は宣教師追放令を発布した。
その一条の中に、ポルトガル商人による日本人奴隷の売買を厳しく禁じた規定がある。
日本での『鎖国体制確立』への第一歩は、奴隷貿易の問題に直接結びついていたことがわかる。
「大唐、南蛮、高麗え日本仁(日本人)を売遣候事曲事(くせごと = 犯罪)。
付(つけたり)、日本におゐて人之売買停止之事。
右之条々、堅く停止せられおはんぬ、若違犯之族之あらば、忽厳科に処せらるべき者也。」
(伊勢神宮文庫所蔵「御朱印師職古格」)
日本人を奴隷として輸出する動きは、ポルトガル人がはじめて種子島に漂着した
1540年代の終わり頃から早くもはじまったと考えられている。
16世紀の後半には、ポルトガル本国や南米アルゼンチンにまでも日本人は送られるようになり、
1582年(天正10年)ローマに派遣された有名な少年使節団の一行も、
世界各地で多数の日本人が奴隷の身分に置かれている事実を目撃して驚愕している。
「我が旅行の先々で、売られて奴隷の境涯に落ちた日本人を親しく見たときには、
こんな安い値で小家畜か駄獣かの様に(同胞の日本人を)手放す我が民族への激しい念に燃え立たざるを得なかった。」
「全くだ。実際、我が民族中のあれほど多数の男女やら童男・童女が、
世界中のあれほど様々な地域へあんなに安い値でさらっていって売りさばかれ、
みじめな賤業に就くのを見て、憐 憫の情を催さない者があろうか。」
といったやりとりが、使節団の会話録に残されている。
この時期、黄海、インド洋航路に加えて、マニラとアカプルコを結ぶ太平洋の定期航路も、
1560年代頃から奴隷貿易航路になっていたことが考えられる。
秀吉は九州統一の直後、博多で耶蘇会のリーダーであったガスパール・コエリョに対し、
「何故ポルトガル人はこんなにも熱心にキリスト教の布教に躍起になり、
そして日本人を買って奴隷として船に連行するのか」と詰問している。
南蛮人のもたらす珍奇な物産や新しい知識に誰よりも魅惑されていながら、
実際の南蛮貿易が日本人の大量の奴隷化をもたらしている事実を目のあたりにして、
秀吉は晴天の霹靂に見舞われたかのように怖れと怒りを抱く。
秀吉の言動を伝える『九州御動座記』には当時の日本人奴隷の境遇が記録されているが、
それは本書の本文でたどった黒人奴隷の境遇とまったくといって良いほど同等である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこから鎖国という考え方が生まれたのかもしれません・・鎖国というより、日本人を奴隷として売るようなキリシタン大名は・・アカン!となったんでしょうか?
そう考えると遠藤さんの『沈黙』もありがたみが薄くなります
みもふたもない言い方をすると、歴史なんてそもそも伝聞で真実かどうか誰にも判らない話。中学のレベルでおなかいっぱいで、選択する必要性を感じませんでした。地理はまだ生活に役に立つことも多く、興味も持てたのですが。
ただ大人になって隣国人の「嘘も百回言い続けていれば真実に変わる」という民族性を知ってからは、次世代が誤った歴史を学ばないように、と強く願うようになりました。教科書についても編集者の曲がった思想が反映されていない物を、と切に希望します。