映画「日本の夜と霧」は1960年安保闘争直後に製作された大島渚監督作品だ。
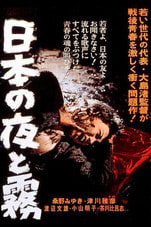
先日大島渚監督の作品「青春残酷物語」を見た。その同じ年に松竹映画として製作された作品だ。
ところが、公開後4日で松竹は上映中止とする。大島渚監督は猛抗議したが、結局松竹を退社することになる。どんな映画なんだろうと思っていたが、まあクズたちがつまらない会話を繰り広げるひどい映画だ。60年安保にとらわれた学生たちを見て、こんな時代に学生生活をすごさなくて本当に良かったと実感させられる作品だ。
日本史の裏の一面を探るという意味では意義があるといってもいい。
ある集会所で、結婚式が始まっている。雛壇には新郎の野沢(渡辺文雄)と新婦(桑野みゆき)と媒酌人を務める大学教授(芥川比呂志)がいる。司会を務めるのは学生運動の元リーダーと思しき男とその妻(小山明子)だ。リーダーは共産党員らしい。
1950年代初頭に学生活動家だったと思しき面々が参列者に集まっている。宴が進む中、突然1人の全学連活動家(津川雅彦)が乱入してくる。彼は安保闘争で指名手配中の身だ。彼はその日もデモに参加してきたという。

安保反対デモのときは5万人集まっていたのに、今では500人しか集まっていないと不満そうな津川だ。そうしていくうちに、津川はここに集まっている元活動家の男女関係について暴露し始めるのだが。。。。
映画では共産主義思想に満ちあふれたような連中がしゃべりまくっているようだけど、中身はない。
以前戦後の知性を代表する加藤周一がこう言っていた。
「左翼政治理論というものは、しばしば、私たちの理解を絶していることがあります。耳慣れぬ抽象的な言葉がたくさん出てきて、どこへ続くかわからない。。。。。問題なのは、そういう論文を書いた筆者の知的能力である。。。。言葉の定義があきらかでなく、整理もつかず、つじつまも合わず、何を言っているのか誰にもわからないというのは筆者の頭の混乱を示している」
まさしくここに出てくるクズどものセリフはまさにその通りだ。安保反対の論陣を張った加藤周一がまわりのバカどもに呆れていったセリフだけど、60年代後半の学生運動のバカも同じようなレベルと言っていい。
何か高尚な話をしているようだけど、映画の主題は単なる不健全な男女関係のもつれである。
連合赤軍のような悲惨な事件にはなってはいないけど、大して変わらない。
フォークダンスなんかを劇中踊ってというのもいやなかんじだ。
ここで踊っているようなババアたちが今も共産党の署名活動なんかやっているのかなあ。
それにしても、普通の工員をスパイ容疑と言って学生寮に監禁する話が恐ろしい。
自分の大学時代には全くこういう雰囲気が学内になかった。
1度や2度学内で過激派と思しき野郎を見たことあるけど、それだけだ。
先日佐藤優「私のマルクス」を読んだ。彼は自分とほぼ同世代だけど、まったく違った高校大学時代を送っていたので驚いた。浦和高校ではアカ教師の影響を受け、同志社大学に入ったら学生運動家や思想家と付き合う。結局外務省に入る彼は若干違った方向に進んだが、自分からすると異常な学生生活だ。京都は東京とは違って共産党の強いところだからそんな感じになったのかなあ??大島渚も京大出身のアカかぶれだ。でも意外にアカ男ってもてるんだよなあ。
元学生運動家の役には、昭和40年代のテレビドラマによく映っていた面々がそろう。戸浦六宏や佐藤慶なんていうのは、名悪役といっていいだろう。現代劇だけでなく、悪代官の典型みたいな役が多かった。
渡辺文雄がどちらかというと、ナイスミドルの中年男性のイメージで、津川雅彦も同様のイメージ、ここではまだ若い。津川は石原裕次郎主演の「狂った果実」の青年役で痛烈な印象を残したが、ここでは軟派と真逆の左翼青年となる。
芥川比呂志がいかにも大学教授といった風貌だ。ぴったり合っている。それにしても驚くのが小山明子の美貌である。本当に美しい。自分が知っている彼女は昭和40年代以降にテレビドラマで演じていた良妻賢母役だ。ここでは女を感じさせる。このあとすぐ大島渚と結婚する。これはうらやましい。

本当にこういう時代に大人になっていなくて良かった。
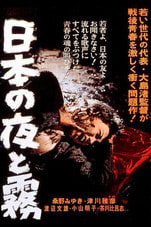
先日大島渚監督の作品「青春残酷物語」を見た。その同じ年に松竹映画として製作された作品だ。
ところが、公開後4日で松竹は上映中止とする。大島渚監督は猛抗議したが、結局松竹を退社することになる。どんな映画なんだろうと思っていたが、まあクズたちがつまらない会話を繰り広げるひどい映画だ。60年安保にとらわれた学生たちを見て、こんな時代に学生生活をすごさなくて本当に良かったと実感させられる作品だ。
日本史の裏の一面を探るという意味では意義があるといってもいい。
ある集会所で、結婚式が始まっている。雛壇には新郎の野沢(渡辺文雄)と新婦(桑野みゆき)と媒酌人を務める大学教授(芥川比呂志)がいる。司会を務めるのは学生運動の元リーダーと思しき男とその妻(小山明子)だ。リーダーは共産党員らしい。
1950年代初頭に学生活動家だったと思しき面々が参列者に集まっている。宴が進む中、突然1人の全学連活動家(津川雅彦)が乱入してくる。彼は安保闘争で指名手配中の身だ。彼はその日もデモに参加してきたという。

安保反対デモのときは5万人集まっていたのに、今では500人しか集まっていないと不満そうな津川だ。そうしていくうちに、津川はここに集まっている元活動家の男女関係について暴露し始めるのだが。。。。
映画では共産主義思想に満ちあふれたような連中がしゃべりまくっているようだけど、中身はない。
以前戦後の知性を代表する加藤周一がこう言っていた。
「左翼政治理論というものは、しばしば、私たちの理解を絶していることがあります。耳慣れぬ抽象的な言葉がたくさん出てきて、どこへ続くかわからない。。。。。問題なのは、そういう論文を書いた筆者の知的能力である。。。。言葉の定義があきらかでなく、整理もつかず、つじつまも合わず、何を言っているのか誰にもわからないというのは筆者の頭の混乱を示している」
まさしくここに出てくるクズどものセリフはまさにその通りだ。安保反対の論陣を張った加藤周一がまわりのバカどもに呆れていったセリフだけど、60年代後半の学生運動のバカも同じようなレベルと言っていい。
何か高尚な話をしているようだけど、映画の主題は単なる不健全な男女関係のもつれである。
連合赤軍のような悲惨な事件にはなってはいないけど、大して変わらない。
フォークダンスなんかを劇中踊ってというのもいやなかんじだ。
ここで踊っているようなババアたちが今も共産党の署名活動なんかやっているのかなあ。
それにしても、普通の工員をスパイ容疑と言って学生寮に監禁する話が恐ろしい。
自分の大学時代には全くこういう雰囲気が学内になかった。
1度や2度学内で過激派と思しき野郎を見たことあるけど、それだけだ。
先日佐藤優「私のマルクス」を読んだ。彼は自分とほぼ同世代だけど、まったく違った高校大学時代を送っていたので驚いた。浦和高校ではアカ教師の影響を受け、同志社大学に入ったら学生運動家や思想家と付き合う。結局外務省に入る彼は若干違った方向に進んだが、自分からすると異常な学生生活だ。京都は東京とは違って共産党の強いところだからそんな感じになったのかなあ??大島渚も京大出身のアカかぶれだ。でも意外にアカ男ってもてるんだよなあ。
元学生運動家の役には、昭和40年代のテレビドラマによく映っていた面々がそろう。戸浦六宏や佐藤慶なんていうのは、名悪役といっていいだろう。現代劇だけでなく、悪代官の典型みたいな役が多かった。
渡辺文雄がどちらかというと、ナイスミドルの中年男性のイメージで、津川雅彦も同様のイメージ、ここではまだ若い。津川は石原裕次郎主演の「狂った果実」の青年役で痛烈な印象を残したが、ここでは軟派と真逆の左翼青年となる。
芥川比呂志がいかにも大学教授といった風貌だ。ぴったり合っている。それにしても驚くのが小山明子の美貌である。本当に美しい。自分が知っている彼女は昭和40年代以降にテレビドラマで演じていた良妻賢母役だ。ここでは女を感じさせる。このあとすぐ大島渚と結婚する。これはうらやましい。

本当にこういう時代に大人になっていなくて良かった。
 | 日本の夜と霧 |
| 60年代安保時代の狂った若者たち | |























































