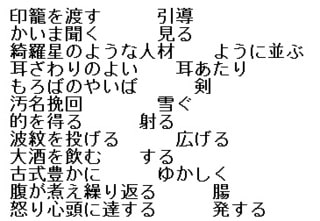最初の4文字を1秒ほど見て眼を閉じ、後ろから思い出そうとしてみます。
たった4文字でしかも間にーが入っているので覚えるのは簡単なはずなのですが、後ろのほうから順に思い出していこうとするとうまくいかなかったりします。
前のほうから思い出そうとするのであればたいていの人は簡単に思い出せるはずです。
記憶するとき、読まないで視覚的なイメージとして記憶しているのであれば、後ろのほうから思い出して読み上げることが簡単にできます。
ところが数字を呼んで記憶すると、読み上げる順序を頭の中で逆にしなければならないので難しくなってしまいます。
「さんよん ろくはち」と読むと、数字を覚えるのでなく音声として覚えていて、想いだすときに頭の中で「はちろく よんさん」と音声を並べ替えようとしたりすると難しくなってしまいます。
音声で覚えるとき頭の中で数字を同時にイメージしていければ、思い出すとき、イメージを右から取り出していけばよいのですが、左から読む癖がついているとこれぐらいでも結構難しい課題になります。
二番目は7つの数字なので1秒程度で視覚的に覚えるのはかなり大変です。
「ごいちろく はちななきゅうに」というように読んで(音読ではなく内言で)音声として覚えることはできます。
しかし左から二番目の数字と右から4番目の数字を足した答えを求められると、右から4番目の数字をどれかつきとめるのに苦労をしてしまいます。
もちろん7つの数字を逆順に想いだすというのも、音声化して記憶している場合は並べ替えを頭の中でやるのが難しいのです。
3行目はアルファベットの4文字ですが、1秒間では数字の場合より記憶しにくいと思います。
音声化しようとすると慣れないせいもあって数字の場合より手間取るため、瞬間的に音声化して記憶するのが難しいのです。
音声化をあきらめて視覚的に記憶すればできるので、視覚イメージとして記憶した後で音声化すればよいのです。
4行目はアルファベットが7文字なので、音声化して記憶するのは1秒程度では数字の場合よりさらに困難です。
音声化して覚えようとしてしまうのは、文字列が横に並んでいると、左から見て読んでいくという癖がついているためで、音声化しないで見るだけで理解したり記憶することができないためです。
脳が理解するスピードは見る速度に比べればはるかに遅いのですが、音声化のスピードはそれよりさらに遅くなります。
音声化をしないで理解することができれば同じところを見続ける時間が少なくなり、眼の負担が減るのですが、左から見るとつい音声化して(心の中で)読んでしまいます。
そこで文字列を見て視覚的に記憶するときに右側から見て記憶する練習をするのもひとつの方法です。