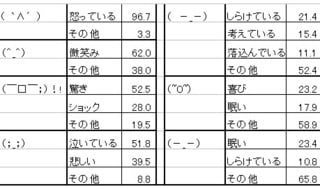図の中央の赤い線に視線を向けた状態で左右を見ると、上の二行の黒い丸はいちばん端まで確認できます。
次のひし形もなんとか確認できます。
ところが4行目の漢字の場合はどうでしょうか。
左右3文字ぐらいづつは読み取ることが出来ても、その外側となると読み取りにくくなるかもしれません。
速読術などでは目を動かさないで文字や図形などを認識できる範囲を、識幅という風に呼ぶらしいのですが、文字を読もうとすると識幅は狭まると言います。
実際、文字を読もうとせずなんとなく4行目を見ると、もっと多くの漢字が見えたような気がするはずです。
また、眼を閉じていてパッと眼を開いた瞬間に4行目を見ると大部分の感じがよく見えたように感じます。
そうすると、「文字を読もうとして注意を向けるから識幅が狭まるのだ」という説明は、ナルホドと思うでしょう。
ところで5行目は察という字ばかりが並んでいます。
真ん中の赤い線に視線を向けて左右を見た場合どの範囲まで読み取れるでしょうか。
いちばん端までは無理としても、4行目の場合よりは多く読み取れるのではないでしょうか。
これは察という文字であると言うことがわかっているから、実際にはハッキリと見えない範囲であっても察という文字だと判断してしまうためです。
いちばん端のほうになるとハッキリと形をとらえられなくなるのですが、左端の黒い丸はそれと認識できるでしょう。
となると漢字を読もうとすると識幅が狭まるといっても、黒丸はわかるのですから、漢字が読み取れないのは複雑な形だからではないかと考えられます。
そこで6行目を見ると、真ん中の赤線に視線を向けたまま左右両サイドを見ると、両端の一と二という文字はハッキリとらえられるけれども、間のいくつかの漢字は読み取れないでしょう。
つまり単純な形をしていれば離れた場所の漢字でも読み取れるのです。
このことは漢字でなく記号を並べた7行目について見ればよりハッキリします。
真ん中の赤線に視線を向けて左右の記号を見ると、真ん中に近い部分はもちろんハッキリ見えるのですが、遠いところでも○や□のように見慣れたものや単純なものが認識しやすくなっています。
つまり中心から離れた形は、細かな部分に注意しなくてもそれとわかるものであれば認識しやすいということなのです。