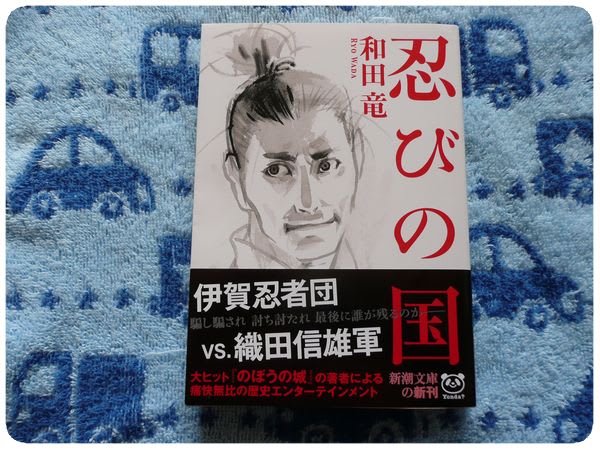
先週一週間、我社は営業活動を自粛していました。毎日会社を出ると自由気儘に歩き回っている私にとっては、社内に閉じ込められ続けるのは苦痛の連続でした。鳥は大空を飛び回るもの、やはりカゴに入れて飼うのは鳥にとっては迷惑この上ないのでしょうね。
年末に『のぼうの城』を読みましたが、同じ作者の『忍びの国』という小説が文庫本で発売されました。表紙に『のぼうの城』のようなインパクトがありませんが、前回面白かったのですぐに手に入れたのでした。
天正4年11月、織田信雄(のぶかつ)=信長の次男が、伊勢の国の領主=北畠具教を暗殺するために、3人の刺客と共に馬上の人となっていました。3人の刺客は北畠家の元家来衆、そういう人物を選ぶところが信長の非道な所業です。一行4人は具教を仕留めますが、この一部始終を天井裏から見ていたものがありました。これが伊賀の忍者・文吾、後の石川五右衛門です。ここまで読むとこの本の主人公は文吾かと思われるのですが、そうではありませんでした。
所変わって伊賀の国、有力な地侍がお互いに牽制しあっていますが、この国を統率できるような強力な力を持った者もおらず、いつも諍いを起こしていました。その地侍の一人が百地三太夫、聞いたことありますよね。
この百地三太夫と下山甲斐という者が諍いを起こし、下山の砦でチャンチャンバラバラやっています。三太夫は下山家の次男・次郎兵衛を切るよう無門という下人に命令します。無門という男は腕は立つのですが、ゼニにならないことは一切しないという変わり者、百貫文で引き受け容易く次郎兵衛を斬り殺します。それに怒ったのが長男の平兵衛、無門と互角に勝負しますが、ここで鐘が鳴り響きます。この鐘は地侍を集めて評定を開くためのもの、鐘が鳴るとどんなに諍っていてもすぐに刀を引き、評定の場=平楽寺へ急がねばなりません。
評定では伊勢の国が織田方に落ちたので、伊賀の国はどうするべきかとの話、結果として織田と闘っても勝ち目は無いと、織田の軍門に下ることになりました。その使者に下山平兵衛を立て、文吾が付いていくことになりますが、平兵衛の腹は煮えくり返っています。途中、文吾に深手を負わせ、平兵衛は信雄に目通りを願い、伊賀を攻めるよう嘆願します。

この平兵衛の伊賀へ対しての裏切りを三太夫は忍法をかけた、下山との諍いも最初から計略であったと明かします。
伊賀を攻めることに意を決した信雄は、伊勢と伊賀の間に丸山城を築くことを決め、その築城のために伊賀者を雇います。伊賀者は毎日ゼニが入るのでせっせと働くのですが、城が出来上がったその日に三太夫は城を焼いてしまいます。
さて城を焼かれた信雄は怒り心頭、伊賀攻めを急ぎますが、一方大金を手にした下人たちは織田と闘ってもゼニは入らんと、伊賀の国から逃げていきます。無門とてもゼニにならない仕事はしたくありません。ここまでは三太夫も計算してなかったらしい。
下人が半減した伊賀の国、怒涛の如く攻め入る織田軍、伊賀一の使い手無門も逃げてしまうのか、ここから以降は作家のためにも明かせません。
面白いですから、買って読んでくださいね。

年末に『のぼうの城』を読みましたが、同じ作者の『忍びの国』という小説が文庫本で発売されました。表紙に『のぼうの城』のようなインパクトがありませんが、前回面白かったのですぐに手に入れたのでした。
天正4年11月、織田信雄(のぶかつ)=信長の次男が、伊勢の国の領主=北畠具教を暗殺するために、3人の刺客と共に馬上の人となっていました。3人の刺客は北畠家の元家来衆、そういう人物を選ぶところが信長の非道な所業です。一行4人は具教を仕留めますが、この一部始終を天井裏から見ていたものがありました。これが伊賀の忍者・文吾、後の石川五右衛門です。ここまで読むとこの本の主人公は文吾かと思われるのですが、そうではありませんでした。
所変わって伊賀の国、有力な地侍がお互いに牽制しあっていますが、この国を統率できるような強力な力を持った者もおらず、いつも諍いを起こしていました。その地侍の一人が百地三太夫、聞いたことありますよね。
この百地三太夫と下山甲斐という者が諍いを起こし、下山の砦でチャンチャンバラバラやっています。三太夫は下山家の次男・次郎兵衛を切るよう無門という下人に命令します。無門という男は腕は立つのですが、ゼニにならないことは一切しないという変わり者、百貫文で引き受け容易く次郎兵衛を斬り殺します。それに怒ったのが長男の平兵衛、無門と互角に勝負しますが、ここで鐘が鳴り響きます。この鐘は地侍を集めて評定を開くためのもの、鐘が鳴るとどんなに諍っていてもすぐに刀を引き、評定の場=平楽寺へ急がねばなりません。
評定では伊勢の国が織田方に落ちたので、伊賀の国はどうするべきかとの話、結果として織田と闘っても勝ち目は無いと、織田の軍門に下ることになりました。その使者に下山平兵衛を立て、文吾が付いていくことになりますが、平兵衛の腹は煮えくり返っています。途中、文吾に深手を負わせ、平兵衛は信雄に目通りを願い、伊賀を攻めるよう嘆願します。

この平兵衛の伊賀へ対しての裏切りを三太夫は忍法をかけた、下山との諍いも最初から計略であったと明かします。
伊賀を攻めることに意を決した信雄は、伊勢と伊賀の間に丸山城を築くことを決め、その築城のために伊賀者を雇います。伊賀者は毎日ゼニが入るのでせっせと働くのですが、城が出来上がったその日に三太夫は城を焼いてしまいます。
さて城を焼かれた信雄は怒り心頭、伊賀攻めを急ぎますが、一方大金を手にした下人たちは織田と闘ってもゼニは入らんと、伊賀の国から逃げていきます。無門とてもゼニにならない仕事はしたくありません。ここまでは三太夫も計算してなかったらしい。
下人が半減した伊賀の国、怒涛の如く攻め入る織田軍、伊賀一の使い手無門も逃げてしまうのか、ここから以降は作家のためにも明かせません。
面白いですから、買って読んでくださいね。





















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます