京都市内を流れる鴨川が、その上流で分岐して高野川と賀茂川に分かれる地点に下鴨神社がある。
鴨川に鴨がいる。

下鴨神社の鳥居の東に「河合神社」がある。なかなか隅に置けない由緒ある神社である。

金ぴかの舞殿を通して本殿が窺える。

その東側の境内に方丈の小屋が再現されている。方丈は一辺が1丈の長さの四角形の小屋を言うが、鴨長明が生活した小屋である。

清貧な生活は、心静かに研ぎ澄まされた処世観が生まれる。

彼は下鴨神社の禰宜の二男だった。7歳の時に神職に付き従5位下に任じられた。26歳の時、平家の福原京にも出向いていたが、やがて都へ戻る。46歳の時宮中で和歌所に活躍したが、50歳で大原へ隠棲する。この時に「方丈記」が生まれた。
58歳にして伏見区日野町に落ち着いたが、それまで全国各地を移り住んでいた。その時に方丈の小屋が完成している。組み立て式でどこにでも移動して建てられる事が出来るのである。

絵馬もできている。

彼は持って生まれた才知を生かし、神官の道を進み、また和歌の道を究め、気軽に平家の遷都で福原まで赴き、再び京に帰って歌道を究め、さらに飽き足らず小庵を結び、世の来し方行く末から、生きる道を達観した。


鴨長明と方丈記、そして、文人たちとの交際が偲ばれます。



鴨川に鴨がいる。

下鴨神社の鳥居の東に「河合神社」がある。なかなか隅に置けない由緒ある神社である。

金ぴかの舞殿を通して本殿が窺える。

その東側の境内に方丈の小屋が再現されている。方丈は一辺が1丈の長さの四角形の小屋を言うが、鴨長明が生活した小屋である。

清貧な生活は、心静かに研ぎ澄まされた処世観が生まれる。

彼は下鴨神社の禰宜の二男だった。7歳の時に神職に付き従5位下に任じられた。26歳の時、平家の福原京にも出向いていたが、やがて都へ戻る。46歳の時宮中で和歌所に活躍したが、50歳で大原へ隠棲する。この時に「方丈記」が生まれた。
58歳にして伏見区日野町に落ち着いたが、それまで全国各地を移り住んでいた。その時に方丈の小屋が完成している。組み立て式でどこにでも移動して建てられる事が出来るのである。

絵馬もできている。

彼は持って生まれた才知を生かし、神官の道を進み、また和歌の道を究め、気軽に平家の遷都で福原まで赴き、再び京に帰って歌道を究め、さらに飽き足らず小庵を結び、世の来し方行く末から、生きる道を達観した。


鴨長明と方丈記、そして、文人たちとの交際が偲ばれます。



















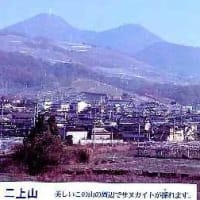
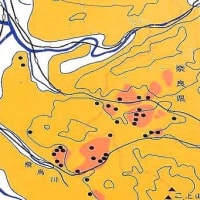


「ゆく河の流れは絶えずして…」というフレーズがこの方でしたか
鴨長明。見せて頂いている資料である程度
記憶をよみがえらせて頂いています。
貴族の世から武士の時代へと移り変わる
激動期に生きたわけですね。そんな中で、
時代に超然として気の向くまま、誘われる
がままに生きたという感じがします。
方丈記という書名も何から来たか。
これでわかりました。
「竹取物語」「枕草子」「平家物語」「徒然草」「奥の細道」も併せて行った中のひとつでした。
『ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。
淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例なし。
世の中にある人と栖(すみか)と、またかくのごとし。・・・』
下鴨神社の河合神社ですか~!
いい付加情報をいただきました。 サンクス!
中質もそうですが、狭い空間で精神統一をする
ということでしょうか。当時から高名だったであろう
鴨長明がこんな小屋で暮らしてたとは、驚きですね。
下鴨神社の河合神社も素晴らしいですね。
源平の移り変わりを目の当たりに見て、世の流れを冷徹な目で見る彼は、現代でも通用しそうですね。
皆さんの発表会聞いてみたいですね。
それに、気侭な奔放な生活では、「食う寝るところに住むところ…」それを自分の意のままに組み立てるのにはちょうどいいかも知れません。