その後、当初の予定通りリハビリテーション科の後期研修をはじめました。
リハビリテーション科では障害の見方とか、車いすで地域で暮らす人たちの会とか参加させてもらったり、ずいぶんいろいろ教えられました。機能障害が治る状態ではないけれども少しでもいいADL、そしてQOLを目指して当事者と協力しながら当事者の生活を支えるなんて、これは、まさに医療の役目だなと。
そんな研修をおこないながら川上村の診療所に週1回いかせてもらったり、在宅の訪問診療をさせてもらったり、総合外来や救急外来にもでて充実していました・・・。
そのうちに同僚がローテーション研修にでたためリハビリテーション科は上司と二人きりなりました。
医師になって4年目のころ、診療報酬が改訂により療養型病床を回復期リハビリテーション病棟に転換しなければ病院としても大赤字になるという話しになりました。
専従医が必要とのことで、だれも他にやれる人がいなかったので訪問診療や診療所、精神科や内科でのローテート研修をあきらめ、専従医として手をあげました。
病棟の立ち上げのメンバーで、いくつかの回復期リハ病棟に見学に行き、その後も個人的にもいくつかの回復期リハ病棟を見学に行きました。みんなで病院の出口のエンジンで農村型の総合病院でのリハモデルを確立するんだと張り切っていました。
当時、多職種のカンファレンスは行われるようになっていたものの、リハ出しとか、下ろすとかいうことばで動線の悪い病棟で数少ないエレベーターをまちながら手間ひまかけて訓練室への送迎をするけど実際に訓練になるのはわずかな時間になったり、リハのスタッフは病棟担当にはなっておらず、カルテもリハだけ別になっていて、病棟のスタッフと情報共有はできておらず、ケースワーカーは医療相談室、リハビリのスタッフはリハ室、病棟は病棟に、医師は医局にというタコつぼに引きこもっている状態でした。
その状態の改善は後期研修医が主張しても「そうだね。」と聞き流されるくらいで変わるものでもありませんでした。
上司にしてもも、リハビリのスタッフが起立歩行の量の確保よりもプラットフォームの上でのファシリテーションを重視するのを快く思わないながらも「それを指摘すれば自分がやめなければならない。」とスタッフと積極的にディスカッションすること無く及び腰でした。
回復期リハビリテーション病棟はリハが中心の人を多くの職種が張り付き共働してADLの向上と自宅復帰を目指す専門病棟にあつめて実績を示して、多職種協働というやり方を病院全体に示すのが役割だと思っていました。
そのためには病院全体の勉強会をしたり、情報共有のためにリハの電子カルテやシステムを検討したり、結局予算もなかったのでデーターベース更新で小額の予算をとりシステム科とともにデーターベースをサーバー上に置く電子システムを作ったりしました。
夜な夜な開発に熱中し、おかげでファイルメーカーはだいたい使いこなせるようになりました。(小さな病院の電子カルテシステムくらいなら作れるくらい。)
アリバイ的な書類をつくるのにエネルギーを注ぐならそういうのをササッとすませられる仕組みをつくって、大事なことにエネルギーを注ぐベキだと思います。そのために開発に力を注ぐのは間違ってはいないのでしょううが・・。
院内のサブシステムをファイルメーカーで作るのは優れた方法だと思っていますが・・・。
(鹿教湯病院などはそれでやっている。)
しかし本来の仕事を差し置いて、おそらくやりすぎてしまったんでしょうね。
情報共有がすすむと仕事が奪われると感じたのでしょうか?上司の心証は複雑なものがあったのだとおもいます。
リハビリテーション科では障害の見方とか、車いすで地域で暮らす人たちの会とか参加させてもらったり、ずいぶんいろいろ教えられました。機能障害が治る状態ではないけれども少しでもいいADL、そしてQOLを目指して当事者と協力しながら当事者の生活を支えるなんて、これは、まさに医療の役目だなと。
そんな研修をおこないながら川上村の診療所に週1回いかせてもらったり、在宅の訪問診療をさせてもらったり、総合外来や救急外来にもでて充実していました・・・。
そのうちに同僚がローテーション研修にでたためリハビリテーション科は上司と二人きりなりました。
医師になって4年目のころ、診療報酬が改訂により療養型病床を回復期リハビリテーション病棟に転換しなければ病院としても大赤字になるという話しになりました。
専従医が必要とのことで、だれも他にやれる人がいなかったので訪問診療や診療所、精神科や内科でのローテート研修をあきらめ、専従医として手をあげました。
病棟の立ち上げのメンバーで、いくつかの回復期リハ病棟に見学に行き、その後も個人的にもいくつかの回復期リハ病棟を見学に行きました。みんなで病院の出口のエンジンで農村型の総合病院でのリハモデルを確立するんだと張り切っていました。
当時、多職種のカンファレンスは行われるようになっていたものの、リハ出しとか、下ろすとかいうことばで動線の悪い病棟で数少ないエレベーターをまちながら手間ひまかけて訓練室への送迎をするけど実際に訓練になるのはわずかな時間になったり、リハのスタッフは病棟担当にはなっておらず、カルテもリハだけ別になっていて、病棟のスタッフと情報共有はできておらず、ケースワーカーは医療相談室、リハビリのスタッフはリハ室、病棟は病棟に、医師は医局にというタコつぼに引きこもっている状態でした。
その状態の改善は後期研修医が主張しても「そうだね。」と聞き流されるくらいで変わるものでもありませんでした。
上司にしてもも、リハビリのスタッフが起立歩行の量の確保よりもプラットフォームの上でのファシリテーションを重視するのを快く思わないながらも「それを指摘すれば自分がやめなければならない。」とスタッフと積極的にディスカッションすること無く及び腰でした。
回復期リハビリテーション病棟はリハが中心の人を多くの職種が張り付き共働してADLの向上と自宅復帰を目指す専門病棟にあつめて実績を示して、多職種協働というやり方を病院全体に示すのが役割だと思っていました。
そのためには病院全体の勉強会をしたり、情報共有のためにリハの電子カルテやシステムを検討したり、結局予算もなかったのでデーターベース更新で小額の予算をとりシステム科とともにデーターベースをサーバー上に置く電子システムを作ったりしました。
夜な夜な開発に熱中し、おかげでファイルメーカーはだいたい使いこなせるようになりました。(小さな病院の電子カルテシステムくらいなら作れるくらい。)
アリバイ的な書類をつくるのにエネルギーを注ぐならそういうのをササッとすませられる仕組みをつくって、大事なことにエネルギーを注ぐベキだと思います。そのために開発に力を注ぐのは間違ってはいないのでしょううが・・。
院内のサブシステムをファイルメーカーで作るのは優れた方法だと思っていますが・・・。
(鹿教湯病院などはそれでやっている。)
しかし本来の仕事を差し置いて、おそらくやりすぎてしまったんでしょうね。
情報共有がすすむと仕事が奪われると感じたのでしょうか?上司の心証は複雑なものがあったのだとおもいます。










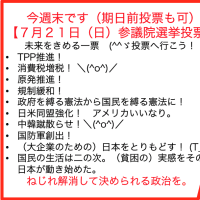
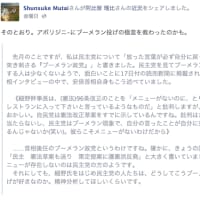




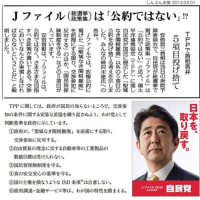

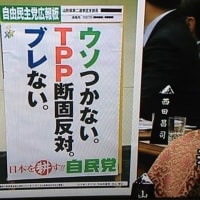

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます