前回長蛇の列にたじろぎ、“登城”をあきらめた彦根城天守。
GWのピークも過ぎたとあって、ゆっくりと“登城”できました。

早速中へ。


この梁の巧みな使い方。
ここ彦根城は近江の名族京極高次が築いた大津城からの天守を始め、佐和山城から佐和口多門櫓(非現存)と太鼓櫓門、小谷城から西ノ丸三重櫓、観音寺城からや、どこのものかは不明とされているが太鼓門、などの移築伝承が多くある。要するにコスト削減と工期短縮が狙いだったようです。
内部は外観からは想像できないほど広いです。

この天守閣、城によく見られる通し柱が有りません。
それゆえに、これだけの広さが確保できたのかと....。

これ、なんでしょう?
千鳥破風に設けられた、隠狭間の入り口。
さすがにこの中までは見られませんでしたが、BS朝日の番組“三津五郎....”では
中に入ってました。
うらやまし~。
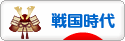
GWのピークも過ぎたとあって、ゆっくりと“登城”できました。

早速中へ。


この梁の巧みな使い方。
ここ彦根城は近江の名族京極高次が築いた大津城からの天守を始め、佐和山城から佐和口多門櫓(非現存)と太鼓櫓門、小谷城から西ノ丸三重櫓、観音寺城からや、どこのものかは不明とされているが太鼓門、などの移築伝承が多くある。要するにコスト削減と工期短縮が狙いだったようです。
内部は外観からは想像できないほど広いです。

この天守閣、城によく見られる通し柱が有りません。
それゆえに、これだけの広さが確保できたのかと....。

これ、なんでしょう?
千鳥破風に設けられた、隠狭間の入り口。
さすがにこの中までは見られませんでしたが、BS朝日の番組“三津五郎....”では
中に入ってました。
うらやまし~。














 だった天気も、次第に
だった天気も、次第に へ
へ












 お手製のお弁当を持って、“たけべの森公園”へ行ってきました。
お手製のお弁当を持って、“たけべの森公園”へ行ってきました。


















 を持ってのお出かけでした。
を持ってのお出かけでした。







