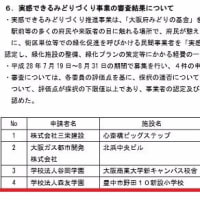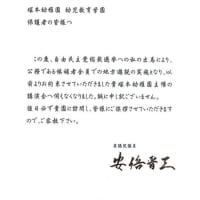前回投稿で“通貨論争“の中、1841年から首相になった当時の有力政治家ロバート・ピールは通貨学派の影響を受け1844年にイギリス金融史上有名な“1844年イングランド銀行条例“を提案します。議会の開会に当たってピールは自らが留保無しで通貨主義を採用した事を言明したとされます(フイーヴィヤー)。
ピールの提案に当たっての議会演説はその趣旨を良く表していますが1844年5月20日のその内容は
“方策の目的は(立法が防止し得る限りにおいて)1825、1836、1839年に我々が蒙った災害の再発を防止するにある。およそ激しい発作はこれを激発させて、それからその回復手段として絶望的な治療法に訴えるより、その発作を予防するほうがよいのである“(前掲渡辺の引用)
と提案し、議会では反対は少数で7月19日には法律となった。ではその1844年銀行法とはどういう内容であったか?
周知のように、全29条からなるこの法律は大きく言って二つの内容が有ったとされます(法律の条文全文は修正条項である29条を除き前掲フラートン岩波版に載っています)。
一つはイングランド銀行自体を二つの部分に分割し“発行部“と“銀行部“にわけ、発券行為は発行部のみが出来るものとし、最初に発行部が銀行部から1400万ポンドの証券と、銀行部が必要としない鋳貨、地金を引継ぎその代わりに銀行部にその資産価値に等しい量の銀行券を渡すとするもので、結果的に1400万ポンド分だけの“保証準備発行“を認め、残りは金属準備無しには発行出来ないとするもので、金属のイングランド銀行への流出入に併せて銀行券の制御を図ろうとするものと言えます。
二つ目としては地方銀行等の発券を制限し暫時的にその発券を減らして行こうとするものとされます。
上記で明らかなように今まで発券と金属準備の関係が規定されていなかった事を明確に金属準備との関係を規定したものであり、只ここで1400万ポンドについてだけは保証準備を認めたとする事により完全には“通貨主義“の立場に立ったものではないとの議論も有りますが、金属準備に併せて銀行券の量を調節しようとしている事から見れば明らかに通貨主義の主張に合わせた物と言えるのではないでしょうか。
この法律に対しJ.S.ミルが危惧しパーマーからもピールに伝えられたとされます。
最新の画像[もっと見る]
「景気政策史」カテゴリの最新記事
 景気政策史―60 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その16 “大不況”と商工業...
景気政策史―60 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その16 “大不況”と商工業... 景気政策史―59 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 “自由貿易”と砲艦...
景気政策史―59 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 “自由貿易”と砲艦... 景気政策史―58 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 英仏通商条約と...
景気政策史―58 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その15 英仏通商条約と... 景気政策史―57 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その14 後発国の自由と...
景気政策史―57 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その14 後発国の自由と... 景気政策史―56 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その13 後発国の自由と...
景気政策史―56 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その13 後発国の自由と... 景気政策史―55 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その12 関税改革及び穀...
景気政策史―55 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その12 関税改革及び穀... 景気政策史ー54 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その11反穀物法同盟...
景気政策史ー54 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その11反穀物法同盟... 景気政策史ー53 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その10穀物法、通貨、...
景気政策史ー53 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その10穀物法、通貨、... 景気政策史ー52 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その9穀物法、通貨、不況
景気政策史ー52 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その9穀物法、通貨、不況 景気政策史ー51 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その8自由貿易と機械輸出
景気政策史ー51 19世紀イギリス対外商業政策と不況 その8自由貿易と機械輸出