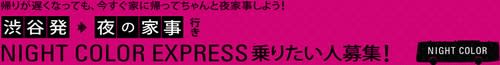東京新聞に「免許返納・破綻… ラジオ苦境」という記事が上がっている。
名古屋の「愛知国際放送(RADIO-i)」が九月末で放送を停止し総務省に免許を返納する見通しだという。
関西ではKiss-FMが既に破綻、10月1日付けで別法人(といっても受け皿会社のようだ)に事業譲渡をして、存続をめざす。「九州国際エフエム」(福岡市)も地元企業と事業譲渡の交渉中だ、と記事は続ける。
ちなみに、愛知国際放送と九州国際エフエムはInterFM(東京:日経新聞系列)とFM COCOLO(大阪:地元資本)とともにMegalopolis Radio Network(メガロポリス・レディオ・ネットワーク)というラジオネットワークを構成していた。
FMラジオ局って、コンパクトに運営が出来るラジオ局であるはず。地元に根ざした情報とその土地の風景になるような音楽で構成すれば、メディアとしての価値はそれなりに、認められると思うのだけれど。
なんとなく東京のテレビキー局のようなイメージを持って運営していたとすれば、それは、大間違いなんだろうな。価値あるコンテンツさえ作ることが出来れば、流通経路はどこにでもあるのに。
こうやって、コンテンツはあるのに流すメディアの変化に対応できなくて潰れていく会社がしばらく増えていくのだろうと感じています。
「ソーシャルメディアとシンジケーション」
このあたりに新しいメディア環境が出現するように思います。
そういえば、明日東京中央区の中堅広告代理店が潰れるという話がtwitterで激流状態ですが、それほど遠くない未来を見据えて対応することが、メディアや広告にかかわる人たちががんばれるフィールドのように思います。
名古屋の「愛知国際放送(RADIO-i)」が九月末で放送を停止し総務省に免許を返納する見通しだという。
関西ではKiss-FMが既に破綻、10月1日付けで別法人(といっても受け皿会社のようだ)に事業譲渡をして、存続をめざす。「九州国際エフエム」(福岡市)も地元企業と事業譲渡の交渉中だ、と記事は続ける。
ちなみに、愛知国際放送と九州国際エフエムはInterFM(東京:日経新聞系列)とFM COCOLO(大阪:地元資本)とともにMegalopolis Radio Network(メガロポリス・レディオ・ネットワーク)というラジオネットワークを構成していた。
FMラジオ局って、コンパクトに運営が出来るラジオ局であるはず。地元に根ざした情報とその土地の風景になるような音楽で構成すれば、メディアとしての価値はそれなりに、認められると思うのだけれど。
なんとなく東京のテレビキー局のようなイメージを持って運営していたとすれば、それは、大間違いなんだろうな。価値あるコンテンツさえ作ることが出来れば、流通経路はどこにでもあるのに。
こうやって、コンテンツはあるのに流すメディアの変化に対応できなくて潰れていく会社がしばらく増えていくのだろうと感じています。
「ソーシャルメディアとシンジケーション」
このあたりに新しいメディア環境が出現するように思います。
そういえば、明日東京中央区の中堅広告代理店が潰れるという話がtwitterで激流状態ですが、それほど遠くない未来を見据えて対応することが、メディアや広告にかかわる人たちががんばれるフィールドのように思います。











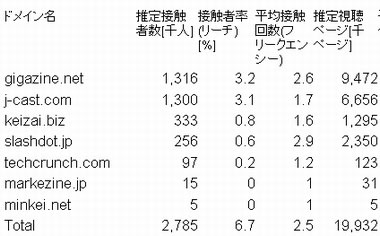

 ブブゼラー♪
ブブゼラー♪