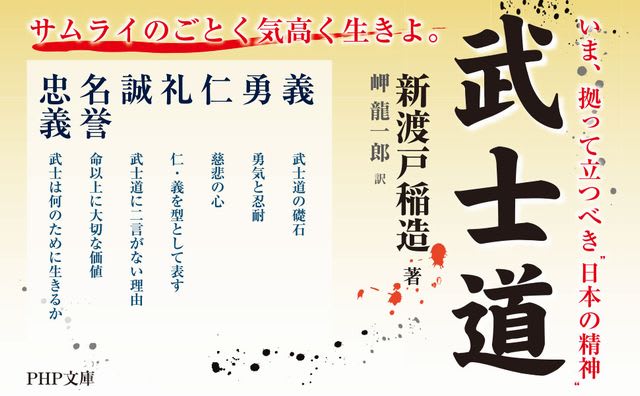🌸生物はなぜ死ぬのか2(生物の多様性のメカニズム)
⛳細菌が持つ多様性の仕組み
☆細菌は、地球上にもっともたくさん古くから存在する生き物
☆細菌には、有性生殖に似た遺伝子をシャツフルして
⛳細菌が持つ多様性の仕組み
☆細菌は、地球上にもっともたくさん古くから存在する生き物
☆細菌には、有性生殖に似た遺伝子をシャツフルして
*多様性を創出する機構がある
☆大腸菌には、染色体とは別にF因子というDNAが存在する
☆大腸菌には、染色体とは別にF因子というDNAが存在する
*F因子は、時おり染色体の中に組み込まれている
☆DNAの1本鎖の切断すると、DNAの複製が開始される
*F因子は接合繊毛の細胞同士を繋ぐ構造体の遺伝子を持っている
*F因子は接合繊毛の細胞同士を繋ぐ構造体の遺伝子を持っている
*F因子により、他の菌と繋がる
☆F因子からのDNA複製によるコピー
☆繊毛を伝ってF因子を持たない菌に移動する
*移動先の菌の中で、相同組換えにより
*同じ領域間で入れ替わりが起こり、遺伝情報が移動する
☆F因子による遺伝情報の交換は、性分化のもっとも初期のタイプ
☆生き物は、あの手この手で多様性(変化)を生み出そうとしている
⛳子供のほうが親より「優秀」な理由
☆性による多様性の獲得と死ななければいけない理由の関係
*生物の成り立ちは「変化と選択」による進化の賜物である
☆性に関して
☆F因子による遺伝情報の交換は、性分化のもっとも初期のタイプ
☆生き物は、あの手この手で多様性(変化)を生み出そうとしている
⛳子供のほうが親より「優秀」な理由
☆性による多様性の獲得と死ななければいけない理由の関係
*生物の成り立ちは「変化と選択」による進化の賜物である
☆性に関して
*卵・精子・胞子などの配偶子の形成
*それが、接合や受精が「変化」を生み出す
☆「選択」は、有性生殖の結果生み出される、多様な子孫に起こる
*子孫だけではなく、選択される対象は、生み出した「親」も含まれる
☆「選択」は、有性生殖の結果生み出される、多様な子孫に起こる
*子孫だけではなく、選択される対象は、生み出した「親」も含まれる
*親は、死ぬという選択によってより一族の変化を加速する
☆子供のほうが親よりも多様性に満ちており
☆子供のほうが親よりも多様性に満ちており
*生物界においてはより価値がある
*生き残る可能性が高い「優秀な」存在
☆親は死んで、子供の生き残りが、種を維持する戦略として正しい
*生物はそのような多様性重視のコンセプトで生き抜いてきた
⛳多様性の実現に重要なコミュニティによる教育
☆子孫を残したら、親はとっとと死んだほうがいい
*親は進化の過程で、子より早く死ぬべくプログラムされている
⛳多様性の実現に重要なコミュニティによる教育
☆子孫を残したら、親はとっとと死んだほうがいい
*親は進化の過程で、子より早く死ぬべくプログラムされている
☆そのような生き物はたくさんいる
*サケ・昆虫などの多くの小動物
*子孫に命をバトンタッチして死んでいく
☆ヒトのような、子供を産みっばなしにできない生き物の親
☆ヒトのような、子供を産みっばなしにできない生き物の親
*自分たちよりも優秀な子孫が独り立ちできるようになるまで
*世話をする必要があり、子育ては、遺伝的多様性と同程度に重要です
☆ヒトのような高度な社会を持つ生き物は
☆ヒトのような高度な社会を持つ生き物は
*子育てに加えて社会の中で生き残るための教育が必要
*親は元気に長生きしないとけない
*親・祖父母や社会(コミュニティ)も教育、子育てに関わる
☆大型の哺乳類は成長して自活するまで、親やコミュニテイの保護が必要
*重要となのは、親の存在のみならず「子育て(教育)の質」です
⛳まとめ
☆生物は、常に多様性を生み出すことで生き残ってきた
☆有性生殖はそのための手段として有効
☆親は子孫より多様性の点で劣っているので
*子より先に死ぬようにプログラムされている
*死ぬ時期は生物種によって異なる
☆大型の哺乳動物は大人になるまで時間がかかるため
*その間、親の長期の保護が必要となる
*親やコミュニテイが自ら見本を見せることです
*親の世代も含めた社会全体で多様性(個性)を認め合うことが大切
☆子供の個性の実現を見て、親はその使命を終えることができる
☆大型哺乳動物(例ゾウ等)
☆大型哺乳動物(例ゾウ等)
*子は生きる知恵を、親を含めた集団(コミュニティ)から学ぶ
☆生物学の死の意味から考えると
☆生物学の死の意味から考えると
*ヒトの場合、親や学校なども含めたコミュニテイ
*子供に何を教えるべきか自ずと見えてくる
☆親が、必要最小限の生きていくための知恵と技術を伝えるのは当然だ
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典『生物はなぜ死ぬ』
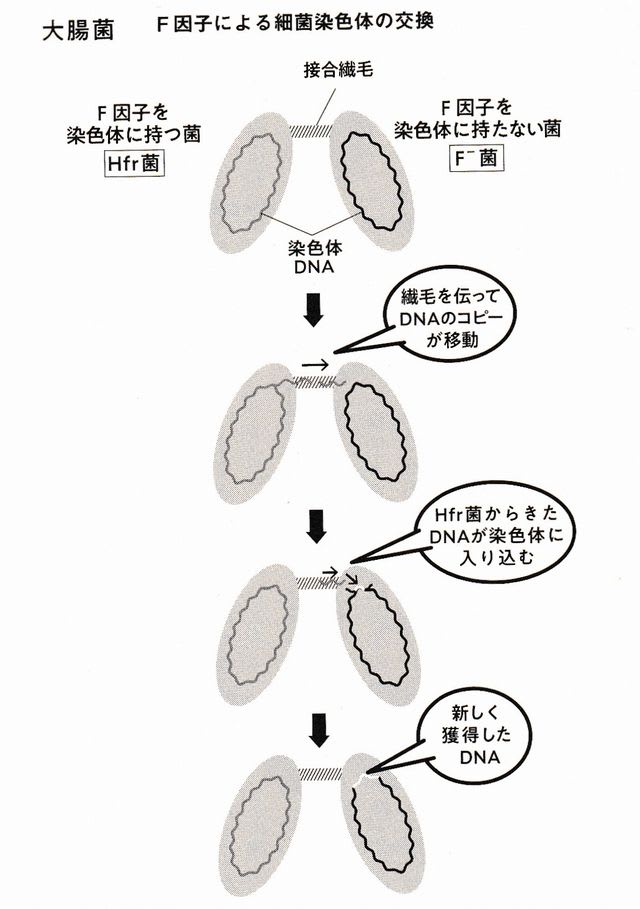
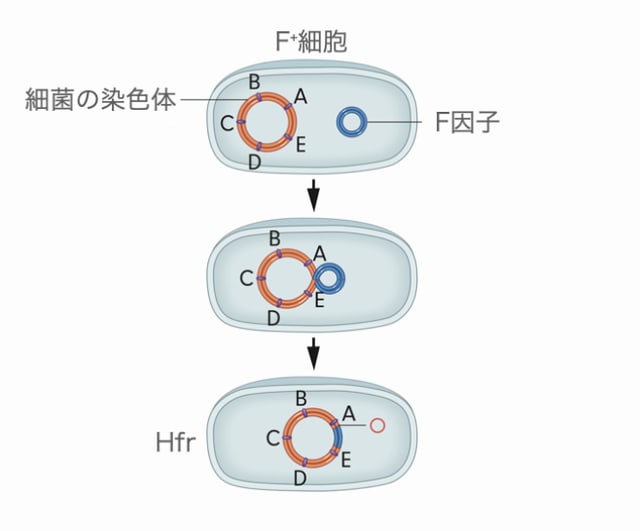

生物はなぜ死ぬのか2(生物の多様化のメカニズム)
(『生物はなぜ死ぬ』記事、ネットより画像引用)