明治8年(1875年)の今日、京都に島津製作所が誕生した。
創業者の島津源蔵は、もとは家業の仏具屋を継いでいたが、京都舎密(化学)局が開設されたことが大きな契機になった。
舎密局の校長は、明石博高(ひろあきら)であったが、明石は、舎密局が単なる学問の場になるだけでなく、地場産業振興をも目的にした。
そのせいもあり、門戸は広く解放され、源蔵は舎密局に足繁く通うようになった。
このとき、既に来日していたドイツ人学者ゴッドフリード・ワグネルが招かれた。
ワグネルは、七宝焼きや有田焼など日本の伝統工芸の発展にも尽力したのであるが、源蔵には足踏み式の旋盤などを贈り、使い方を指導した。
これが、島津製作所の創立に繋がっていく。
幕末、長崎に海軍伝習所ができたが、その際、教師陣の中にオランダの若き軍医ポンペの姿も見られた。
ポンペは医学を教授したが、彼は、医学は広範囲な学問に繋がるもの、として物理学や化学なども必修科目に加え、自ら講義した。
彼は、教科書を使わなかったが、授業の際に毎回、手製のメモを用意した。
そのメモの底本となったのが、ワグネルの著書であったと言われる。
2002年、島津製作所の社員である田中耕一氏がノーベル化学賞をとって話題となった。
島津製作所なくしては、田中氏もあり得ず、ワグネルなくしては、島津製作所もなかったかもしれない。
ワグネルは、その後、東京大学や東京工業大学で教鞭をとることになる。多くの外国人教師が、任期を終え母国に帰国していったのに対し、ワグネルは、37歳で来日し、61歳で没する24年の間、日本に滞在し続けた。墓地は青山霊園にある。
ワグネルは、今日ではあまり知名度がないが、明治以来、綿々と繋がっている化学の脈流の真ん中にどっかりと腰を降ろしていることには変わりない。
足踏み式旋盤については、こちらを(展示室のご案内→第一展示室の順にクリック)
参考文献
日本の化学の開拓者たち (裳華堂) 芝哲夫
↓よろしかったらクリックお願いします。

創業者の島津源蔵は、もとは家業の仏具屋を継いでいたが、京都舎密(化学)局が開設されたことが大きな契機になった。
舎密局の校長は、明石博高(ひろあきら)であったが、明石は、舎密局が単なる学問の場になるだけでなく、地場産業振興をも目的にした。
そのせいもあり、門戸は広く解放され、源蔵は舎密局に足繁く通うようになった。
このとき、既に来日していたドイツ人学者ゴッドフリード・ワグネルが招かれた。
ワグネルは、七宝焼きや有田焼など日本の伝統工芸の発展にも尽力したのであるが、源蔵には足踏み式の旋盤などを贈り、使い方を指導した。
これが、島津製作所の創立に繋がっていく。
幕末、長崎に海軍伝習所ができたが、その際、教師陣の中にオランダの若き軍医ポンペの姿も見られた。
ポンペは医学を教授したが、彼は、医学は広範囲な学問に繋がるもの、として物理学や化学なども必修科目に加え、自ら講義した。
彼は、教科書を使わなかったが、授業の際に毎回、手製のメモを用意した。
そのメモの底本となったのが、ワグネルの著書であったと言われる。
2002年、島津製作所の社員である田中耕一氏がノーベル化学賞をとって話題となった。
島津製作所なくしては、田中氏もあり得ず、ワグネルなくしては、島津製作所もなかったかもしれない。
ワグネルは、その後、東京大学や東京工業大学で教鞭をとることになる。多くの外国人教師が、任期を終え母国に帰国していったのに対し、ワグネルは、37歳で来日し、61歳で没する24年の間、日本に滞在し続けた。墓地は青山霊園にある。
ワグネルは、今日ではあまり知名度がないが、明治以来、綿々と繋がっている化学の脈流の真ん中にどっかりと腰を降ろしていることには変わりない。
足踏み式旋盤については、こちらを(展示室のご案内→第一展示室の順にクリック)
参考文献
日本の化学の開拓者たち (裳華堂) 芝哲夫
↓よろしかったらクリックお願いします。












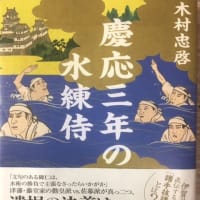
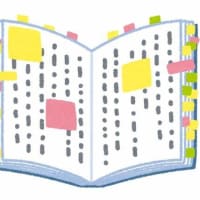
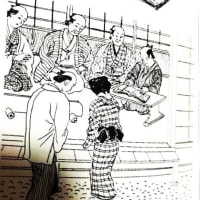
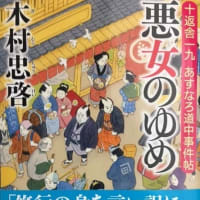
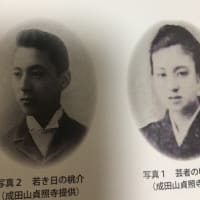

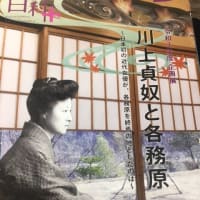
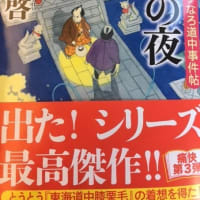
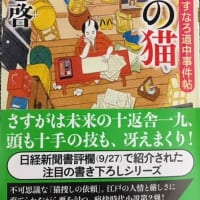




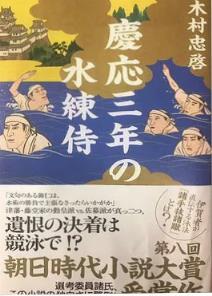

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます