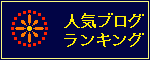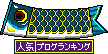江戸初期、文化の中心は上方であった。
文化後進国である江戸においても、四代将軍・家綱の明暦年間(一六五五~一六五八年)になってくると出版業が企業として成り立つようになる。
その頃はまだ京都資本系が圧倒的に優位であったが、後に江戸資本の版元も力を付け、上方系資本に対抗するようになった。
江戸の版元は、自らの利益確保のために、書物問屋と地本問屋という組織を結成。時代の流れと、企業努力もあり、元禄年間位から江戸系と上方系の実力は拮抗し始め、宝暦年間(一七五一~一七六四年)には、江戸系が上方系を凌駕していった。
前出の書物問屋とは、儒学書、歴史書、医学書など固い関係の本を扱う版元で、地本問屋とは草双紙のように江戸の地で出版された地本を扱う本屋である。
有名な地本問屋としては、鶴屋喜右衛門、鱗形屋孫兵衛、山本九左衛門などがいる。
須原屋市兵衛(「解体新書」「海国兵談」などを出版し、幕府から睨まれた)のように書物問屋として有名ながら、地本問屋の仲間組織に入っている者もいた。
江戸の地本問屋として現代、もっとも名が知られているのは、蔦屋重三郎であろう(蔦屋も後に書物問屋に加盟)。
レンタルショップのTUTAYAが名前の由来とした蔦屋重三郎は、寛延三年(一七五〇年)一月七日、吉原に生まれた。本名・柯理{からまる}。七歳のときに両親が離縁し、蔦屋を経営する喜多川氏に養子に行く。その頃の蔦屋は茶屋を営んでいたというが、はっきりしない。ともあれ、安永二年(一七七三年)に重三郎は吉原大門のすぐ近くで吉原のガイドブックである「吉原細見」の卸し・小売を始める。
「吉原細見」の版元は鱗形屋であり、蔦屋は鱗形屋の直営店の扱いであったが、わずか数年後の安永四年、鱗形屋が今でいう著作権問題で大打撃を受けた隙に乗じて、「吉原細見」を発行。それ以降は、鱗形屋版吉原細見と蔦屋版吉原細見が並行出版されていたが、鱗形屋が衰退し出版業界から退場していったのに従い、吉原細見だけでなく、鱗形屋の専属作家であった恋川春町などを抱えるようになった。
天明三年(一七八三年)九月、蔦屋は一流の版元が名を連ねる日本橋通油町に進出。
蔦屋に関わり深い作家としては、先ほどの恋川春町に加え、朋誠堂喜三二、山東京伝、唐来三和、十返舎一九、滝沢馬琴、絵師としては喜多川歌麿、写楽などがいる。
重三郎は、田沼時代に蔦重サロンといってもよい独自のネットワークを形成し、江戸の名プロデューサーとして名高いが、ミスも目立つ。
もっとも大きい事件は、黄表紙から引退したいと言っている山東京伝を無理やり口説いて新作を発表し、寛政の改革の筆禍に引っ掛ったことである。そのほかにも写楽の登用から蜜月関係にあった歌麿との仲に亀裂が入った挙句、鳴りもの入りの写楽もフェイドアウトしていった点、葛飾北斎の才能を開花させらなかった点などが挙げられる。
それでも重三郎に対しては称賛の声が聞こえるばかりで、非難の声は聞こえてこない。
普通の人間ならすっかり自信を失ってしまうような場面でも、重三郎は前向きである。
重三郎の軌跡を見ていると、常に何か新しいことをやらねば済まない、といった気質が見てとれる。
現状維持では、後退。前進することによってのみ、今の地位が保たれるといった心情があったに違いない。
逆境ですら変化は好ましいと思っていたのかも知れない。
過去の栄光に拘泥することなく、未来を見つめる姿。重三郎の眼の先には何が見えていたのだろう。
寛政八年五月六日朝、病の床で死期を悟った重三郎は死後の家事や妻への最期のあいさつを済ませ、昼に自分は死ぬだろうと予言。
しかし、昼を過ぎても死ななかった重三郎は「命の幕引きを告げる拍子木がまだ鳴らない」と笑ったと言われる。
少しの時間差はあったものの、その日の夕刻に死す。享年四十八歳だった。
参考
蔦屋重三郎 (講談社学術文庫) 松木寛
東京人 2007年11月号
↓ よろしかったら、クリックお願いします。
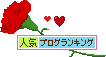
人気ブログランキングへ

にほんブログ村
匠堂本舗

文化後進国である江戸においても、四代将軍・家綱の明暦年間(一六五五~一六五八年)になってくると出版業が企業として成り立つようになる。
その頃はまだ京都資本系が圧倒的に優位であったが、後に江戸資本の版元も力を付け、上方系資本に対抗するようになった。
江戸の版元は、自らの利益確保のために、書物問屋と地本問屋という組織を結成。時代の流れと、企業努力もあり、元禄年間位から江戸系と上方系の実力は拮抗し始め、宝暦年間(一七五一~一七六四年)には、江戸系が上方系を凌駕していった。
前出の書物問屋とは、儒学書、歴史書、医学書など固い関係の本を扱う版元で、地本問屋とは草双紙のように江戸の地で出版された地本を扱う本屋である。
有名な地本問屋としては、鶴屋喜右衛門、鱗形屋孫兵衛、山本九左衛門などがいる。
須原屋市兵衛(「解体新書」「海国兵談」などを出版し、幕府から睨まれた)のように書物問屋として有名ながら、地本問屋の仲間組織に入っている者もいた。
江戸の地本問屋として現代、もっとも名が知られているのは、蔦屋重三郎であろう(蔦屋も後に書物問屋に加盟)。
レンタルショップのTUTAYAが名前の由来とした蔦屋重三郎は、寛延三年(一七五〇年)一月七日、吉原に生まれた。本名・柯理{からまる}。七歳のときに両親が離縁し、蔦屋を経営する喜多川氏に養子に行く。その頃の蔦屋は茶屋を営んでいたというが、はっきりしない。ともあれ、安永二年(一七七三年)に重三郎は吉原大門のすぐ近くで吉原のガイドブックである「吉原細見」の卸し・小売を始める。
「吉原細見」の版元は鱗形屋であり、蔦屋は鱗形屋の直営店の扱いであったが、わずか数年後の安永四年、鱗形屋が今でいう著作権問題で大打撃を受けた隙に乗じて、「吉原細見」を発行。それ以降は、鱗形屋版吉原細見と蔦屋版吉原細見が並行出版されていたが、鱗形屋が衰退し出版業界から退場していったのに従い、吉原細見だけでなく、鱗形屋の専属作家であった恋川春町などを抱えるようになった。
天明三年(一七八三年)九月、蔦屋は一流の版元が名を連ねる日本橋通油町に進出。
蔦屋に関わり深い作家としては、先ほどの恋川春町に加え、朋誠堂喜三二、山東京伝、唐来三和、十返舎一九、滝沢馬琴、絵師としては喜多川歌麿、写楽などがいる。
重三郎は、田沼時代に蔦重サロンといってもよい独自のネットワークを形成し、江戸の名プロデューサーとして名高いが、ミスも目立つ。
もっとも大きい事件は、黄表紙から引退したいと言っている山東京伝を無理やり口説いて新作を発表し、寛政の改革の筆禍に引っ掛ったことである。そのほかにも写楽の登用から蜜月関係にあった歌麿との仲に亀裂が入った挙句、鳴りもの入りの写楽もフェイドアウトしていった点、葛飾北斎の才能を開花させらなかった点などが挙げられる。
それでも重三郎に対しては称賛の声が聞こえるばかりで、非難の声は聞こえてこない。
普通の人間ならすっかり自信を失ってしまうような場面でも、重三郎は前向きである。
重三郎の軌跡を見ていると、常に何か新しいことをやらねば済まない、といった気質が見てとれる。
現状維持では、後退。前進することによってのみ、今の地位が保たれるといった心情があったに違いない。
逆境ですら変化は好ましいと思っていたのかも知れない。
過去の栄光に拘泥することなく、未来を見つめる姿。重三郎の眼の先には何が見えていたのだろう。
寛政八年五月六日朝、病の床で死期を悟った重三郎は死後の家事や妻への最期のあいさつを済ませ、昼に自分は死ぬだろうと予言。
しかし、昼を過ぎても死ななかった重三郎は「命の幕引きを告げる拍子木がまだ鳴らない」と笑ったと言われる。
少しの時間差はあったものの、その日の夕刻に死す。享年四十八歳だった。
参考
蔦屋重三郎 (講談社学術文庫) 松木寛
東京人 2007年11月号
↓ よろしかったら、クリックお願いします。
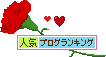
人気ブログランキングへ
にほんブログ村
匠堂本舗