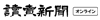「事情聞かず誤認」「教育長への指導は越権行為」…第三者委、斎藤知事の行為を詳細に分析・正当性否定(読売新聞) - goo ニュース
兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、19日に調査報告書を公表した県の第三者委員会は、斎藤氏の行為がパワハラに該当するかを詳細に分析して10件を認定し、正当性を訴える斎藤氏の主張を否定した。どのような判断に基づいて結論を出したのか。
■10件認定
2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、パワハラについて▽優越的な関係を背景とした言動▽業務上必要かつ相当な範囲を超えている▽労働者の就業環境が害される――と定義。厚生労働省の指針では、パワハラに該当する行為を「精神的な攻撃」「過大な要求」など6類型に分類している。
元裁判官ら6人の弁護士で構成する第三者委は、この法律や指針を踏まえた上で、前県西播磨県民局長(昨年7月に死亡)の告発文書などで指摘された斎藤氏の16件の行為について、パワハラに該当するかを検討し、うち10件を認定した。
(中略)
■「司法が判断」疑問
斎藤氏の言動を巡っては、県議会百条委員会も4日に公表した調査報告書で、一部の行為を「パワハラ行為と言っても過言ではない」と指摘していた。
斎藤氏は翌日の記者会見で、「ハラスメントは、最終的には司法の場で判断されるのが一般的」と主張。しかし、実際には、企業や自治体の多くが裁判とは無関係に、厚労省の指針などを参考に社員や職員のパワハラを認定している。兵庫県もパワハラを理由に職員を懲戒処分にしたケースがある。
元大阪高裁判事で、第三者委委員長の藤本久俊弁護士は19日の記者会見で、「裁判に訴えられた件だけがパワハラ(と認定される)ということは、違うのではないか」と述べ、斎藤氏の主張に疑問を呈した。
繰り返す恐れも
労災問題に詳しい上出恭子弁護士(大阪弁護士会)の話「第三者委は中立的な立場の弁護士が様々な事実を照らし合わせて判断しており、パワハラが認定されたことは重い。斎藤知事に結論を真摯に受け止める姿勢がなければ、同じことが繰り返される恐れがある」
元記事はこちら⇩
 </picture>
</picture>
斎藤知事への告発文書問題。
百条委員会でも第三者委員会でも斎藤知事のパワハラを認定しましたが、
知事は中々これらの報告には納得していない様子です。
特にこの問題の発端のひとつ、昨年3月の記者会見での「嘘八百発言」は第三者委員会の報告後ですら
撤回しないと述べています。
自分の非を認めない、そんな斎藤氏の性格から起こった騒動とも言えそうです。
参考:⇩
3月12日頃:西播磨県民局長は報道機関等に告発文書を送付。
3月20日:知事は告発文書の存在を把握。
3月21日:知事は片山副知事に徹底的に調べるよう指示。その後人事課は、西播磨県民局長が文書作成者と特定。
3月25日:片山副知事は西播磨県民局まで出向き徴取と公用PCを没収。
3月27日:西播磨県民局長の定年退職を保留。記者会見で「事実無根」「誹謗中傷」「嘘八百」「公務員失格」と断罪。
4月1日:西播磨県民局長は知事の記者会見の反論文を報道機関に送付。
4月4日:西播磨県民局長は県の広報通報窓口に通報。
5月7日:県は西播磨県民局長を3か月停職の懲戒処分。
5月21日:県議会の要請を受け知事は第三者委員会での再調査を表明。
6月13日:県議会は百条委員会の設置を決定。
斎藤さんは悪くないと応援している方々、兵庫県内在住でしょうか、それとも他府県在住でしょうか。
5年前制定のパワハラ防止法を知っているのでしょうか。
更に言えば、自分の職場では理不尽な上司や虐めのような仕打ちを受けている同僚はいないのでしょうか。
経験が無くとも自分の配偶者や子供が職場でパワハラ被害に遭う可能性はゼロではありません。
立花氏のデマ拡散や斎藤氏のパワハラ認定を知っても
「斎藤さんガンバレ、斎藤さん敗けるな!」と応援するのでしょうか。
選挙演説で「20m歩かされただけで起こる訳ないじゃないですか」と斎藤さん。
それに拍手する聴衆。
ねぇ、教えて、アホの斎藤支持者さん。
— 但馬問屋 (@wanpakuten) March 20, 2025
ウソの演説で当選しても「民意を得た」ことになるの?
ウソだろうが公選法違反だろうが、当選しちゃえば結果オーライなの? https://t.co/xgCcNni0B1 pic.twitter.com/T80roK9k2V
当時、自転車進入禁止の標識を見ましたが、自転車でさえ通行禁止、
それだけ地下に貴重な埋蔵物があるという事だったのです。私も地下の事まで考えが及ばなかったです。
知事なのに
— 星😊花粉ヤバいですね💦 (@6LDdxtizimekJuh) March 20, 2025
県立考古博物館のこと何も知らなかったんですね。
そして
知ろうともしなかった。
こんな兵庫県知事いりません#斎藤元彦の辞職を求めます#斎藤元彦#END元彦 pic.twitter.com/tvS1pubc1I
そして今朝Xで、こんなポストを発見しました。⇩
本日、いなむら和美候補の街頭演説に
— むむむ (@mumumu_inamu) November 12, 2024
突如参戦した、
【元県民局長の親友】の怒りの訴えです!
多くの人に斉藤県政の実態を伝えて下さい🙇#兵庫県知事選挙#いなむら和美と兵庫を創る pic.twitter.com/bbcSIrktXb
演説をしている方は加古喜一郎さん。きいちろ - Wikipedia
この演説の所為か、立花氏に攻撃された事もある様ですが、
今年1月に亡くなっています。(立花氏の発言は関係ないと思いますが。。。)
※こちらは昨年11月12日、稲村和美さんの応援演説の頃の投稿です。⇩
彼自身は、もはや退職を待つだけの身。
— 加古きいちろ(加古貴一郎) (@yumeiromugen) November 12, 2024
あのような告発文書を発することに、彼自身の立身出世などのメリットは何もない。
あるのはリスクのみ。
それでも行動した。
よほど腹に据えかねる何かがあったのだろう。
そして、常々から県政運営の歪みを憂い、後輩たちの将来を憂いていたことは間違いない。
また加古氏は竹内県議と同じ高校出身です。
4人の自殺者。
— ukdata (@ukrss) February 18, 2025
いずれも姫路西高校卒業です。
渡瀬康英県民局長
竹内英明県議
加古貴一郎(衆院選落選)
橋本浩良総務課長
橋本浩良氏は初めて聞く名前ですが、優勝パレード担当で、過労が原因なのか鬱病を発症し亡くなり、
死因は自死だと言われています。
偶然が重なったと思いますが、それでも気持ち悪いです。
それにしても不可解な事が多過ぎます。
これが兵庫県庁内の闇、という事なのでしょうか。
いずれにしても斎藤さんには謙虚な気持ち、そして県庁、県議会を纏め、
県民の為を考えて行動してもらいたいです。