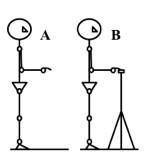PCS International Conference of Neuroscience
Theme: Effects of illusory kinesthesia by vibratory tendon stimulation on acute pain
Time: 7-8 April, 2017
Place: Lisbon, Portugal
株式会社geneセミナー
開催日時 2017年4月16日(日)10:00~16:00(受付9:30~)
テーマ 半側空間無視・失行の神経メカニズムとニューロリハビリテーション~札幌会場~
会場 札幌コンベンションセンターSORA 2階 204会議室
芸西病院講演
平成29年4月22日(土)14時〜17時
テーマ:社会・発達神経科学とリハビリテーション
場所:芸西病院
対象:病院スタッフ
近森リハビリテーション病院 講演
平成29年4月23日(日)12時〜14時
テーマ:半側空間無視の病態解釈とリハビリテーション
場所:近森リハビリテーション病院
対象:病院スタッフ
ミヤタジュク・プレゼンツ・ナイトセミナー
平成29年4月23日(日)19時〜21時
テーマ 脳を学ぶ〜コミュニケーションって何?〜
場所 ミヤタヤ
産業理学療法研究会講演
テーマ 慢性痛の神経メカニズムから予防と臨床介入を考える
場所 幕張勤労プラザ
日時 平成29年5月11日(木)17時半~19時半
第52回日本理学療法学術大会
日時 2017年05月12日15時:30分
場所 幕張メッセ
演題発表 脳卒中片麻痺上肢における運動イメージ能力と運動機能ならびに身体使用頻度との関係
熊本デイサービスHOKORU(ホコル)講演
テーマ リハビリテーションのための脳・神経科学入門
日時 平成29年5月19日(金)
場所 HOKORU
株式会社geneセミナー
テーマ 痛みの脳内機構とニューロリハビリテーション~東京会場~
開催日時 2017年5月21日(日)10:00~16:00(受付9:30~)
会場 株式会社 東京証券会館 8階 ホール
トライデントスポーツ医療看護専門学校特別講義
日時: 平成29年5月26日(金)
テーマ:痛みの脳内機構とリハビリテーション
北斗病院 講演
日時 平成29年5月27日(土)〜28日(日)
テーマ ニューロリハビリテーション
場所 十勝リハビリテーションセンター・北斗病院