今年の二月、
「着物の堅苦しいルールはどのようにして
できたのか」の記事をアップ。
その続きとして
「着付け」のルールの移り変わりを
アップすると書きましたが、
諸処の事情からそのままになっていました。
娘の結婚式にあたり、ファーマルのこと
いろいろ当たっているうちに、
その当時に書いたメモが残っていたので、
この際だからアップしておきます。
日本に始めて着付けの学校
「装道」ができたのが
1964年(昭和34年)です。
その課程のなかで、
① 1967年 初めて補正胴着を使用。
補正で寸胴体型を作ることが常識になる。
② 胸やおはしょりは整えられ、帯揚げ
帯締めもくずしがみられなくなる。
着付け教室はフォーマル着付けが中心で、
だんだん楽な着付けから遠ざかっていく。
とあります。
出典は、
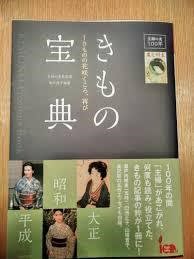
「きもの宝典」(田中敦子・主婦と生活社刊)
(文中では着付け教室を特定していません。為念)
ラクな着付け(気付け)からと遠ざかっては
人を圧倒したり、遠ざけたりするので、
引き寄せからも遠くなりますよ(笑)
よく戦前はこうだった、それは違う、
おかしいとの意見が出てきますが、
それも道理で、
着付け教室ができる前は
礼装も自分で着付け。
少し丁寧にやるくらいで
基本はふだんと変わらなかった。
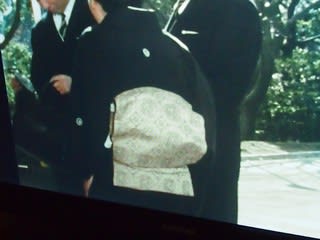 ~40
~40
礼装でもゆるい。昭和30~40年代。
「おはしょりはこう」
「帯締めの位置はこう」
などのいろいろな決まり事は
伝統というより、
ある着付け教室のフォーマル用の
マニュアルなわけです。
それが権威を持つようになっていった。
フォーマル着付けを普段きものにまで
応用?(強制?)するようになった。
なぜここまで権威を持つようになり、
絶対感を持つようになったのか。
最近、古本屋で
たまたま手にした古本が
回答をくれそうです、

「装道礼法きもの学院テキスト」&「きものの本」
拝読してみると、
とても参考になることが書いてあります。
これはまた次に~~。
で、懸念の結婚式の
これまた懸念の黒留。
「ああ、きれい!」
「~~でもほかの人みたい」
と言われるより、
自分らしく出席したいので、
昭和の母、自分着付け。で行きます。
鋭意レッスン中。
いつもの応援ポチ
いつものありがとうございます。



























誰もがモデルでも女優でも大名の奥方でもないのですから、ゆったり楽しく着たいのが本来のキモノですよね。
折々に楽しく拝読しています。
コメントありがとうございます。
女優やモデルと同じようになろうとするより、自分らしく着ようとするほうが難しいですね。私もはなさんのブログ拝見しております。今後ともよろしくお願いします。