先の「黒留めに刺繍半襟はOK?」の
記事で、黒留の刺繍は「鷹」ではなく
「孔雀」ではないかとのご指摘をいただきました。
確かに!
訂正しておきますね。
ところで「間違い」は
自分の密かな願望を潜在意識がキャッチして
表に表したともいいます。
「ミス」を起こしたとき、
即訂正するのは無論ですが、
自分の「ココロの内側」に分け入り、
検討してみるのも面白いかもしれません。
ーーーーーーー ーーーーーーー
ーーーーーーー
さて、「着付けのルール」、
先日「着付けの変遷」をアップしましたが、
今回は、「装道」の創始者、山中典士氏の言葉を
見つけましたので、それをご紹介しておきます。
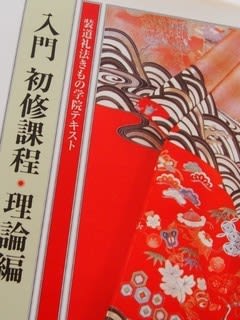
「入門 初修課程・理論編」(装道出版局)
この本には、
「装道」の創始者山中氏の簡単な経歴とともに、
きもの教室を開く経緯が記されています。
山中氏は15歳のときに海軍の飛行士を
目指したが、幸い無事に帰還。
無事に帰還なさらなかったら、
現在のきもの事情もかなり
変っていたでしょうね。
いまの私が着物に興味を持てたのも~~。
復員後間もない昭和23年に呉服業界に。
帯やきものの販売に携わり、
あるきものの会社の重要なポストに。
昭和39年、
「このままではきものは滅びる」
と危機感を持ち、
「きものの着装を指導する専門家を養成する
学校」を創設。
先の記事と日本で初めて着付け教室が
できた年が違っています。
あとで調べてみます)
そうなんですね、
一般の人相手ではないんですね。
「専門家育成」だったんですね。
最初は生徒7人、次は二十人、
そして朝日新聞に「女性の新しい職業」として
紹介されたことから一気に広がった。
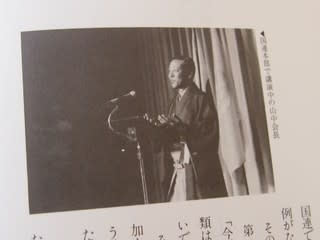
講演する山中氏。
開設にあたり、
「このままではきものは滅びる」
との危機感を抱いた理由を四つ
あげています。
①時代の変化。
洋装全盛の時代。
②生活環境の変化。
生活は合理化され、新幹線などができて
スピード化。
③ 女性の体型の変化。
現代女性の身体にメリハリができはじめ、
これでは着崩れるとずん胴体型を作るため
補正。
④価値観の変化。
きものを買う歓びから車や海外旅行にお金を
使うように。
これからのきものは
「温故知新」ではなく
「知新温故」、つまり時代にあった
新しい着付けをしなければと、
おっしゃっていますよ。
ここでは②のスピード化と③の体型の変化に
伴う補正について述べてみます。
② 黒留10分?で着るなどの
レッスンがありますが、
これはそのせいなんですね。
ゲームじみたレッスンかと思っていました(笑)
ファストファッション
(ファストの意味は違うけど)を
目指していたのですね。
早いほうが着付ける側も着付けられる側も
どちらも楽ですが、
「ゆっくり着るからこそのきもの」
ではないのですね。
私はゆっくり派です。
慣れれば、それなりに早く着られるけど。
③の体型の変化に伴う寸胴体型作りは、
これは着る人の個性をなくすのでは?
と思っていますが、
着せる側にすれば、着崩れないのが
大切、ということでしょうか。
同じような体型にしたほうが
着付ける側は楽、
ということはあると思います。
今ではフォーマルでも
楽で着崩れない着付けを
なさっている方も大勢
おはしょり三角折り上げにしても、
衽線にしても、どなたかが
「先生、こうすればおはしょり、
すっきり見えませんか」
「そうね、見える!見える!」と
試行錯誤を重ねられた結果なんですね。
私の試行錯誤と基本、同じだわ(笑)

普段に着る人のためではなく、
「着付けを職業にする人」
のための着付けだったのですね。
納得。
一般の普通の人は、
それこそ「お好み次第」で
よろしいのですね。
納得。
時代の変化に伴い、
着付けもどんどん変えていったほうがいい
ということですよね。
納得。
きもの警察は、ある着付け教室の
やり方を「伝統」だとか「正しい」とか
勘違いした一部の人たちが行う、
むしろ邪道、だということが
よくわかりました。
読んでみるものです。
これまでの謎が解明。
いろいろすっきりしました。
手に取ってよかった。
私があまり知りたがるものだから、
山中氏が引き寄せてくれたんですね。
いずれにせよ、私がきものを楽しめるのは
これまでたくさんの素敵な着姿を
見せてくださったから。
それもこれも功罪はともかくこの方のお陰。
感謝です。
というわけで、
いつも応援ポチ
ありがとうございます。



























「装道」のお話を読ませていただきました。
私は今上陛下と同い年なのですが(1960年生まれ)母も伯母も着付けはできませんでした。
18で和裁学校、20代で装道に通い、今はお人形専門の呉服屋さんをやっています。
40年、着物から離れずに暮らしてきましたけど
装道で習ったことはあくまで基礎。
いろんな人から見聞きしたことや、本で読んだこと、ブログで拝見できることで未だに学ぶことが多いです。
だから楽しいのに自分の知識が「絶対に正しい!」と思って他人に押しつけるような着物警察の方々は、狭い了見で自分の世界を狭めているような気がします。
もっと楽しめばいいのに。
コメントありがとうございます。「お人形のためのきもの」ってすごいですね。ブログも拝見させていただきました。人が着るきものを作るより大変そうです。
ぜひ広めてください。何かあったら、こちらでも告知くらいはできますのでご連絡ください。私は広島出身なんですよ。豪雨の時には本当に心配しました。妹一家がいるんですね。着物警察の件は、何度かアップしているのでもういいかなと思ったのですが、こういう記事ってやはり何度もアップしたほうが浸透するのかもしれないって思うようになりました。ドールきもの、素敵です。頑張ってください。
ありがとうございます。
着物が好きだから、それに関わる仕事をしたかったのですが、着付け教室をするには、まだ若すぎて(22歳でした)呉服屋さんの仕事は、売り込む営業ができませんでした。
結局、呉服屋さんになったのですが(相変わらず営業下手です)お客様は男性の方が多いですよ。
皆さん、着物がお好きなんですね。
女性も男性ももっと着物を楽しんで欲しいです。
再度のコメントありがとうございます。こんな風にやり取りできるの楽しいです。男性ファンが多いとのこと、いいですね。男性もきもの着たいという方多いのです。でも少しハードルが高いのかも。一度はまるとずっと着たくなるのは男性も女性も同じですね。どうしてきものって楽しいんでしょう。枠があるから、その枠をいかにうまく超えたり、その加減が楽しいのではないかとも考えます。