坐功は先ず形坐より始まり、心坐に入り、心坐より息坐に進むのである。
何を以って坐というのでしょうか。静を得、静を凝らすを以って坐というのです。何故に静を凝らさなければならないのか。今の時代、人が喜んで快楽、娯楽を得ようとする時代です。人に六根(目、耳、鼻、舌、身、意)がある以上、人は内在神を六塵に侵されえいるのです。六塵とは目で見て色欲が生まれ、耳で聞いて声欲が生まれ、鼻で嗅いで香欲が生まれ、舌で舐めて味欲が生まれ、身で触れて、触欲が生まれ、意に着して法欲が生まれます。言わば、知らず知らずに心は外のものに囚われているのです。この六塵により心は妄想妄念を生み、気は妄鬼に奪われ、元気を損傷し、それにより、先天の炁霊は日に日に衰弱し、吾が生命力を消耗し、損なっています。是により人は病を自らが得ているのです。
先天坐に三段階あります。
形坐。まず、座イスを使い、舌を上あごに付け、両手は膝がしらに密着させ、目は半目、時間は四度(16分)から十六度です。この形坐を以って、入門としなければ決して上乗に到りません。坐イスをもって、徐々に習坐します。平平坦々として損なわない様に為します。形坐の工夫は反復を繰り返し、たとえ、困難があっても、窔(内在神)を守り、念を清めます。そして、守ると言う事に固執しません。そして、坐中に悟ることにより、黙することが出来るようになります。
念がない時は、一たび感ずれば通じ、一たび通じれば、即ち悟り、一たび悟れば化し、一たび化せば、明らかになります。吾が師老祖は平黙の2字を以って坐功の主旨としています。もし一時でも平黙を得ることができたなら、一時の先天の炁霊の感通があり、前もって予知する事もでき、自己の本性を見ることもできるのです。
形坐は心を練り、気を練り、質を練るゆえんです。
心坐。心坐は念を空とし、窔(内在神)を虚とし、自然の運行に任せ、先天の炁霊の自然の活力を伸ばし適合させるのです。
日々の日常生活の中で、心で坐をします。日常坐臥です、これは相当難しいです。心坐の修練はたとえ、坐らない時においても形坐の時と同様に練らねばなりません。
暇で心に苦悩がない時は比較的容易です。心が乱れていないからです。しかし、一旦事が起き、悩みの種が生まれると、心坐を練るのは難しくなります。悩みを心配するからです。さらに事が思うようにいかず、意気消沈している時や、怒り心頭の心理状態では更に難しくなります。是を成すには修練に志す事にあります。最初は修練してもうまく行きませんが、この志を変えることなく必ず再三再四練るので、そこに成果があがるようになります。一度の修練で失敗をしても、自己を信じこれを成す、堅固な意志が必要です。心坐で守ることは、心の本来の主宰を守る事であり、端然として位を正すだけで自ずから自然の陰陽風雨晦明に広がり、中和を致します。このように和の光が充実してくれば、直晶(陽気)は自ずから昇り、曲汚は自ずから亡びるのです。
息坐。息坐は黙(一念不生)を悟り、これが坐の根本であり、先天の坐であります。それはあたかも、胎児が生まれて来る前に気海(母の腹)に平坐している状態であり、そこには少しの雑念や意念なども存在しない状態であり、呼吸は胎息であり、これこそが無為自然なのです。息坐とは先天の炁霊の坐なのです。
息坐は先天の炁霊の自然に坐し、ただ平黙だけです。平黙を行うことができれば、息坐は自ずから功を現わすことができるのです。
「天下の事はみな粗より精に進み、練ることによって得られる。学んで時々刻々にこれを習うようにすれば、必ず最高の玄妙の境地に至るのである。それには人知れず苦労をして、一途に貫いて修練に励み、これを学び、悟り、実行していけばよいのである。いかに高遠な理想をもっても、千里の道も一歩からであり、高い山に登るにも、低い処から登り始めるのである。」
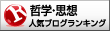 哲学・思想 ブログランキングへ
哲学・思想 ブログランキングへ


にほんブログ村
面白くないかもしれませんが上記三カ所押してくださいませ。
何を以って坐というのでしょうか。静を得、静を凝らすを以って坐というのです。何故に静を凝らさなければならないのか。今の時代、人が喜んで快楽、娯楽を得ようとする時代です。人に六根(目、耳、鼻、舌、身、意)がある以上、人は内在神を六塵に侵されえいるのです。六塵とは目で見て色欲が生まれ、耳で聞いて声欲が生まれ、鼻で嗅いで香欲が生まれ、舌で舐めて味欲が生まれ、身で触れて、触欲が生まれ、意に着して法欲が生まれます。言わば、知らず知らずに心は外のものに囚われているのです。この六塵により心は妄想妄念を生み、気は妄鬼に奪われ、元気を損傷し、それにより、先天の炁霊は日に日に衰弱し、吾が生命力を消耗し、損なっています。是により人は病を自らが得ているのです。
先天坐に三段階あります。
形坐。まず、座イスを使い、舌を上あごに付け、両手は膝がしらに密着させ、目は半目、時間は四度(16分)から十六度です。この形坐を以って、入門としなければ決して上乗に到りません。坐イスをもって、徐々に習坐します。平平坦々として損なわない様に為します。形坐の工夫は反復を繰り返し、たとえ、困難があっても、窔(内在神)を守り、念を清めます。そして、守ると言う事に固執しません。そして、坐中に悟ることにより、黙することが出来るようになります。
念がない時は、一たび感ずれば通じ、一たび通じれば、即ち悟り、一たび悟れば化し、一たび化せば、明らかになります。吾が師老祖は平黙の2字を以って坐功の主旨としています。もし一時でも平黙を得ることができたなら、一時の先天の炁霊の感通があり、前もって予知する事もでき、自己の本性を見ることもできるのです。
形坐は心を練り、気を練り、質を練るゆえんです。
心坐。心坐は念を空とし、窔(内在神)を虚とし、自然の運行に任せ、先天の炁霊の自然の活力を伸ばし適合させるのです。
日々の日常生活の中で、心で坐をします。日常坐臥です、これは相当難しいです。心坐の修練はたとえ、坐らない時においても形坐の時と同様に練らねばなりません。
暇で心に苦悩がない時は比較的容易です。心が乱れていないからです。しかし、一旦事が起き、悩みの種が生まれると、心坐を練るのは難しくなります。悩みを心配するからです。さらに事が思うようにいかず、意気消沈している時や、怒り心頭の心理状態では更に難しくなります。是を成すには修練に志す事にあります。最初は修練してもうまく行きませんが、この志を変えることなく必ず再三再四練るので、そこに成果があがるようになります。一度の修練で失敗をしても、自己を信じこれを成す、堅固な意志が必要です。心坐で守ることは、心の本来の主宰を守る事であり、端然として位を正すだけで自ずから自然の陰陽風雨晦明に広がり、中和を致します。このように和の光が充実してくれば、直晶(陽気)は自ずから昇り、曲汚は自ずから亡びるのです。
息坐。息坐は黙(一念不生)を悟り、これが坐の根本であり、先天の坐であります。それはあたかも、胎児が生まれて来る前に気海(母の腹)に平坐している状態であり、そこには少しの雑念や意念なども存在しない状態であり、呼吸は胎息であり、これこそが無為自然なのです。息坐とは先天の炁霊の坐なのです。
息坐は先天の炁霊の自然に坐し、ただ平黙だけです。平黙を行うことができれば、息坐は自ずから功を現わすことができるのです。
「天下の事はみな粗より精に進み、練ることによって得られる。学んで時々刻々にこれを習うようにすれば、必ず最高の玄妙の境地に至るのである。それには人知れず苦労をして、一途に貫いて修練に励み、これを学び、悟り、実行していけばよいのである。いかに高遠な理想をもっても、千里の道も一歩からであり、高い山に登るにも、低い処から登り始めるのである。」

にほんブログ村
面白くないかもしれませんが上記三カ所押してくださいませ。










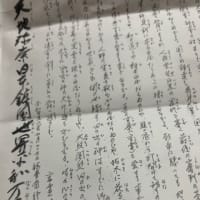


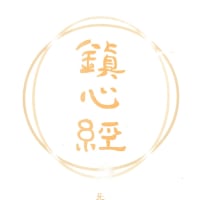












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます