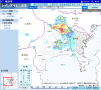午前中に記載したとおり午後から「戦場に輝くベガ」【HPはこちら】の上映会に参加してきた。
一昨年2014年に「星ナビ」に「終わらない物語」の紹介記事を書いていたので、内容はほとんど理解していた。
また星ナビ編集委員から具体的に感想も聞いていたので、既視感があったが、それでも前段の「スペースファンタジーライブ」とあわせて興味深く、そして感銘深い2時間を過ごすことが出来た。
記念に当時の記事をもう一度ここに再掲載して起きたい。当時の記事をすでに読んだ方は読み飛ばしてください。
プラネタリウムの番組というのをご存じであろうか。プラネタリウムで星を見ることが今は流行っている。そして60分なり90分の投影時間内の番組というのは、それぞれのプラネタリウムによってさまざまに工夫されている。その番組制作には多くの体験者の想いが込められている。
私も昔は星空を眺めるのは大好きで、小中学生の当時、渋谷にあった五島プラネタリウムに幾度も通った。その当時は星座と星座にまつわる神話、日周運動の説明、惑星の運行の説明など基本的な観測の説明が主であった。
今回この月刊誌で紹介されたプラネタリウム番組「戦場に輝くベガ-約束の星を見上げて-」は山梨県立科学館のオリジナル番組である。太平洋戦争中の「天文航法」をテーマにして、当時の忘れられてしまいそうな事実を掘り起し、人々の暮らしや想い、願いをつづった出色の番組である。
この番組の脚本・演出を担当された跡部浩一・高橋真理子両氏による8頁にわたる紹介文である。
私も知らなかったが、長距離飛行、特に爆撃機の出撃にはレーダーの無かった当時は、星空の観測による位置確認がどうしても必要であった。特定の明るい観測しやすい星3個の地平高度を測り、簡易天測表を使って位置を測るというもの。その測定は搭乗員がするものの、機上での計算をしなくても済むように作られたのが「高度方位暦」というとのこと。その作成に学徒動員された当時の女学生が当たっていた。その事実を丹念に掘り起し、番組に丁寧に仕上げたことが紹介されている。
星空を見上げるのが好き、天文現象に興味がある人はたくさんいる。星を見上げるのは人類の人類たるゆえん、人の原初からの尽きない想像力を駆り立ててきたともいえる。この紹介文書には次のような言葉も記載されている。6段に分かれた文章の圧巻は5段目である。
「星空は地球上の生命が共有できる唯一の風景である。‥星空はすべてをつなぐ力を持っている。」「この番組を構成している軸に、男と女、加害と被害、当時と今、という対がある。それをすべて引き裂くのが「戦争」であり、すべてを超えてつなぐことができるのが「星」だとこの物語は伝える。」
あらすじの紹介では戦争の加害と被害ということに言及している。「(主人公の)和夫は、満天の星に包まれながら、自分が爆撃した相手にもねどうしても会いたい大切な人がいるであろうことに思い至る。」
これはひょっとしたら戦争というものを無くすための、残念ながら、とても儚い微かな希望なのである。しかし今のところそこに微かな希望を持つしかないのが、現在の私たちである。
戦争は、誰もが加害者になり、誰もが被害者になる。人が人を殺す論理が「正義」になるのが戦争である。あの戦争の後も、あれから70年経ても人は国家意思に従属させられて、戦争に駆り出されてきた。今また「国家の論理」「国家の正義」が個人の意思・論理の上に君臨しようとしている。「正義の戦争」という名で「人が人を殺す正義」が大手を振ってのし歩こうとしている。世界中があの70年前とその後も続いた殺戮戦の教訓を忘却し始めている。
「星が武器としてではなく、希望の光として輝ける日が来ることを祈っています」がこの番組の最後に語られるようだ。私たちは戦争を知らない世代と云われたが、いつの間にか私たちが戦争を語り継がねばならない世代になっている。若い世代が「終わらない物語」が終わる可能性を求めて、生き抜いてほしいと思う。
なお高度方位暦の詳しい内容は以下にあります。私のツィッターのフォロワーの「山田陽志郎」さんに紹介していただきました。とても勉強になります。
【http://www.jha.or.jp/jp/shop/products/suiro/pdf/suiro157.pdf#page=5】
同時にパンフにも紹介されている「聖マーガレット礼拝堂に祈りが途絶えた日」の本の紹介文も教えていただいた。

本日配布された資料から二つを紹介。


一昨年2014年に「星ナビ」に「終わらない物語」の紹介記事を書いていたので、内容はほとんど理解していた。
また星ナビ編集委員から具体的に感想も聞いていたので、既視感があったが、それでも前段の「スペースファンタジーライブ」とあわせて興味深く、そして感銘深い2時間を過ごすことが出来た。
記念に当時の記事をもう一度ここに再掲載して起きたい。当時の記事をすでに読んだ方は読み飛ばしてください。
プラネタリウムの番組というのをご存じであろうか。プラネタリウムで星を見ることが今は流行っている。そして60分なり90分の投影時間内の番組というのは、それぞれのプラネタリウムによってさまざまに工夫されている。その番組制作には多くの体験者の想いが込められている。
私も昔は星空を眺めるのは大好きで、小中学生の当時、渋谷にあった五島プラネタリウムに幾度も通った。その当時は星座と星座にまつわる神話、日周運動の説明、惑星の運行の説明など基本的な観測の説明が主であった。
今回この月刊誌で紹介されたプラネタリウム番組「戦場に輝くベガ-約束の星を見上げて-」は山梨県立科学館のオリジナル番組である。太平洋戦争中の「天文航法」をテーマにして、当時の忘れられてしまいそうな事実を掘り起し、人々の暮らしや想い、願いをつづった出色の番組である。
この番組の脚本・演出を担当された跡部浩一・高橋真理子両氏による8頁にわたる紹介文である。
私も知らなかったが、長距離飛行、特に爆撃機の出撃にはレーダーの無かった当時は、星空の観測による位置確認がどうしても必要であった。特定の明るい観測しやすい星3個の地平高度を測り、簡易天測表を使って位置を測るというもの。その測定は搭乗員がするものの、機上での計算をしなくても済むように作られたのが「高度方位暦」というとのこと。その作成に学徒動員された当時の女学生が当たっていた。その事実を丹念に掘り起し、番組に丁寧に仕上げたことが紹介されている。
星空を見上げるのが好き、天文現象に興味がある人はたくさんいる。星を見上げるのは人類の人類たるゆえん、人の原初からの尽きない想像力を駆り立ててきたともいえる。この紹介文書には次のような言葉も記載されている。6段に分かれた文章の圧巻は5段目である。
「星空は地球上の生命が共有できる唯一の風景である。‥星空はすべてをつなぐ力を持っている。」「この番組を構成している軸に、男と女、加害と被害、当時と今、という対がある。それをすべて引き裂くのが「戦争」であり、すべてを超えてつなぐことができるのが「星」だとこの物語は伝える。」
あらすじの紹介では戦争の加害と被害ということに言及している。「(主人公の)和夫は、満天の星に包まれながら、自分が爆撃した相手にもねどうしても会いたい大切な人がいるであろうことに思い至る。」
これはひょっとしたら戦争というものを無くすための、残念ながら、とても儚い微かな希望なのである。しかし今のところそこに微かな希望を持つしかないのが、現在の私たちである。
戦争は、誰もが加害者になり、誰もが被害者になる。人が人を殺す論理が「正義」になるのが戦争である。あの戦争の後も、あれから70年経ても人は国家意思に従属させられて、戦争に駆り出されてきた。今また「国家の論理」「国家の正義」が個人の意思・論理の上に君臨しようとしている。「正義の戦争」という名で「人が人を殺す正義」が大手を振ってのし歩こうとしている。世界中があの70年前とその後も続いた殺戮戦の教訓を忘却し始めている。
「星が武器としてではなく、希望の光として輝ける日が来ることを祈っています」がこの番組の最後に語られるようだ。私たちは戦争を知らない世代と云われたが、いつの間にか私たちが戦争を語り継がねばならない世代になっている。若い世代が「終わらない物語」が終わる可能性を求めて、生き抜いてほしいと思う。
なお高度方位暦の詳しい内容は以下にあります。私のツィッターのフォロワーの「山田陽志郎」さんに紹介していただきました。とても勉強になります。
【http://www.jha.or.jp/jp/shop/products/suiro/pdf/suiro157.pdf#page=5】
同時にパンフにも紹介されている「聖マーガレット礼拝堂に祈りが途絶えた日」の本の紹介文も教えていただいた。

本日配布された資料から二つを紹介。