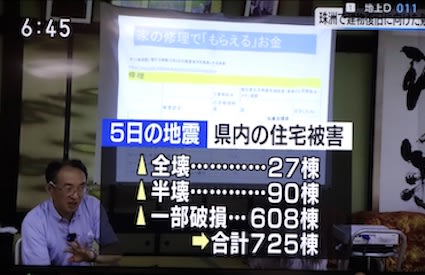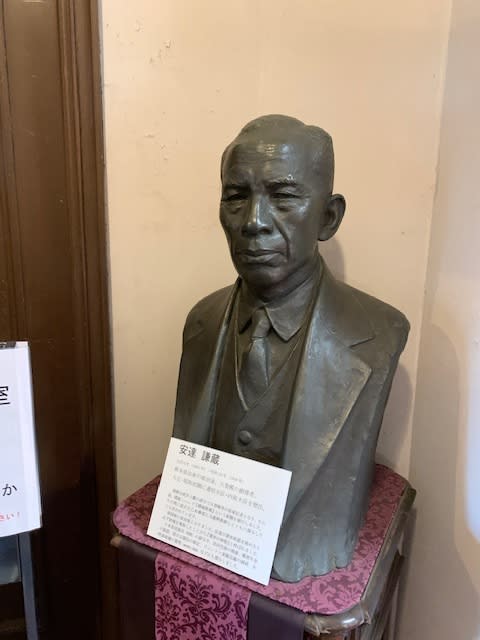写真は、モノクロームの Roof-1を乗せた住まい。
当事務所の設計ではありません。
当事務所の設計ではありません。
メーカーさんの使用されているモデルハウスです。
(木材の納めなど気になりますが、趣旨が違うのでここでは触れません)
一般の太陽光発電とは違い、屋根と一体化。遠方では区別がつかず。
住まいの設計の中で、大事にするべきポイントは何か?
と、聞かれたら、、、
快適性や居心地など、内部空間の質から、日当たり、風通し、、
収納や使い勝手のこと、水回りの設備、、、など機能面に渡り、
そして、外観のデザインなど、
私が独立した頃は、
ユーザーさんから出る言葉はそんなところでした。
しかし、地球温暖化が叫ばれるようになって、
それが一般的な実感として伴うものになってきて、
また、災害の多発によって、
最近は、
耐震性、断熱性、を最初にあげる方が増えてきました。
以前は、そんな言葉すら、専門家も使わなかったというのに!
私が、建築家協会に入りたての頃、
品格法の等級の話をしたときに、そんな国の縛りには従いたくない!
と、一蹴されたこともあります。(従う必要はなかったですから)
機能よりも、意匠性、奇抜さ、斬新さを求める傾向にありました。
巾木のない家だったり、いかにカッコイイ建築作品を作るか、
を、住宅作家の先輩方は、飲み屋では話すのでした。
巾木がない納めは、確かに素敵だけど、掃除機が当たったら、
壁は傷つくし汚れるけどなぁ、
この方達は、掃除しないのかなぁ。
箒で履けということなのかなぁ、
などど心の中でぼやきながら。。。
メンテナンスのことには、全く触れない面々。
なんとなく、男性中心のそんな空気感から
抜け出したくて、あまり団体の中に入っていくのを
避け続けて、、、今に至りますが(笑)
やっと、機能面やメンテナンスの話を、
堂々とできる時代になったのかなと思います。
当たり前すぎて、本来は、そこは、クリアすべきなのですけれどね。
省エネ法もやっと改正され、カーボンニュートラルも叫ばれ
以前のような意匠優先の住まいは、実はもう時代遅れなのかもしれません。
伝統家屋だから、寒いのは我慢するという発想も
主婦いじめだと思っているので、納得行きません。
(台所の寒さを知らない殿方のおっしゃるところでは!?)
今日は、デザイン性を確保しつつ、太陽光発電する
今年の新商品の屋根材の、メンテナンス性、維持管理、
保守点検、などなど、しつこく質問して参りました。

写真の奥の屋根材が、太陽光発電池付き、手前は、鋼板の屋根材。
近づけば、違いがわかります。
新しい機能は、大好きです。
新時代の匂いがするものも大好きです。
モデルを見学できると知った時は、
すぐに申し込みました。
が、しかし、それがきちんと維持管理できるものなのか、
建主の経済的負担が、きちんと暮らしの中で元が取れていくのか
しっかりと見極める必要があります。

下地との取り付けかた、通気などの納め方もじっくりと伺いました。
若い方は、将来の年老いた生活は、想像し難く
住まいの維持管理の手間も、職人さん不足も
きっと、想像し難いのだろうなと、思いながら
この屋根材を提案するときの、メリットデメリットをしっかりと
自分に落としこみながら、興味のある方には、紹介していこうと思います。
まだまだ、課題も感じましたが、
きっと、この方向性は、間違っていないでしょう。
どんどんとこの方向に行くのではないでしょうか。
なぜなら、HEMS*とセットだからです。
商品だけなら、私も納得できなかったと思います。

タブレットの画面と同じ操作で分かる、電気の見える化
それが、仕組みも一緒に考えているという点が
素晴らしかったですね。
だから、建築関係よりはエンジニアの方が
社員さんには多いようでした。
*「HEMS(ヘムス)」とは、Home Energy Management Service(ホーム・ エネルギー・マネジメント・システム)の略。家庭内で使用している電気機器の使用量や稼働状況をモニター画面などで「見える化」し、電気の使用状況を把握することで、消費者が自らエネルギーを管理するシステム。
インフラを電気だけに頼るのは、防災的にどうなのか?
という点も、もちろんあります。
ただ、都市ガスは、電気がないと使えない。
プロパンなら、むしろ防災には良いんだけどなぁ。。。
などなど、災害時と、平常時の両方の生活を見据えて
その人の暮らし方と、希望、そして地域性に配慮しながら、
時代の方向性を間違えないものづくりがしていきたいですね。

隣接して、工事中のモデル、屋根の一体化がよく分かる。
機能的な面で、一つの提案の形が増えたことは、
喜ばしいことだなと、会場を後にしました。
喜ばしいことだなと、会場を後にしました。
研究開発、そしてベンチャー起業、
お疲れ様でしたと労いつつ、
業界において、選択肢が増えたことには、感謝ですね。
現地でたまたま、ご一緒した設計の方や工務店さんから、
屋根下地の結露の問題や、職人さんの育成について
子どもたちの施工現場に触れる機会が少ない日本の課題など、
問題点を共有できたのも、嬉しかったですね。
ありがとうございました!