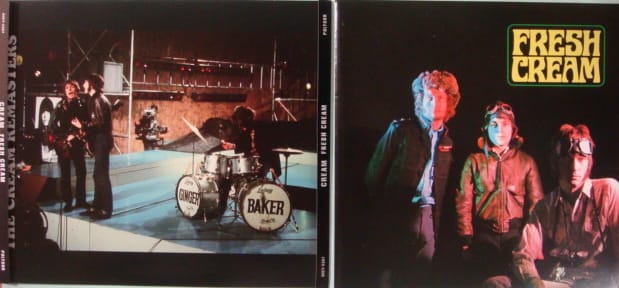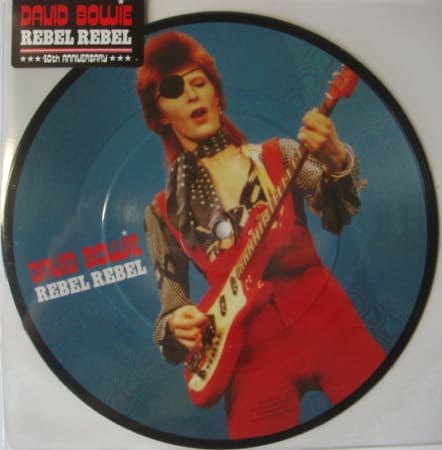それから2年後、同業者のメロディー・メーカー紙には、“ここ2年間 と云うもの英国が待ち続けた新しいタイプのロック・グループが今ここに登場した。彼らがビッグ・グループになることはもう既に運命付けられている。 このアルバム【SWEET SILENCE】は何かとっても新しくて、とてもエキサイティングな始まりである。”とこのレコードのライナーの表紙のところに記載されていた。読んでいる方が恥ずかしくなるぐらいのすごい宣伝文句であった。


それは、MR.BIGを歌ったFREEについてではなく、エリック・マーチン所属のアメリカン・ロック・バンドMR.BIGでもない。そう、あの70年代に登場した幻の英国ハード・ロック・バンド MR.BIGのこと。
ギター・ボーカルそして作詞・作曲を担当のディッケンと、ベースとドラムス二名の変則的な構成の4人組ロック・バンドだった。1974年エピックと契約しシングルを出すものの、不発。1975年EMIに移籍して出したのがこのアルバム、SWEET SILENCE。同じEMIからデビューし、当初辛口メディアに叩かれていたクイーンが2年の間に大ブレークを果たしたことから、EMIは2匹目のドジョウを狙い、彼らを売り出すことにしたのだろう。当時クイーンのオペラ座の夜のツアーにも前座で帯同したとの事。
翌年2枚目をだしシングルが中ヒット、そして1978年の3枚目はレコーディングされたものの、発売には至らず解散。2001年にCDで復刻される。
2枚目以降を聴いていないので、1枚目を聴いただけの感想を述べると、サイド1の1曲目TIME BASE、2曲目WOUNDERFUL CREATIONや6曲目SWEET SILENCEなどは確かに新しいタイプのロックの香りを感じたが、残念なことに他の曲が弱い。無理やりバラエティー感を出そうと思ったのか、カントリー、中国風、ボードビル調のサウンド取り入れた曲やスローバラッドもクイーンのそれらと比べると魅力に欠ける。せっかくのツイン・ドラムスなのだからそれを生かしてハード・ロック一辺倒でやってほしかった。また、ボーカルの少しねちっこいしゃがれ声も、好き嫌いの分かれるところかも。
残念ながら、”ビッグ・グループになることはもう既に運命付けられている”。と云う当時の宣伝文句を果たし得ることはなかった。
今更ながら思うのだが、このアルバムも含めてレコードのライナー・ノートにある記事は、レコード会社からの依頼として書いているので、当然ネガティブな記事は書けないし、たとえ好みに合わなくとも何かいいところを無理にでも探しだして褒め上げるという作業で、当時書いた本人もこれを今改めて読むと”あれは仕事だった。”と思い起こすのでは。
だから、表現が適切だったかどうかは別にして、ニック・ケントのクイーンに対する酷評は、本当に彼自身が思った事を書いたので意気込みは評価出来る。しかし、うがった見方をすれば、クイーンが新人バンドだったからで、もし大物バンドであればそのような事を言えたかどうかはわからない。
WITH THE BEATLES発売の時、女性ファンがキャーキャー言ってる時に“そんなのただの雑音さ”と言えたなら本物である。まあ、当時NME紙は、表紙によくビートルズかストーンズの写真を掲載していたそうなので、彼らに対してネガティブな記事がたとえあったとしても、現実的にそのような記事の掲載は無理だったかな?
ところで、中心メンバーのディッケンは、MR.BIGを再結成し、2011年には、通算4枚目のアルバムを発表。この歳になっても活動を続ける本当にロックな人である。

甘美のハード・ロッカー! UHA味覚糖の親戚か?
Mr.Big - Wonderful Creation
Mr.Big - Sweet Silence (邦題:甘美のハード・ロッカー)