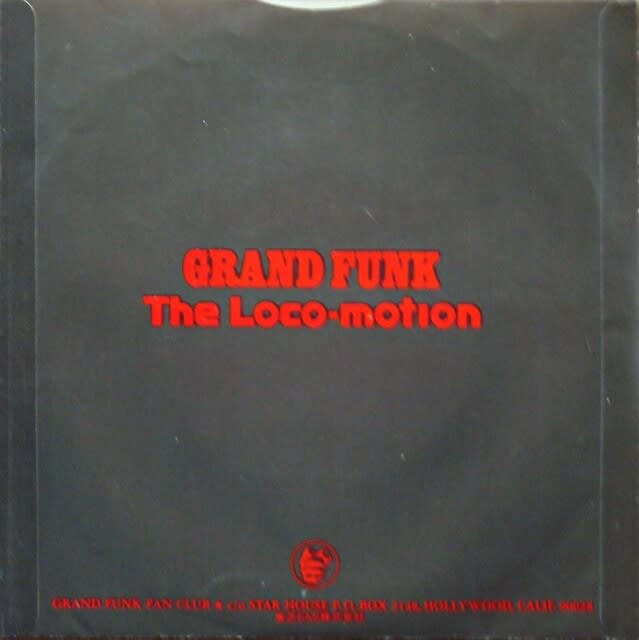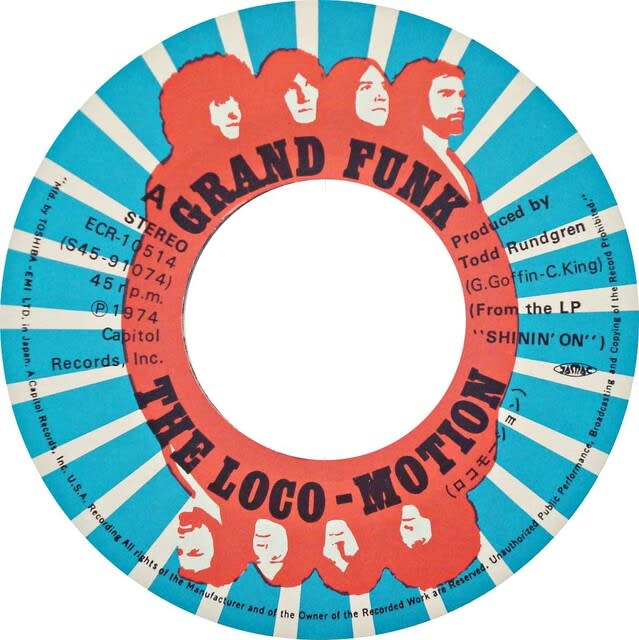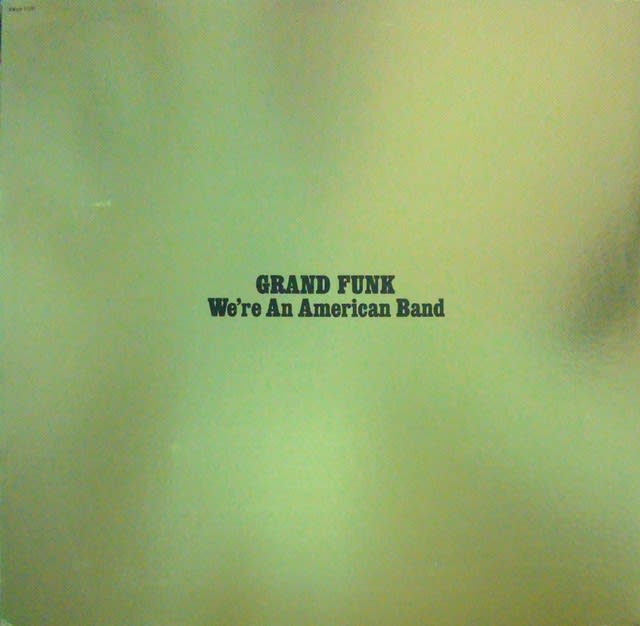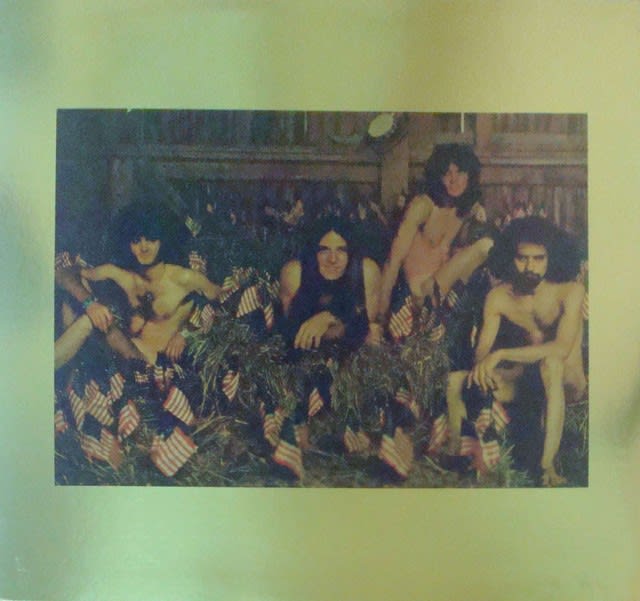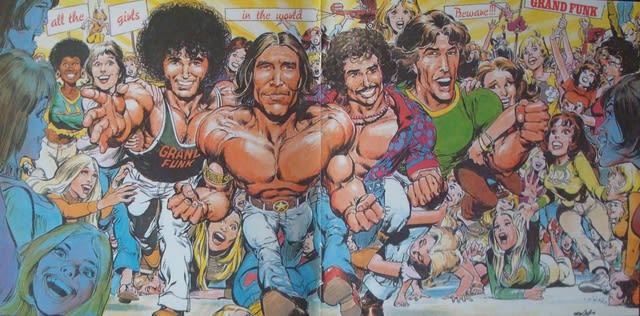ライブでの長尺演奏といえばオールマン・ブラザーズ・バンドの専売特許。
私の持っている音源中では、Ludlow GarageでのライブにおけるMountain Jamがダントツ、なんと45分越え!
レコードだと、最長はEat A Peachに収録されたこれまたMountain Jamが33分41秒かな?
カッティング作業に置いて色々やりくりすれば、28分程度はレコードの片面になんとか収まるが、30分越えとなるとレコード裏表にまたがる収録ってなことになり、ひっくり返して連続して聴くのは少々面倒臭いが、まあトイレ休憩と思えばよろし〜
これに続く長さの曲が同じMountainでもバンド名がMountainによる例のアレ。
1973年に急遽再結成し来日したMountainのライブ盤。Twin Peaksに収録された、Nantucket Sleighride(To Owen Coffin)だ。
因みに当時フェリックス・パパラルディは方向性の違いからバンドから脱退し、この日本公演はクリームのジャック・ブルースが加入した新バンド、ウエスト、ブルースとレイングの3名で行われる予定だったが、ジャックの脱退によりレスリーとフェリックス、さらに新メンバー2名を加えてのマウンテン再結成と相成った。
急ごしらえのバンドとは言え、さすがプロ! 息のあった演奏は聴きごたえがる。


Nantucket Sleighride(To Owen Coffin)はなんと32分29秒にも及ぶ熱演だ。
しばしばこれを聴くのは拷問ダァ〜なんて否定的な意見も耳にする。
確かに、かってゴルゴ13が逆さ吊りで鞭を打たれさらにヘッドフォンを装着しZepの聖なる館を爆音で聴かせる拷問があったように、一般人でも正座してヘッドフォン経由の大音量となると結構厳しいかも。
しかしスピーカーを通してなら、これ結構いけるんですよ。
ツイン・リードが右と左に別れて交互に掛け合いするのだが、これがなんとなく人の会話に聞こえて結構楽しい雰囲気に。
もし上手くリード弾けるのなら是非その掛け合いに混ぜていただきたいなんて思ってしまう。
Zepのライブ盤、The Song Remains The Sameに収録されたこれまた30分にも及ぶDazed And Confusedなんて決して他者を寄せ付けないバリアーみたいなものがあるからね。
KGB:おいゴルゴ、早く吐いちまいな!
ゴルゴ:・・・・ (心の中では、Zepの拷問を凌いだこの俺がナンタケットぐらいで落ちると思ってるなら甘いぜ!)