ちょっと開きましたが今日は猫の話です。
なお前回でお話した“反乱”は、トイレの増設、猫砂を以前使っていたものに戻すなどでほぼ終結しました。猫砂についてはよく説明書に新規に使う時は前のと少しずつ混ぜてとありますが、こんなにも違うものかと驚いています。もっともそれが原因と断定はできませんが。
さて、カロンタンの娘キャサリンの息子、名前はまだなく、猫にしては少したれ目気味なので暫定名「たれ目」と呼んでいる雄ねこは灰色と黒のとらで、この春生まれた子猫の中で一番大きくて太い脚が力強く、けれども動きはゆっくりで、ちょっとさえないやつです。
ちょっと前、子猫の間でウィルスによるいわゆる猫の鼻かぜが流行り、ほかの猫が治ってからもしばらくぐちゅぐちゅいっていたたれ目はある日、何か左目が腫れてしまいました。インターネットで症状を調べると、病気が治れば自然に戻ることが多いとのこと。動物病院の看護師Sさんにも相談したのですが、自分の忙しさもあってそのまま様子をみていました。
ところが、しばらくすると今度は黒ずんできたので、これはまずいとSさんの働く動物病院に。心配ではありましたが、初めての車にずっと運転席の下にもぐりこんでいて慣れるとお腹の上に座るようになったたれ目に、祖母のカロンタンがそうしていたことを思い出しました。
診察した若いH先生は、「これはけっこう難しいですね」。ここで初めて自分のうかつさに気づき、点眼薬とサプリメントをもらい、ほかの子猫からは隔離するようにいわれてこの日は帰りました。
隔離のために最初はダンボールにたれ目を入れましたが、普段使っていないシャワー室の方が広いと思って移動。しかし、当然のことながらたれ目は暴れます。いったん仕事に出かけて帰ってみると、シャワー室内はがしゃがしゃ、たれ目もキャネット、猫砂まみれで、目の保護のために着けていたメガホンのようなエリザベスカラーも吹っ飛んだ状態。さえないやつですが、脚は太いしいざという時には相当の力が出るようです。
やむなくもとの状態に。普段通りにほかの子猫と遊ぶたれ目は、目が腫れていることなどまったく問題ないように見えます。
約束の3日後に再び診察に行きました。「思ったよりひいてないですね」というH先生は、たれ目自身の血清から点眼液をつくるという方法をすすめ、看護師さんが「がんばれ、たれ目」と応援してくれる中、注射完了。「がまん強いですね」「ええ、動きはちょっと鈍いんですが」というやり取りがありました。それでも「やっぱりこれくらいしか採れませんでした」と、できた点眼液は1、2日分だけです。帰ってからはやつの血からできた薬だからと、こまめに点眼を続けました。それ以外の時間、たれ目はいつも通りに楽しそうです。
しかしその2日後、台風の雨の朝。昨夜の分のトイレを捨てに畑に出かけて戻ってみると、たれ目の左目から血が流れ、目尻には何か膜がぶら下がっていました。
ほかの子猫と遊んでいてなったのか、自分で何かにぶつかってなったのかはわかりません。人間ならずいぶん痛いと思う傷なのに、たれ目は前と同じに運転席の下に丸くなったまま。時々大丈夫かとなでながら、台風の中、車を走らせました。
急いで病院に着くとH先生は留守で、代わりに診てくれた先生がいうには、手術になるだろうからあずかりますとのこと。しかたなくたれ目を残し、一人で帰りました。
お昼過ぎだったか、院長先生から電話あり。最悪の場合には眼摘もあり得るが、もっともいい状態にしたいとの話でした。まかせるよりほかにしかたありません。
翌日、迎えに行って手術後のたれ目に対面。「こんなになりましたが、どうですか」とSさんが連れてきたたれ目の左目は、上のまぶたが縫いつけられ、何とか少し開く状態でした。10日くらいで抜糸になるそうです。にゃーにゃーいいだしたたれ目に、「おお、元気になった」と、にこやかなH先生とSさんでした。
もしまた傷が開くようなら、もう一度手術が必要です、ほかの猫ちゃんに触れないように隔離してないと、というH先生の言葉に従い、今度は最近寝ていなかった寝室にたれ目を隔離。またもやぎゃーぎゃー大騒ぎでしたが、すまんすまんと逃げるように仕事に出かけ、帰るとやはり大騒ぎでした。
たれ目帰還は水曜日。以来、毎晩隔離室でたれ目と寝ています。ドアを閉めると必死にぎゃーぎゃーのたれ目ですが、一緒にいるとくっついて静かに落ち着いています。点眼にも慣れたし、サプリメントも魚や肉もやし、鰹節などに混ぜてよく食べ、効果のほどはわかりませんが魚の目玉は必ずたれ目にやっています。エアコンがない隔離室はドアを開ければ十分に冷えますが、隔離なので開けっ放しにはできません。このところ夜は涼しいので助かりますが、サポートにアイスノンも買いました。
今回の隔離室暮らしで、たれ目という1頭の猫との距離は縮まっています。多くの猫と暮らしていると、猫どもをつい一頭一頭でなく集団としてとらえてしまいがちですが、一対一で過ごしてみるとその猫のリズムのようなものがよくわかります。本を読む横で、こういうタイミングで鳴いたり、こうやって乗っかって来たり。それはそれで貴重な時間と思います。そして、鼻をなめに口を近づけるたれ目の左目は、焦点がぼけて右目と同じような光を放ちます。
病院の待合で話をした車にぶつかって脚を折った犬の飼い主の夫婦は、あの時、放さなければよかったのにと悔やんでいました。私も、もっと早く病院に連れて来ていたら、ちゃんと隔離していたら膜は破れなかったかも知れない、とよく思います。
しかし帰って来てからのたれ目が、エリザベスカラーが苦しそうでほかの猫と遊びたそうなほかは、以前と変わらず元気なのでいくらかは助かります。たまに隙をみて脱走すると思わぬ鋭い脚を見せるし、片目が見えないことは人間が思うより不自由ではないように思えます。Sさんの話では、片目が義眼の猫などもあまり困ることなく暮らしているそうです。
でも何よりなのは、たれ目は片目が見えなくなっても、命はあるということ。たれ目が帰ってきた日のちょうど一年前の27日は、カロンタンが裏の道で車にはねられた日でした。たれ目には、まだ命があるからアジやサンマも食べられるし、もう少しでほかの猫と遊ぶこともできます。それは何とすばらしいことでしょう。
たれ目の抜糸まであと一週間ほど。まだちょっと不自由な暮らしが続きますが、それもまた味なものです。たれ目と一人と一頭の、シンプルな生活を楽しむつもりです。
ところで、な、カロンタン。一周忌にはいろいろ思い出そうとしていたことがあったけど、カロンタンの孫がとんだことになって考えなくちゃいけないことが多くて思い出せなかったよ。でも、生きてるやつの方が先だよな、カロンタン。
(ニャ)
長くなりました。最後まで付き合っていただいた方、どうもありがとうございます。
なお前回でお話した“反乱”は、トイレの増設、猫砂を以前使っていたものに戻すなどでほぼ終結しました。猫砂についてはよく説明書に新規に使う時は前のと少しずつ混ぜてとありますが、こんなにも違うものかと驚いています。もっともそれが原因と断定はできませんが。
さて、カロンタンの娘キャサリンの息子、名前はまだなく、猫にしては少したれ目気味なので暫定名「たれ目」と呼んでいる雄ねこは灰色と黒のとらで、この春生まれた子猫の中で一番大きくて太い脚が力強く、けれども動きはゆっくりで、ちょっとさえないやつです。
ちょっと前、子猫の間でウィルスによるいわゆる猫の鼻かぜが流行り、ほかの猫が治ってからもしばらくぐちゅぐちゅいっていたたれ目はある日、何か左目が腫れてしまいました。インターネットで症状を調べると、病気が治れば自然に戻ることが多いとのこと。動物病院の看護師Sさんにも相談したのですが、自分の忙しさもあってそのまま様子をみていました。
ところが、しばらくすると今度は黒ずんできたので、これはまずいとSさんの働く動物病院に。心配ではありましたが、初めての車にずっと運転席の下にもぐりこんでいて慣れるとお腹の上に座るようになったたれ目に、祖母のカロンタンがそうしていたことを思い出しました。
診察した若いH先生は、「これはけっこう難しいですね」。ここで初めて自分のうかつさに気づき、点眼薬とサプリメントをもらい、ほかの子猫からは隔離するようにいわれてこの日は帰りました。
隔離のために最初はダンボールにたれ目を入れましたが、普段使っていないシャワー室の方が広いと思って移動。しかし、当然のことながらたれ目は暴れます。いったん仕事に出かけて帰ってみると、シャワー室内はがしゃがしゃ、たれ目もキャネット、猫砂まみれで、目の保護のために着けていたメガホンのようなエリザベスカラーも吹っ飛んだ状態。さえないやつですが、脚は太いしいざという時には相当の力が出るようです。
やむなくもとの状態に。普段通りにほかの子猫と遊ぶたれ目は、目が腫れていることなどまったく問題ないように見えます。
約束の3日後に再び診察に行きました。「思ったよりひいてないですね」というH先生は、たれ目自身の血清から点眼液をつくるという方法をすすめ、看護師さんが「がんばれ、たれ目」と応援してくれる中、注射完了。「がまん強いですね」「ええ、動きはちょっと鈍いんですが」というやり取りがありました。それでも「やっぱりこれくらいしか採れませんでした」と、できた点眼液は1、2日分だけです。帰ってからはやつの血からできた薬だからと、こまめに点眼を続けました。それ以外の時間、たれ目はいつも通りに楽しそうです。
しかしその2日後、台風の雨の朝。昨夜の分のトイレを捨てに畑に出かけて戻ってみると、たれ目の左目から血が流れ、目尻には何か膜がぶら下がっていました。
ほかの子猫と遊んでいてなったのか、自分で何かにぶつかってなったのかはわかりません。人間ならずいぶん痛いと思う傷なのに、たれ目は前と同じに運転席の下に丸くなったまま。時々大丈夫かとなでながら、台風の中、車を走らせました。
急いで病院に着くとH先生は留守で、代わりに診てくれた先生がいうには、手術になるだろうからあずかりますとのこと。しかたなくたれ目を残し、一人で帰りました。
お昼過ぎだったか、院長先生から電話あり。最悪の場合には眼摘もあり得るが、もっともいい状態にしたいとの話でした。まかせるよりほかにしかたありません。
翌日、迎えに行って手術後のたれ目に対面。「こんなになりましたが、どうですか」とSさんが連れてきたたれ目の左目は、上のまぶたが縫いつけられ、何とか少し開く状態でした。10日くらいで抜糸になるそうです。にゃーにゃーいいだしたたれ目に、「おお、元気になった」と、にこやかなH先生とSさんでした。
もしまた傷が開くようなら、もう一度手術が必要です、ほかの猫ちゃんに触れないように隔離してないと、というH先生の言葉に従い、今度は最近寝ていなかった寝室にたれ目を隔離。またもやぎゃーぎゃー大騒ぎでしたが、すまんすまんと逃げるように仕事に出かけ、帰るとやはり大騒ぎでした。
たれ目帰還は水曜日。以来、毎晩隔離室でたれ目と寝ています。ドアを閉めると必死にぎゃーぎゃーのたれ目ですが、一緒にいるとくっついて静かに落ち着いています。点眼にも慣れたし、サプリメントも魚や肉もやし、鰹節などに混ぜてよく食べ、効果のほどはわかりませんが魚の目玉は必ずたれ目にやっています。エアコンがない隔離室はドアを開ければ十分に冷えますが、隔離なので開けっ放しにはできません。このところ夜は涼しいので助かりますが、サポートにアイスノンも買いました。
今回の隔離室暮らしで、たれ目という1頭の猫との距離は縮まっています。多くの猫と暮らしていると、猫どもをつい一頭一頭でなく集団としてとらえてしまいがちですが、一対一で過ごしてみるとその猫のリズムのようなものがよくわかります。本を読む横で、こういうタイミングで鳴いたり、こうやって乗っかって来たり。それはそれで貴重な時間と思います。そして、鼻をなめに口を近づけるたれ目の左目は、焦点がぼけて右目と同じような光を放ちます。
病院の待合で話をした車にぶつかって脚を折った犬の飼い主の夫婦は、あの時、放さなければよかったのにと悔やんでいました。私も、もっと早く病院に連れて来ていたら、ちゃんと隔離していたら膜は破れなかったかも知れない、とよく思います。
しかし帰って来てからのたれ目が、エリザベスカラーが苦しそうでほかの猫と遊びたそうなほかは、以前と変わらず元気なのでいくらかは助かります。たまに隙をみて脱走すると思わぬ鋭い脚を見せるし、片目が見えないことは人間が思うより不自由ではないように思えます。Sさんの話では、片目が義眼の猫などもあまり困ることなく暮らしているそうです。
でも何よりなのは、たれ目は片目が見えなくなっても、命はあるということ。たれ目が帰ってきた日のちょうど一年前の27日は、カロンタンが裏の道で車にはねられた日でした。たれ目には、まだ命があるからアジやサンマも食べられるし、もう少しでほかの猫と遊ぶこともできます。それは何とすばらしいことでしょう。
たれ目の抜糸まであと一週間ほど。まだちょっと不自由な暮らしが続きますが、それもまた味なものです。たれ目と一人と一頭の、シンプルな生活を楽しむつもりです。
ところで、な、カロンタン。一周忌にはいろいろ思い出そうとしていたことがあったけど、カロンタンの孫がとんだことになって考えなくちゃいけないことが多くて思い出せなかったよ。でも、生きてるやつの方が先だよな、カロンタン。
(ニャ)
長くなりました。最後まで付き合っていただいた方、どうもありがとうございます。










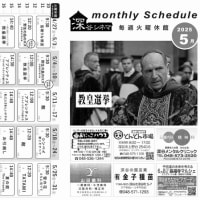

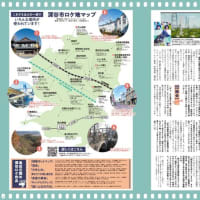













そういえば以前テレビで鼻のないゾウを見ました。
不自由はあるにしても、それなりに生きていけるようです。
なんでもゾウというのは、集団意識がすごく強いので、仲間が助けてくれるそうなんですが、その1頭のために群れに影響が出ると判断されると、すぐさまおいてけぼりにされるそうです。
野生の中で生き抜くにはそうでないといけないのでしょうね。
その後のたれ目は隔離生活にもリズムが出てきて、今週になってからはやつを隔離室に置いて映画をみる余裕もできました。しかし、隔離~しばらく静か~あきて騒ぎ出す~連れて来てほかの猫に接触しないように保持してテレビ前~しばらく静か~あきて騒ぎ出す~再び隔離、の繰り返しのため、なかなか集中できません。それでも、ひとまず順調です。
個人プレーで知られる猫ですが、少なくとも子猫どもを見ていると、寝るのも暴れ出すのもすべて一斉で一種の団体性を感じます。これは人間の子どもを見ていて感じるものに似ています。
保坂和志さんの小説に、猫は種としての意識が強いというような一節がありました。猫も人間も、特に子どものうちに強いこの団体性に興味があります。夏目漱石の息子によると、子どもの頃漱石と祭りに出かけ、兄姉がしたがったことに「僕も」と同調したら火のように怒られたそうです。個人:集団=個性:集団性については、考えることが多いですね。
もっとも、ゾウの集団意識とは別のものと思いますが。自然状態では生きていけないものに手を差し伸べることは、文化というもののもっとも重要な機能の一つでしょう。
小さい動物を虐待するなんて、本当に考えられません
でも、その動物を、だからこそ本当に大切に育てている人がいる。
本当に心温まる話で、目から汗かきまくりでした
そうですか。それは見たかったですね。
ミニチュアダックスを飼う塾OGは、散歩で病気で目が見えなく、耳が聞こえなくなってしまったキャバリアとその飼い主さんと知り合ったそうです。犬の場合は嗅覚が発達しているので、いわれないとわからないほどといいますからたいしたものですね。人間のように不幸を嘆くことなく、持っているものだけで生きていこうとする姿には学ぶべきものがあります。きっと、今しかない動物の強さなのでしょう。
非道な行いをする者があとを絶たないのも事実。ですが、その犬の飼い主のような人も少なくはないと思うと勇気もわいてきます。こちらといえば宮沢賢司のように、「そういうものにわたしはなりたい」とつぶやくだけですが。
また、たれ目の左目は素人が見る限りは順調なよう。今週末か来週に診察に行こうと思っています。
それでは
たれ目ちゃん、大変でしたね。順調なようでなによりです。
本格的ににゃんこたちを飼われているようなので、私のように1匹との関わりとはまた違った見方ができそうですね。
本格的というより、うっかりしてたらどんどん増えてしまったので何とか一緒に生きているといった状況です。しかし、そうなればなったで大変なことも多いけれど、喜ばしいこともけっこうある、というところでしょうか。たくさんねこがいると一頭ではわからなかったことがいろいろわかり、こうしてわかることも、ささやかながら世界の一部だと思います。
まさに今、こねこどもがいつまでも追いかけっこを繰り返す、観衆一人の"夜の運動会"が始まりました。まざりたくってたまらないたれ目も騒ぎ出したので、なだめに行かねば。
それでは、またお越しください。