「状況や文脈の中で、たった1つだけ『ある意味』を指し示しめせる『単語』以外の『意味』を、人間は正確に理解したり共有する事はできない。ソレが言語の限界だ。
状況や文脈なんか関係なく、意味が多数発生してしまう『単語』の意味は共有できているつもりでも本当はできていない。なんとなく『言葉の持つイメージ』だけが伝わるだけだ。
では、『言葉の持つイメージ』とはなんだろうか?
それこそが『うなぎ犬』だ。
うなぎ犬はマンガの中以外にどこにもいないはずなのに、赤塚不二夫の『バカボン』の中には、確かにいるとイメージされている。
ホームズもワトソンも、坊ちゃんもラムちゃんも、どこにもいないはずなのに、仮にいるというイメージを我々は共有している。それが、『言葉の持つイメージ』だ。『個性』という単語も、正確な意味などどこにもないのに、まるでフィクションの登場人物が現実にいるかのように、まるで意味があるかのようにイメージして、『ある』と錯覚してしまう。
正確な意味を共有できずに、ただぼんやりとしたこんなかんじってイメージのみを共有しているだけの『単語』は多く、この手の言葉が混じると人はいかがわしさやダマされている感じを受けるが、そもそも、自分や誰もがなんとなく抱いているだけのイメージに正確に突っ込める手段もなく、なんだかなぁと思いながらも普通の人は口をつぐんでいる。
だが、イメージに惑わされる馬鹿な人が多いのも事実だ。
ソレは、ヲタクがリアルに居もしないキャラに萌えて『モエー』と言っているのに等しい。意味がない言葉にゃ意味がないって事が分からなくて、分からないからすごいんだと勝手に思い込んでる。
かって、『ボーダー』の蜂須賀は、イメージのはらむ危険性について常に警鐘を鳴らしていた。だが、俺は蜂須賀の『アッチ側・コチラ側』という二極化に我慢できず袂を分けた。
何故なら俺は分ける事でしか人間は物事を理解できないが、分ける事によって多くの誤解も生まれると考えるからだ。
ようするに、理解する方法と同じ仕方で人間は誤解もする。理解も誤解も同じ方式なのだ。
分ける本人に理解と誤解の差はない。分けたから分かる。ただそれだけ。根本的に理解と誤解の差はほとんどない。
蜂須賀はすごい男だ。
俺は彼からの影響を多分に受けた。
蜂須賀のメッセージだけは今も心に残る。目をつぶれば砂漠に白い雪が舞う景色、そこにボブの歌が流れる」
「へー、蜂須賀さんって人がそんなに死神へ影響を与えたんだ。ところでその人は今なにしてんの?」
「ナニしてんのって、だから蜂須賀は『ボーダー』ってマンガの主人公なんだよ」
「なんだ。しょせんマンガ。それだってイメージじゃん」










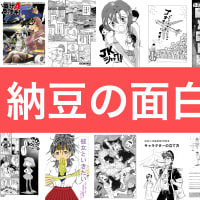

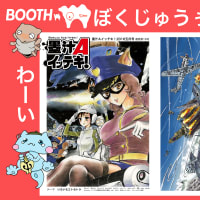
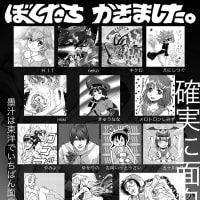


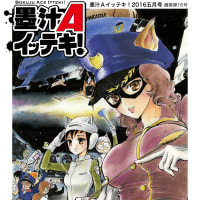



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます