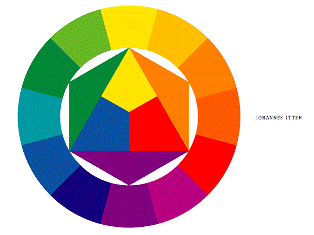「流行語大賞と言葉と文字」 久保野 和行

年末恒例のユーキャン新語流行語大賞が12月2日に発表されました。面白いのは、その年の世相を反映した言葉が躍動していることです。今年は30回目を迎えるこのイベントで、初めて4つの大賞が選ばれたことです。
「今でしょ!」はテレビの予備校コマーシャル画面での出現語でした。
「じぇじぇじぇ」はNHKの朝の連続ドラマ“あまちゃん”の中で語られた言葉でした。
「倍返し」テレビドラマの内容が、バブル末期に大手銀行に入行した主人公“半沢直樹”は劇中で決める言葉として生まれました。
「お・も・て・な・し」はオリンピック招致活動の最終プレゼンで日本社会に根づく歓待の精神を日本語で紹介した言葉でした。
このように人間が持っている最大のスキルは言葉であり、同時に文字である。叡智の塊である言葉と文字は、人類はどのようにして生まれ発展していったんだろうと考えるとおもしろい。
人間が動物との差別化が進むのは、数万年前に言葉を持つことにより人類が登場する。これを別名では第一次情報革命と認識する。
言葉を持つことで知恵が発達し、同時に多くの人々との接触が行われ、現在流にいえばコミュニケーションスキルが向上した。そこで、次に突き当たった壁が、言葉の保存・保管管理方法に行き着いた。そこで約3千年前あたりに文字が考案された。これを第二次情報革命となった。
これが文字を持ったことにより歴史というストリーが生まれ進化することです。
そして、ここからが面白いのは当然ながら第三次情報革命が生まれ、必然的に飛躍的に進化することになつたのが。これが何と、“印刷”なのです。
1450年にグーテンベルクが葡萄の絞り機から印刷機を発明した。このことによって従来、なかなか情報が得られなかった宗教の情報を知ることができた。それがキリスト教の「四十二行聖書」がヨハネス・グーテンベルクによって180部印刷された。現存するのは世界で48部セットであり、アジア地域では日本の慶応義塾大学に唯一ある。
大量の複写物を製造する印刷技術は、文明・文化の拡散であり、同時に情報の収集に役立った。
そして今日では第四次情報革命に入っている。いわずもだがインターネット社会の出現である。インターネットの登場は無限の情報収集が可能になった。それにともない、情報にはボーダレス化(国境が無い状態)が進み、多言語でもIT技術によってリアルタイムに翻訳ができる技術が構築されている。
情報が大量に、なおかつ無限大に得られる環境であるが、人々の感覚では、快適空間での言葉は、必要以上の情報は要らないだろうし、その時代背景が、その時々の流行語を生む出す素地があると思う。

年末恒例のユーキャン新語流行語大賞が12月2日に発表されました。面白いのは、その年の世相を反映した言葉が躍動していることです。今年は30回目を迎えるこのイベントで、初めて4つの大賞が選ばれたことです。
「今でしょ!」はテレビの予備校コマーシャル画面での出現語でした。
「じぇじぇじぇ」はNHKの朝の連続ドラマ“あまちゃん”の中で語られた言葉でした。
「倍返し」テレビドラマの内容が、バブル末期に大手銀行に入行した主人公“半沢直樹”は劇中で決める言葉として生まれました。
「お・も・て・な・し」はオリンピック招致活動の最終プレゼンで日本社会に根づく歓待の精神を日本語で紹介した言葉でした。
このように人間が持っている最大のスキルは言葉であり、同時に文字である。叡智の塊である言葉と文字は、人類はどのようにして生まれ発展していったんだろうと考えるとおもしろい。
人間が動物との差別化が進むのは、数万年前に言葉を持つことにより人類が登場する。これを別名では第一次情報革命と認識する。
言葉を持つことで知恵が発達し、同時に多くの人々との接触が行われ、現在流にいえばコミュニケーションスキルが向上した。そこで、次に突き当たった壁が、言葉の保存・保管管理方法に行き着いた。そこで約3千年前あたりに文字が考案された。これを第二次情報革命となった。
これが文字を持ったことにより歴史というストリーが生まれ進化することです。
そして、ここからが面白いのは当然ながら第三次情報革命が生まれ、必然的に飛躍的に進化することになつたのが。これが何と、“印刷”なのです。
1450年にグーテンベルクが葡萄の絞り機から印刷機を発明した。このことによって従来、なかなか情報が得られなかった宗教の情報を知ることができた。それがキリスト教の「四十二行聖書」がヨハネス・グーテンベルクによって180部印刷された。現存するのは世界で48部セットであり、アジア地域では日本の慶応義塾大学に唯一ある。
大量の複写物を製造する印刷技術は、文明・文化の拡散であり、同時に情報の収集に役立った。
そして今日では第四次情報革命に入っている。いわずもだがインターネット社会の出現である。インターネットの登場は無限の情報収集が可能になった。それにともない、情報にはボーダレス化(国境が無い状態)が進み、多言語でもIT技術によってリアルタイムに翻訳ができる技術が構築されている。
情報が大量に、なおかつ無限大に得られる環境であるが、人々の感覚では、快適空間での言葉は、必要以上の情報は要らないだろうし、その時代背景が、その時々の流行語を生む出す素地があると思う。