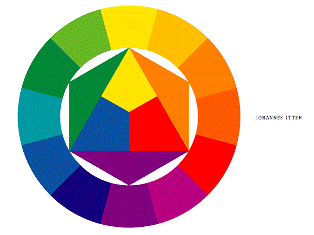[印刷]の今とこれからを考える 「印刷図書館クラブ」月例会報告(平成25年9月度会合より)
《6月度記事参照》
●中小印刷会社には「未来」が待っている
アメリカの印刷業界団体PIAが先頃まとめた特別報告書(文末表記)が、「未来を育てる―中小印刷業は生き残れるか?―」をテーマに採り上げている。日米の違いがあるとはいえ、同じように圧倒的多数の中小印刷会社からなる日本の印刷業界にとって、学ぶべきところは少なくない。統計的な数字については、例によって原本をご覧いただくとして、報告書は冒頭に「Small is Beautiful」(小さい会社は優れている)と謳い、印刷市場は激変したという認識のもとでも、「中小印刷会社は実現可能な未来をもっている」と力説している。中小印刷会社は大規模会社と十分に競争でき、予測可能な未来の印刷産業のなかで、重要な存在であり続けるだろうとする。PIAが着目しているのは、①中小印刷会社が印刷産業のなかで占めるポジション、②経営における“粘り強さ”、③売上げ構成の多様性――である。
●競争優位性は企業規模とは関係ない
中小規模の印刷会社が優れているとする根拠として、大企業を含む印刷産業では何より「規模の経済」が働かないことを挙げている。多品種小ロット製品の個別受注生産という産業特性から、年間の印刷ユニット数が増えたとしても、ユニット当たりの製造コストを一貫して引き下げられない。その分、収益を拡大できない。最初のうちは稼働率向上など生産の効率化でコストを引き下げることができても、ある程度、ユニット数が増えてくると、人件費等が負担となってコストカーブが落ちていかない。さらに生産量が増えると、設備等の固定費が増大して逆に製造コストが高まってしまうのが実情だ。新技術の生産システムに投資すれば、全体としての製造コストは低減できるが、その点は企業規模にかかわらず同じ条件下にある。中小印刷会社は大会社に対して“絶対的に不利”というわけではないのだ。
●小規模ならでの企業特性が強みとなる
印刷業にはなぜ「規模の経済」の理論が適用されないのかについて、もっと詳しくみていくと、印刷業ではライン生産のような連続プロセスよりも、工程ごとに個別生産をおこなうジョブ・ショップ方式の製造プロセスを利用して、中小印刷会社でも大企業と同程度の生産効率で印刷物をつくっている。しかも単なる製造業ではなく、製造とサービスが組み合わさった業態でもある。その分、中小印刷会社は機動性に優れ、顧客(とくに経営者層)と親密な関係を維持することができている。小規模な印刷会社の経営者は、より起業家的であり、必要性が生じたときには迅速に対応できる強みももっている。中小印刷会社は小口発注の中小顧客と、大きな印刷会社は大口発注の大規模な顧客企業と必然的に取引する。この“調和”はお互いに直接競争しないことを意味する。中小印刷会社は、企業規模を拡大して競争力を強化することよりも、事業内容の質を高めることが重要である。コストを低減する新技術、ビジネスプロセスに投資し続ける必要はあるが、これらは規模を拡大しないでも実践可能であり、中小印刷会社が印刷産業のなかで不可欠な存在として生き続ける基本的条件となる。
●企業規模の問題は経営能力より重要でない
アメリカの中小印刷会社の場合、ビジネスプロセスに占める付帯サービスの割合は10~13%程度に過ぎず、それと比べプリプレスと印刷工程への依存度が高い。付帯サービスへの進出に躊躇している分、印刷物製造が主力となっている。それにもかかわらず、生産システムへの投資やビジネスプロセスの改革に遅れ、中小印刷会社の売上高利益率は大会社に及ばない。「適切な対応を実行しているプロフィットリーダー格の小企業は、大企業のリーダーより高い収益性を達成している。企業規模の問題は、経営能力よりも重要度が低いといった方がよい」というのがPIAの見立てだ。強力な競争優位性と緊密な顧客関係から生まれる価格設定力の分析でも「中小印刷会社の方がむしろ大企業より価格の引き上げに成功している」と評価する。
●顧客にどんな価値を与えられるかから始まる
中小印刷会社が成功するための鍵(KFS)は何か? PIAでは「(ソリューションを提供することによって)顧客に付加価値を移転する重要性に気付くことだ」として、次のような課題を列挙する。①印刷物の製造から付帯サービス、情報伝達・問題解決策の提供へ、印刷マネジメントサービスへと自ら変化する、②優れた代替品や競争のないユニークな製品・サービスで、強力な需要を創出する、③必須の戦略として、自社にとってうま味のある製品別ニッチあるいはバーチカルセグメント(限定されたビジネスプロセス)に特化する、④価格設定力を強めることのできる独自の付帯サービスを提供する――こと。さらには、⑤自社の「顧客」をよく知る、⑤特化した事業分野で多様な付帯サービスを提供する、⑥顧客との間でwin-winの関係を築く、⑦顧客への認識と提供する製品・サービスを土台に印刷会社としてのブランド力を磨く、⑧コスト志向より需要志向でいく――なども指摘している。それには、情報を共有し能力開発を怠らず、社員の遂行能力を正しく評価できる包括的な組織体制となることが前提である。
※本稿は、下記の参考資料を下地にして作成しています。
PIA特別報告書[Sizing up the Future: Can Small and Medium Printers Survive?]
●事業理念と行動力で“分”に応じたビジネスを
PIAの資料をみるまでもなく、日本でも最近、小規模企業がやっているような印刷物が伸びている。パソコンとプリンタが普及した時代であっても、素人には手の出ない高品質な小モノ印刷物、特殊な印刷物、後加工を必要とする印刷物などだ。加工度を上げて高付加価値化を実現するノウハウは、やはり印刷業界ならではの財産であることを裏付けている。データを活かして電子メディアを逆利用できる分野は限りなくある。このような視点で工夫を凝らしている印刷会社に対する需要が増えている。利益を出していける仕組みを企業として確立し、“分”に応じたビジネスをおこなうことである。そのためには、事業に関する理念と行動力に確固たる見識が伴っていなければならない。幸いにして、印刷業は地産地消型の産業であり、それぞれの“場”で臨機応変の機動力を存分に発揮できる土壌がある。
●入口はプリントマネージャー、出口は分化(特化)で
印刷会社は自らの意思で、デジタルデータを駆使できる終始面倒見のよいプリントマネージャーになるべきである。余裕が出てきたらクリエイティブな仕事を手掛ければよい。新規参入してきた専門会社からの依頼を、下請けのようなかたちで印刷物として“出力”しているだけではあまりにももったいない。業態の異なる印刷会社同士でコラボレーションして、全体でシナジー効果を探るような仕組みをつくれれば、プリントマネージャーとしての窓口機能も力強いものになる。顧客側の業界はどんどん若返り新しいビジネスを模索している。印刷の仕事をとりやすい環境が生まれてきているともいえる。それに負けずに印刷産業全体も変化すべきときだ。ビジネスは一般的に普遍-拡大-成熟-分化-新規参入の道を辿る。印刷産業自身も今こそ上手に分化する必要がある。そうすれば小さな印刷会社であっても、垂直分業が進むビジネスの世界の隙間(ニッチ)を掴むことができ、主力の座につけるはずである。
(以上)
《6月度記事参照》
●中小印刷会社には「未来」が待っている
アメリカの印刷業界団体PIAが先頃まとめた特別報告書(文末表記)が、「未来を育てる―中小印刷業は生き残れるか?―」をテーマに採り上げている。日米の違いがあるとはいえ、同じように圧倒的多数の中小印刷会社からなる日本の印刷業界にとって、学ぶべきところは少なくない。統計的な数字については、例によって原本をご覧いただくとして、報告書は冒頭に「Small is Beautiful」(小さい会社は優れている)と謳い、印刷市場は激変したという認識のもとでも、「中小印刷会社は実現可能な未来をもっている」と力説している。中小印刷会社は大規模会社と十分に競争でき、予測可能な未来の印刷産業のなかで、重要な存在であり続けるだろうとする。PIAが着目しているのは、①中小印刷会社が印刷産業のなかで占めるポジション、②経営における“粘り強さ”、③売上げ構成の多様性――である。
●競争優位性は企業規模とは関係ない
中小規模の印刷会社が優れているとする根拠として、大企業を含む印刷産業では何より「規模の経済」が働かないことを挙げている。多品種小ロット製品の個別受注生産という産業特性から、年間の印刷ユニット数が増えたとしても、ユニット当たりの製造コストを一貫して引き下げられない。その分、収益を拡大できない。最初のうちは稼働率向上など生産の効率化でコストを引き下げることができても、ある程度、ユニット数が増えてくると、人件費等が負担となってコストカーブが落ちていかない。さらに生産量が増えると、設備等の固定費が増大して逆に製造コストが高まってしまうのが実情だ。新技術の生産システムに投資すれば、全体としての製造コストは低減できるが、その点は企業規模にかかわらず同じ条件下にある。中小印刷会社は大会社に対して“絶対的に不利”というわけではないのだ。
●小規模ならでの企業特性が強みとなる
印刷業にはなぜ「規模の経済」の理論が適用されないのかについて、もっと詳しくみていくと、印刷業ではライン生産のような連続プロセスよりも、工程ごとに個別生産をおこなうジョブ・ショップ方式の製造プロセスを利用して、中小印刷会社でも大企業と同程度の生産効率で印刷物をつくっている。しかも単なる製造業ではなく、製造とサービスが組み合わさった業態でもある。その分、中小印刷会社は機動性に優れ、顧客(とくに経営者層)と親密な関係を維持することができている。小規模な印刷会社の経営者は、より起業家的であり、必要性が生じたときには迅速に対応できる強みももっている。中小印刷会社は小口発注の中小顧客と、大きな印刷会社は大口発注の大規模な顧客企業と必然的に取引する。この“調和”はお互いに直接競争しないことを意味する。中小印刷会社は、企業規模を拡大して競争力を強化することよりも、事業内容の質を高めることが重要である。コストを低減する新技術、ビジネスプロセスに投資し続ける必要はあるが、これらは規模を拡大しないでも実践可能であり、中小印刷会社が印刷産業のなかで不可欠な存在として生き続ける基本的条件となる。
●企業規模の問題は経営能力より重要でない
アメリカの中小印刷会社の場合、ビジネスプロセスに占める付帯サービスの割合は10~13%程度に過ぎず、それと比べプリプレスと印刷工程への依存度が高い。付帯サービスへの進出に躊躇している分、印刷物製造が主力となっている。それにもかかわらず、生産システムへの投資やビジネスプロセスの改革に遅れ、中小印刷会社の売上高利益率は大会社に及ばない。「適切な対応を実行しているプロフィットリーダー格の小企業は、大企業のリーダーより高い収益性を達成している。企業規模の問題は、経営能力よりも重要度が低いといった方がよい」というのがPIAの見立てだ。強力な競争優位性と緊密な顧客関係から生まれる価格設定力の分析でも「中小印刷会社の方がむしろ大企業より価格の引き上げに成功している」と評価する。
●顧客にどんな価値を与えられるかから始まる
中小印刷会社が成功するための鍵(KFS)は何か? PIAでは「(ソリューションを提供することによって)顧客に付加価値を移転する重要性に気付くことだ」として、次のような課題を列挙する。①印刷物の製造から付帯サービス、情報伝達・問題解決策の提供へ、印刷マネジメントサービスへと自ら変化する、②優れた代替品や競争のないユニークな製品・サービスで、強力な需要を創出する、③必須の戦略として、自社にとってうま味のある製品別ニッチあるいはバーチカルセグメント(限定されたビジネスプロセス)に特化する、④価格設定力を強めることのできる独自の付帯サービスを提供する――こと。さらには、⑤自社の「顧客」をよく知る、⑤特化した事業分野で多様な付帯サービスを提供する、⑥顧客との間でwin-winの関係を築く、⑦顧客への認識と提供する製品・サービスを土台に印刷会社としてのブランド力を磨く、⑧コスト志向より需要志向でいく――なども指摘している。それには、情報を共有し能力開発を怠らず、社員の遂行能力を正しく評価できる包括的な組織体制となることが前提である。
※本稿は、下記の参考資料を下地にして作成しています。
PIA特別報告書[Sizing up the Future: Can Small and Medium Printers Survive?]
●事業理念と行動力で“分”に応じたビジネスを
PIAの資料をみるまでもなく、日本でも最近、小規模企業がやっているような印刷物が伸びている。パソコンとプリンタが普及した時代であっても、素人には手の出ない高品質な小モノ印刷物、特殊な印刷物、後加工を必要とする印刷物などだ。加工度を上げて高付加価値化を実現するノウハウは、やはり印刷業界ならではの財産であることを裏付けている。データを活かして電子メディアを逆利用できる分野は限りなくある。このような視点で工夫を凝らしている印刷会社に対する需要が増えている。利益を出していける仕組みを企業として確立し、“分”に応じたビジネスをおこなうことである。そのためには、事業に関する理念と行動力に確固たる見識が伴っていなければならない。幸いにして、印刷業は地産地消型の産業であり、それぞれの“場”で臨機応変の機動力を存分に発揮できる土壌がある。
●入口はプリントマネージャー、出口は分化(特化)で
印刷会社は自らの意思で、デジタルデータを駆使できる終始面倒見のよいプリントマネージャーになるべきである。余裕が出てきたらクリエイティブな仕事を手掛ければよい。新規参入してきた専門会社からの依頼を、下請けのようなかたちで印刷物として“出力”しているだけではあまりにももったいない。業態の異なる印刷会社同士でコラボレーションして、全体でシナジー効果を探るような仕組みをつくれれば、プリントマネージャーとしての窓口機能も力強いものになる。顧客側の業界はどんどん若返り新しいビジネスを模索している。印刷の仕事をとりやすい環境が生まれてきているともいえる。それに負けずに印刷産業全体も変化すべきときだ。ビジネスは一般的に普遍-拡大-成熟-分化-新規参入の道を辿る。印刷産業自身も今こそ上手に分化する必要がある。そうすれば小さな印刷会社であっても、垂直分業が進むビジネスの世界の隙間(ニッチ)を掴むことができ、主力の座につけるはずである。
(以上)