■民法に根強く残る「家父長制」
「離婚から三百日以内に誕生した子は前夫の子」。民法七七二条の規定だ。これがネックとなって、子どもが「無戸籍」な状態の家族たちがいる。
そんな人たちが法務省や国会議員に民法改正を訴えた。問題は「家」制度に根ざす。ただ、現行民法による親子関係の不合理は、この「三百日規定」に限らないようだ。
■親子関係不存在年間で4000件近く
二十五日に法務省民事局や議員事務所を回り、窮状を訴えたのは大阪市の特定非営利活動法人(NPO法人)「親子法改正研究会」代表理事で、兵庫県議の井戸正枝さん(四一)ら。
井戸さんは、前夫と数年の別居を経て二〇〇二年に離婚した。離婚成立から二百六十五日目、現在の夫との間に息子(四つ)を出産。だが、市役所に前夫を父とする出生届を提出するように言われ、驚いたという。
「当初、弁護士といっても『法は法』という反応で弁護士抜きの本人訴訟で闘わざるを得なかった。孤独だった」(井戸さん)。
結局、現在の夫を相手取った「強制認知」の訴訟によって子どもの戸籍を得たが「約一年間、その子には戸籍はなかった」と振り返る。
その後、NPO法人を設立したが「妊娠中だが、そんな規定は知らなかった」など不安を訴える声が殺到した。
親子関係不存在という出生届は年間、三千五百-四千件あるが「大半が私と同じケース」と井戸さんは語る。
各地で「無戸籍」なまま育った子どもたちが海外への修学旅行などで旅券が必要となり、そこから争うケースも出ている。
「行政、裁判所も地域によって扱いが違う。裁判をやるといっても、弁護士費用だけで最低三十万円はかかる。まして乳飲み子の育児を抱え、生活に追われ、容易ではない。やはり、法自体を変えてほしい」
こうした現行法と家族に関する意識の変化などによる実態との乖離は「三百日規定」のみではない。
■「婚外子差別」「6ヶ月の再婚禁止規定」も
まず、再婚する際にも問題はある。女性にのみ「離婚後、六カ月再婚を禁止する」と課した民法七三三条の規定がそれだ。「子の父を確定する困難を避けること」がその理由とされている。
しかし、民法七七二条には「結婚二〇一日以後に生まれた子は現在の夫の子」という規定もあり、父親確定のためなら再婚禁止期間は百日となる。
また、夫の生死が三年以上不明という理由で離婚、再婚する場合でも七三三条は適用される。
■国際カップルで無国籍児も増加
「婚外子」差別も長く争われている。欧米では法的な差別はほぼ撤廃されているが、日本では「婚外子の法定相続分は婚内子の二分の一」(民法九〇〇条)。
東京高裁は一九九三年に「法の下の平等」(憲法一四条)に反すると判断。国際人権委員会も同年、日本政府に改善を勧告した。
だが、九五年に最高裁は「立法裁量権の範囲内で合憲」と高裁判決を逆転。ただ、その最高裁も〇三年には「法改正が立法府より可及的速やかになされることを期待する」と同様の判決で付言を添えている。
また、民法以外でも国籍法で、父親が日本人、母親が外国人で結婚していない場合、父親が出生前に認知しない限り、子どもは日本国籍を得られないと定められている。
増える無戸籍の子、改正急務
この仕組みを知らずに出産後、父親が認知しても結婚しない限り、国籍は取れず「無戸籍」状態の子どもが増えている。
井戸さんはこうした数々の問題を「『家』制度や『家父長制』を引きずった遺物ともいえる法の存在が問題」と指摘する。「現実に困っている人々の実際の例を突きつけていきたい」
一方、長勢甚遠法相は二十六日の記者会見で前日の井戸さんらの行動を受け、「さまざまなケースがあると思うので調べさせる」と話した。
井戸さんは「実態調査に乗り出してくれそう」と受け止めているが、法務省の事務方は「実態調査という意味ではないと解釈している」と話している。
『東京新聞』(2007/1/27)ニュースの追跡
「離婚から三百日以内に誕生した子は前夫の子」。民法七七二条の規定だ。これがネックとなって、子どもが「無戸籍」な状態の家族たちがいる。
そんな人たちが法務省や国会議員に民法改正を訴えた。問題は「家」制度に根ざす。ただ、現行民法による親子関係の不合理は、この「三百日規定」に限らないようだ。
■親子関係不存在年間で4000件近く
二十五日に法務省民事局や議員事務所を回り、窮状を訴えたのは大阪市の特定非営利活動法人(NPO法人)「親子法改正研究会」代表理事で、兵庫県議の井戸正枝さん(四一)ら。
井戸さんは、前夫と数年の別居を経て二〇〇二年に離婚した。離婚成立から二百六十五日目、現在の夫との間に息子(四つ)を出産。だが、市役所に前夫を父とする出生届を提出するように言われ、驚いたという。
「当初、弁護士といっても『法は法』という反応で弁護士抜きの本人訴訟で闘わざるを得なかった。孤独だった」(井戸さん)。
結局、現在の夫を相手取った「強制認知」の訴訟によって子どもの戸籍を得たが「約一年間、その子には戸籍はなかった」と振り返る。
その後、NPO法人を設立したが「妊娠中だが、そんな規定は知らなかった」など不安を訴える声が殺到した。
親子関係不存在という出生届は年間、三千五百-四千件あるが「大半が私と同じケース」と井戸さんは語る。
各地で「無戸籍」なまま育った子どもたちが海外への修学旅行などで旅券が必要となり、そこから争うケースも出ている。
「行政、裁判所も地域によって扱いが違う。裁判をやるといっても、弁護士費用だけで最低三十万円はかかる。まして乳飲み子の育児を抱え、生活に追われ、容易ではない。やはり、法自体を変えてほしい」
こうした現行法と家族に関する意識の変化などによる実態との乖離は「三百日規定」のみではない。
■「婚外子差別」「6ヶ月の再婚禁止規定」も
まず、再婚する際にも問題はある。女性にのみ「離婚後、六カ月再婚を禁止する」と課した民法七三三条の規定がそれだ。「子の父を確定する困難を避けること」がその理由とされている。
しかし、民法七七二条には「結婚二〇一日以後に生まれた子は現在の夫の子」という規定もあり、父親確定のためなら再婚禁止期間は百日となる。
また、夫の生死が三年以上不明という理由で離婚、再婚する場合でも七三三条は適用される。
■国際カップルで無国籍児も増加
「婚外子」差別も長く争われている。欧米では法的な差別はほぼ撤廃されているが、日本では「婚外子の法定相続分は婚内子の二分の一」(民法九〇〇条)。
東京高裁は一九九三年に「法の下の平等」(憲法一四条)に反すると判断。国際人権委員会も同年、日本政府に改善を勧告した。
だが、九五年に最高裁は「立法裁量権の範囲内で合憲」と高裁判決を逆転。ただ、その最高裁も〇三年には「法改正が立法府より可及的速やかになされることを期待する」と同様の判決で付言を添えている。
また、民法以外でも国籍法で、父親が日本人、母親が外国人で結婚していない場合、父親が出生前に認知しない限り、子どもは日本国籍を得られないと定められている。
増える無戸籍の子、改正急務
この仕組みを知らずに出産後、父親が認知しても結婚しない限り、国籍は取れず「無戸籍」状態の子どもが増えている。
井戸さんはこうした数々の問題を「『家』制度や『家父長制』を引きずった遺物ともいえる法の存在が問題」と指摘する。「現実に困っている人々の実際の例を突きつけていきたい」
一方、長勢甚遠法相は二十六日の記者会見で前日の井戸さんらの行動を受け、「さまざまなケースがあると思うので調べさせる」と話した。
井戸さんは「実態調査に乗り出してくれそう」と受け止めているが、法務省の事務方は「実態調査という意味ではないと解釈している」と話している。
『東京新聞』(2007/1/27)ニュースの追跡











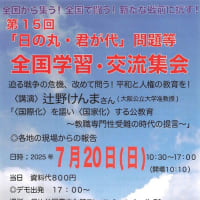

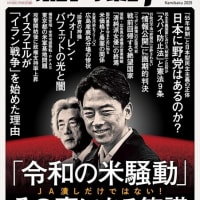
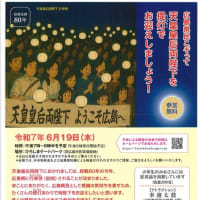


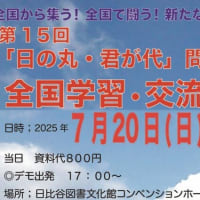





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます