結局のところ初期反射音ってどうすればいいんだろうというのを調べたりしていると、
正直オーディオ系界隈だけ調べてもどうして良いのかが分からない。
十人十色でこれが良くて他がダメだめと言ってしまって、結局自分はどうすれば良いのかを考察する手がかりに乏しいのだ。
他分野をということでまずはコンサートホールの音響関係で調べると、
初期反射音は方向感、定位を補強するなので積極的に利用するようだ。
表面に凹凸を付けずにそのまま押し出す。天井から音響板を付けて距離を短くしたり
側壁を押し出す感じにして初期反射効果を強調するといいと考えることがあるらしい。
大空間での初期反射音の扱いは分かったが、あくまで参考程度。
小規模のリスニングルームには使えない。
次に音楽スタジオ関係で調べてみると、自分が知りたかった知見がてんこ盛り。
良い悪いではなく、こうなってるからこうするとこうなるよ、という科学的な考察が蓄積されている。
オーディオ界隈で紹介されていた理論も非常に分かりやすく解説されてもいた。
スタジオ自体はリスニングルームより若干広いスペースを相手にしており、楽しく聴くより正確な音を聴くことが重視されるため、スタジオの真似をすれば良いわけではない。
だが、自分は室内の響かせ方をどうすべきかという手掛かりは、まさしくここにあったと思える。
そもそも15年もオーディオやっていて防音室まで作ったのに、なぜそっちの方面に首を突っ込まず、ろくに勉強しなかったのかと我ながら不勉強にもほどがあるが、遅いにしろこれからのためにいろいろな知見を収集することにしている。
あとで整理するためにTipsを以下に。
引用:https://www.japrs.or.jp/pdf/news_2009_No2.pdf
日本音楽スタジオ協会(以下JAPRS)の2009年の雑誌。NHKのスタジオを2部屋改修した際のレポートが掲載されている。5.1chのスタジオなのでまるまる使えるわけでは無いのだが。
1件はお馴染み日東紡の円状拡散体と吸音を組み合わせたスタジオ

ここでの知見
広くスタジオで行われ、石井式でも使われている反射部と吸音部を組み合わせる方法だと、リスニングポイントが少し変わるだけで特性が大きく変化してしまう。
反射と吸音の組み合わせだと一次反射によるコムフィルタ効果により直接音にカラーリングされてしまうが、拡散と吸音だとそれが起こらない。
拡散と吸音なので、一次反射は少なく、残響はあるが短めという仕上がりになっているようだ。
2件目はソナという会社が作ったスタジオ

初期反射音を積極的に利用したスタジオということだ。まさに自分が参考にしたい情報が沢山詰まっていそうな感じだ。
ここでの知見
初期反射音をコントロールルームで活用するのは未だに賛否両論がある(そっちの界隈でも定説はないようだ。という意味では家庭用オーディオでも好きに扱っても不正解はないということになる)。
ただ世代の新しいスタジオは拡散で一次反射音をキャンセルしてしまう傾向が多いようだ。
Reflection Free Zoneという概念があるらしく正面と側面の一次反射面をピンポイントに吸音し、後壁を拡散させることで初期反射をなくしてしまいつつ、残響は生じさせる考えのようだ。
Nashville’s Blackbird Studio Cというスタジオは贅沢に四方八方を細かい拡散体で覆ってしまっている。一次反射音はキャンセルされ残響となり、無響室に控えめの残響が付与されたような音になっているそうだ。Dolby atmos 9.1.6chののリファレンスにもなっているらしい。

つまるところ一次反射面を含めて拡散体を沢山置くような部屋というのは現代的モニターライクな部屋であり、そういう音が出せるということになる。
(自分の中でモニターライクな部屋=吸音の多い部屋だという不勉強な概念があったが新しく塗り変わった。)
モニターライクな音に関して否定的な言い方をすれば、拡散体を沢山置きすぎると正しい音で鳴るが、神経質だったり、面白みが無い音になる可能性を秘めている。QRDや日東紡の様な高級調音オブジェはそういう方向のグッズであることは認識して使う必要がある。
ただ、一次反射をそのまま出すとコムフィルタ効果によりカラレーションが付いてしまい、モニターには適さない音になる。
ソナはこのスタジオを設計する際に一次反射を活用しつつカラレーションさせない手法として反射はするが反射の際に波形を変えてしまい、直接音と干渉しないようにしてコムフィルタ現象を生じさせにくくするという手法で解決させたようだ。
これは是非倣いたいメソッドである。
どうするかというと反射効果の強い拡散体を反射板として使うことで波形の相似性を解消させるとのことだ。

こんな拡散体売ってないし試験管状に木材を加工できないので作るのも難しいし真似できないじゃないかと途方にくれていたが、
理屈的には反射効果の強い拡散体であればいいので、全く同じ形で無くてもいいのかもしれない。
black birdのように細かい凸凹ではなく、大きさの粗い拡散パネルであれば反射効果の強い拡散体ということになり同じ効果が期待できるかも知れない。
このスタジオの音はモニターとして有用な特性を獲得しながらも一次反射音が残っているせいかガッツのある音、芯のある音だそうだ。自分の志向としてはそういう音を目指したいのかもしれない。
別の比較的新しい記事でソナでは同じ非相関一次反射を目的にして東映のatmos用のスタジオやカプコンのスタジオで平面に正方形の穴をランダムに開けたパネルを設置していたようだ。こっちの方が最新版なのだろうか。自作するならこっちの方が作りやすそうだ。


気になったので自分の部屋のインパルス応答を測定。今までも測定していたようなのだが、
理解できていなかったのでスルーしていた。
割と読み方が簡単だし測定結果があまりぶれないので再現性が高く、素人でも有用な測定法のようだ。

初期反射面が吸音部だったり調音パネルを置いたりクッションを置いたりと割と消音させたつもりなのだが、初期反射はいたって普通にありそうに見える。決して少なくはないようだ。
そして-60dbの残響時間はせいぜい300msくらい。短すぎて話にならないほどではないが、割とモニターに近いデッド気味の環境だった。
シアター面のスクリーンとその背面にある吸音材や部屋の中央にある足置きと自分の足(測定中は毛布で代用)などが追加の吸音作用を発揮して想定以上にデッドになっているのかもしれない。
もっとライブでもいいくらいなので吸音部を一部潰して非相関一次反射部などの機構を入れてもいいのかもしれない。
ソナのホームページに行ったところさらに興味深い記事もあったので後日Tipsを纏める予定。
正直オーディオ系界隈だけ調べてもどうして良いのかが分からない。
十人十色でこれが良くて他がダメだめと言ってしまって、結局自分はどうすれば良いのかを考察する手がかりに乏しいのだ。
他分野をということでまずはコンサートホールの音響関係で調べると、
初期反射音は方向感、定位を補強するなので積極的に利用するようだ。
表面に凹凸を付けずにそのまま押し出す。天井から音響板を付けて距離を短くしたり
側壁を押し出す感じにして初期反射効果を強調するといいと考えることがあるらしい。
大空間での初期反射音の扱いは分かったが、あくまで参考程度。
小規模のリスニングルームには使えない。
次に音楽スタジオ関係で調べてみると、自分が知りたかった知見がてんこ盛り。
良い悪いではなく、こうなってるからこうするとこうなるよ、という科学的な考察が蓄積されている。
オーディオ界隈で紹介されていた理論も非常に分かりやすく解説されてもいた。
スタジオ自体はリスニングルームより若干広いスペースを相手にしており、楽しく聴くより正確な音を聴くことが重視されるため、スタジオの真似をすれば良いわけではない。
だが、自分は室内の響かせ方をどうすべきかという手掛かりは、まさしくここにあったと思える。
そもそも15年もオーディオやっていて防音室まで作ったのに、なぜそっちの方面に首を突っ込まず、ろくに勉強しなかったのかと我ながら不勉強にもほどがあるが、遅いにしろこれからのためにいろいろな知見を収集することにしている。
あとで整理するためにTipsを以下に。
引用:https://www.japrs.or.jp/pdf/news_2009_No2.pdf
日本音楽スタジオ協会(以下JAPRS)の2009年の雑誌。NHKのスタジオを2部屋改修した際のレポートが掲載されている。5.1chのスタジオなのでまるまる使えるわけでは無いのだが。
1件はお馴染み日東紡の円状拡散体と吸音を組み合わせたスタジオ

ここでの知見
広くスタジオで行われ、石井式でも使われている反射部と吸音部を組み合わせる方法だと、リスニングポイントが少し変わるだけで特性が大きく変化してしまう。
反射と吸音の組み合わせだと一次反射によるコムフィルタ効果により直接音にカラーリングされてしまうが、拡散と吸音だとそれが起こらない。
拡散と吸音なので、一次反射は少なく、残響はあるが短めという仕上がりになっているようだ。
2件目はソナという会社が作ったスタジオ

初期反射音を積極的に利用したスタジオということだ。まさに自分が参考にしたい情報が沢山詰まっていそうな感じだ。
ここでの知見
初期反射音をコントロールルームで活用するのは未だに賛否両論がある(そっちの界隈でも定説はないようだ。という意味では家庭用オーディオでも好きに扱っても不正解はないということになる)。
ただ世代の新しいスタジオは拡散で一次反射音をキャンセルしてしまう傾向が多いようだ。
Reflection Free Zoneという概念があるらしく正面と側面の一次反射面をピンポイントに吸音し、後壁を拡散させることで初期反射をなくしてしまいつつ、残響は生じさせる考えのようだ。
Nashville’s Blackbird Studio Cというスタジオは贅沢に四方八方を細かい拡散体で覆ってしまっている。一次反射音はキャンセルされ残響となり、無響室に控えめの残響が付与されたような音になっているそうだ。Dolby atmos 9.1.6chののリファレンスにもなっているらしい。

つまるところ一次反射面を含めて拡散体を沢山置くような部屋というのは現代的モニターライクな部屋であり、そういう音が出せるということになる。
(自分の中でモニターライクな部屋=吸音の多い部屋だという不勉強な概念があったが新しく塗り変わった。)
モニターライクな音に関して否定的な言い方をすれば、拡散体を沢山置きすぎると正しい音で鳴るが、神経質だったり、面白みが無い音になる可能性を秘めている。QRDや日東紡の様な高級調音オブジェはそういう方向のグッズであることは認識して使う必要がある。
ただ、一次反射をそのまま出すとコムフィルタ効果によりカラレーションが付いてしまい、モニターには適さない音になる。
ソナはこのスタジオを設計する際に一次反射を活用しつつカラレーションさせない手法として反射はするが反射の際に波形を変えてしまい、直接音と干渉しないようにしてコムフィルタ現象を生じさせにくくするという手法で解決させたようだ。
これは是非倣いたいメソッドである。
どうするかというと反射効果の強い拡散体を反射板として使うことで波形の相似性を解消させるとのことだ。

こんな拡散体売ってないし試験管状に木材を加工できないので作るのも難しいし真似できないじゃないかと途方にくれていたが、
理屈的には反射効果の強い拡散体であればいいので、全く同じ形で無くてもいいのかもしれない。
black birdのように細かい凸凹ではなく、大きさの粗い拡散パネルであれば反射効果の強い拡散体ということになり同じ効果が期待できるかも知れない。
このスタジオの音はモニターとして有用な特性を獲得しながらも一次反射音が残っているせいかガッツのある音、芯のある音だそうだ。自分の志向としてはそういう音を目指したいのかもしれない。
別の比較的新しい記事でソナでは同じ非相関一次反射を目的にして東映のatmos用のスタジオやカプコンのスタジオで平面に正方形の穴をランダムに開けたパネルを設置していたようだ。こっちの方が最新版なのだろうか。自作するならこっちの方が作りやすそうだ。


気になったので自分の部屋のインパルス応答を測定。今までも測定していたようなのだが、
理解できていなかったのでスルーしていた。
割と読み方が簡単だし測定結果があまりぶれないので再現性が高く、素人でも有用な測定法のようだ。

初期反射面が吸音部だったり調音パネルを置いたりクッションを置いたりと割と消音させたつもりなのだが、初期反射はいたって普通にありそうに見える。決して少なくはないようだ。
そして-60dbの残響時間はせいぜい300msくらい。短すぎて話にならないほどではないが、割とモニターに近いデッド気味の環境だった。
シアター面のスクリーンとその背面にある吸音材や部屋の中央にある足置きと自分の足(測定中は毛布で代用)などが追加の吸音作用を発揮して想定以上にデッドになっているのかもしれない。
もっとライブでもいいくらいなので吸音部を一部潰して非相関一次反射部などの機構を入れてもいいのかもしれない。
ソナのホームページに行ったところさらに興味深い記事もあったので後日Tipsを纏める予定。

















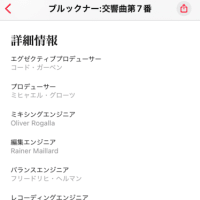

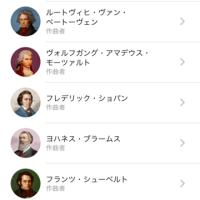
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます