放送大学の公開講座ネタの続きで
ハイパーソニックエフェクトを扱った講義がありました。
http://ocw.ouj.ac.jp/ra/8970114/06.html

特に気になった点を特筆すると、
・20kHz以上の超高域の脳への影響の研究はかなり大掛かりに行われており、学術的に信頼に足る研究実績がある(少なくともオーディオメーカーの商品のPRよりもずっと)
・超高域、特に40k~100kHzを豊富に含んだ音楽(ガムラン音楽など)を聴いたときに、同じ音源のCD音質(20kHz以上をカット)で聴いた時では得られない、脳の感動や喜びを司る部分が活性化された。
→超高域を含んだ音源はより良い聴体験となる。
・20k~40kHzはそういった脳の活性化が表れない。
→サンプリング周波数が96kHzのハイレゾ音源はハイパーソニックエフェクトの帯域を多くは含んでいない。192kHzやDSD音源でないと十分な期待はできない。また、20kHz~40kHzを聴き取れる若い耳を持ってない限りはあまりこの帯域は重要ではない。
・超高域の感覚受容器は耳ではなく(耳以外のどの部分かは現在不明)、イヤホンやヘッドホンで超高域を含んだ音を聴いても脳の特有の活性化は生じない。スピーカーで体で音を受けないと効果が表れない。
→ヘッドホンやイヤホンでの周波数帯域の広さはあまり意味が無い。そして耳が感覚受容器でない以上、老化による高域の聞こえづらさと超高域の感受性は関連がない。スーパーツィーターは若い人にしか必要が無いという考えは学術的には正しい見解とはいえない。
・CD音源に超高域のピンクノイズを足しても脳の特有の活性化は表れない。楽器の演奏から出る特有のゆらぎを含んだ超高域のみで起こる反応である。
・ピアノやオーケストラのような西洋楽器には超高域はほとんど含んでいない。
→クラシック音源に超高域を含んでいるということ自体はあまり意味が無い。(超高域が収録できるくらいサンプリング周波数が高く、情報量が多いというメリットはあるが)
ハイパーソニックエフェクトを扱った講義がありました。
http://ocw.ouj.ac.jp/ra/8970114/06.html

特に気になった点を特筆すると、
・20kHz以上の超高域の脳への影響の研究はかなり大掛かりに行われており、学術的に信頼に足る研究実績がある(少なくともオーディオメーカーの商品のPRよりもずっと)
・超高域、特に40k~100kHzを豊富に含んだ音楽(ガムラン音楽など)を聴いたときに、同じ音源のCD音質(20kHz以上をカット)で聴いた時では得られない、脳の感動や喜びを司る部分が活性化された。
→超高域を含んだ音源はより良い聴体験となる。
・20k~40kHzはそういった脳の活性化が表れない。
→サンプリング周波数が96kHzのハイレゾ音源はハイパーソニックエフェクトの帯域を多くは含んでいない。192kHzやDSD音源でないと十分な期待はできない。また、20kHz~40kHzを聴き取れる若い耳を持ってない限りはあまりこの帯域は重要ではない。
・超高域の感覚受容器は耳ではなく(耳以外のどの部分かは現在不明)、イヤホンやヘッドホンで超高域を含んだ音を聴いても脳の特有の活性化は生じない。スピーカーで体で音を受けないと効果が表れない。
→ヘッドホンやイヤホンでの周波数帯域の広さはあまり意味が無い。そして耳が感覚受容器でない以上、老化による高域の聞こえづらさと超高域の感受性は関連がない。スーパーツィーターは若い人にしか必要が無いという考えは学術的には正しい見解とはいえない。
・CD音源に超高域のピンクノイズを足しても脳の特有の活性化は表れない。楽器の演奏から出る特有のゆらぎを含んだ超高域のみで起こる反応である。
・ピアノやオーケストラのような西洋楽器には超高域はほとんど含んでいない。
→クラシック音源に超高域を含んでいるということ自体はあまり意味が無い。(超高域が収録できるくらいサンプリング周波数が高く、情報量が多いというメリットはあるが)

















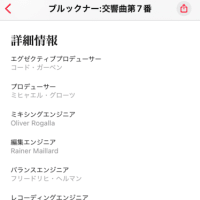

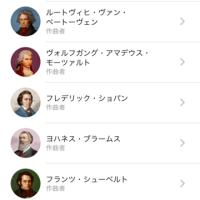






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます