ご迷惑ツールを、削除してくれるソフト。
「Junkware Removal Tool」
Babylonとか、Askツールバーとか・・・
いつの間にか入り込む、迷惑なアドウェアを、問答無用で除去してくれるソフト。
「AdwCleaner」と同じ、Malwarebytesのサービスです。
※「AdwCleaner」については、こちらの記事を参照してください。
=======================================
まずは、「DOWNLOAD」ボタンをクリック。

入手したファイルを起動すると、なんと! Dos窓。
あやしすぎる・・・けど、Malwarebytesだから、たぶん大丈夫です。

「保存していない作業があったら、保存してね。
勝手にじゃんじゃん、終了させちゃうよ。
自己責任でOKなら、何かキーを押してね。」
と書いてあります。
覚悟が決まったら、何かキーを押してください。
チェックが、始まります。

「(* )って、なんだろう」と思ったら、作業経過を表すゲージでした。
「JRT.txt」というテキストファイルが開いたら、作業終了。
削除したものが、書いてあります。

Exif情報で、写真ファイルの名前変更やフォルダ分けができるソフト。
「Rexifer」
写真ファイルの整理は、けっこう大変です。
最近はデジカメだけでなく、スマホで撮影することも多いから、なおさら。
「Rexifer」は、複数の人・カメラから集まってきた写真でも、
一括でリネーム&フォルダ分けして、場面ごとのアルバムにできます。
=======================================
Vectorのページからファイルを入手
→解凍してできる「Rexifer.exe」を実行します。

まずは、リネームやフォルダ分けのルール(フォーマット)を、決めてあげます。
フォーマットの書式は、1「設定」→「タグ挿入」を見ると、だいたいわかります。

たとえば・・・
「撮影年月ごとのフォルダを作って、それぞれの写真を振り分ける。
各写真のファイル名は、20170321.jpgのように年月日にする。
同じ年月日のファイルは、後ろに「-1」「-2」のように連番を付ける。」
・・・という場合、フォーマットは、
「<y4><m2><\><y4><m2><d2>-<RN>」
となります。
希望のフォーマットを作ったら、2から該当するフォーマットを指定。
フォーマット欄に、直接書き込んでもOK。
フォーマットを決めたら、3写真ファイルの入っているフォルダをドラッグ&ドロップ。
4「実行」をクリックして、作業完了です。
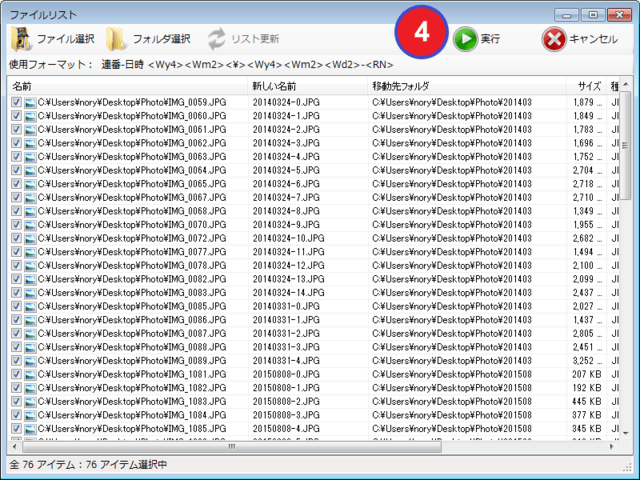
写真の、Exif情報を編集できるソフト。
「F6 Exif」
デジカメやスマホで写真を撮影すると、撮影日・場所などのExif情報が組み込まれます。
それを、編集/削除/追加できるソフト。
「位置情報を削除したい」
「スキャンした画像に、Exif情報を入れたい」
といったときに便利です。
=====================================
Vectorのページからファイルを入手
→解凍してできる「F6Exif.exe」を実行するだけ。
「ファイル」メニュー→「開く」、または写真ファイルをドラッグ&ドロップ。

Exif情報をすべて削除したいときは、「編集」メニュー→「Exif削除」。
Exif情報を確認したり、一部編集・削除・追加したりしたいときは、
「ツール」メニュー→「Exif一覧表示/編集」で、ExifListウィンドウを出します。

編集/削除したい項目を選んで、「編集」メニュー→「修正」で、書き換えます。
追加したいときは、「編集」メニュー→「追加」。

位置情報(GPS)を追加したいときは、
(1)IFD項目で、GPSを選択
(2)TAG項目で、「北緯(N)or 南緯(S)」を選択
(3)「N」と入力して、「更新」
(4)同様にして、(2)のTAG項目で、「緯度(数値)」「東経(E)or 西経(W)」「経度(数値)」を登録
で、ようやく情報が登録できます。
緯度や経度は、たとえば35度28分17秒なら、「35 Enter 28 Enter 17 Enter」と改行して、
3行で入力します。
パソコン全体の健康診断をしてくれるソフト。
「Kaspersky System Checker」
セキュリティ界のボス、カスペルスキー様が、健康診断してくれます。
人間同様、パソコンもたまに健診しておきましょう。

「DOWNLOAD NOW」をクリック
→入手したファイルを実行します。
なんかよくわかりませんが、とりあえず「Accept(了解)」。

「Run Diagnostics」で、診断開始。

「パソコン全体を~」というので、時間がかかるかと思ったのですが、
トイレに行って、戻ってきたら終わっていました。
「Detected Items」タブ。

問題点は、赤いビックリマークです。
「vulnerable(脆弱)」とあるのは、たいてい「ソフトのバージョンが古い」という場合。
最新バージョンにアップデートしたほうがいい、ということです。
ボクのパソコンは、不明なデバイスが放置状態でした。
問題なければ、緑チェックマーク。

「System Info」タブ。

パソコンのシステム構成、インストールされているソフトの情報が出ます。
「Infrequently Used」項目は、使用頻度の低いソフトがピックアップされているので、
アンインストール候補になります。
ネットバンク利用者のための、マルウェアチェック。
「DreamBot・Gozi感染チェックサイト」
DreamBotやGoziは、ネットバンク利用時の認証情報を狙うマルウェアです。
感染しているかどうか、1~2秒でチェックできます。
=======================================
ふだん使っているブラウザで、「感染チェック」をクリック。
ChromeやOperaは推奨ブラウザに入っていませんが、ふつうに使えます。

問題なければ、↓。

人工知能が、あなたにオススメの本を紹介してくれます。
「ブックツリー」
学生さんが、研究の一環で作ったサイトのようです。
ページデザインとか、変な「妖精」とか、
「発想はおもしろいけど、レベル低そうだなぁ」という印象 (^^;
ですが、意外や意外、ちゃんとした結果を出してくれます。
人工知能の学習が進んだら、ものすごく便利なサイトになりそう。
=======================================
IDとパスワードを自由に決めて、ログインします。

最初は、「本棚に追加」をクリックして、
これまで読んだ本を検索して、点数を付けていきます。
点数の付け方は、5段階でも10段階でも100点満点法でも、統一がとれていればOK。
(数値の大きいものほど、「おもしろかった」となります。)

本を検索するコツですが・・・
たとえば、森村誠一の「喪失」を探したいとき、
「喪失」で検索すると、検索結果が多くて、探しきれません。
AND検索が使えるので、「喪失 森村誠一」という具合に、著者名も入れるといいです。
とりあえず、17冊を本棚に登録してみました。
「実行」→「実行」をクリックすると・・・

「おすすめの結果」が、表示されます。

テンキーで、スマホ/携帯式入力ができるソフト。
「テンキー入力」
「こんなの、必要なの?」って思われるかもしれませんが・・・
意外や意外、かなり便利です。
ボクは、電話をかけながら、パソコンでデータ検索するときなど、
片手打ちでかなり苦労します。
電話の頻度からすると、ヘッドセットするほどでもないし。
・・・こんなときは、「テンキー入力」を起動すれば問題解決。
他にも、
「タッチタイプはできないが、すぐに入力作業をしないといけない」
「障がいで、片手しか使えない」
という場合も、慣れるとかなり速く打てます。
[PageUp]キーで、このソフトを起動/停止できるので、
「通常はフルキーボード使用、いざというときに起動」
という使い方ができます。
スマホ式(フリック入力)は、カーソルキーも使うので、
両手を使ったほうがスムーズ。
携帯式(トグル入力)なら、スピードは落ちますが、
完全に片手作業で済みます。
====================================
Vectorのページからファイルを入手
→解凍してできる「テンキー入力.exe」を実行。
最初に、入力方式を選びます。
タスクトレイ・アイコンを右クリックで、後で変更もOK。

入力の仕方などは、「操作説明書.pdf」に詳しく出ています。
(↓「操作説明書」から引用)

フリック入力の場合は、たとえば・・・
「え」を入力するときは、「7」を押しながら「→」を打ちます。
テンキーの「+」がEnter(決定/改行)で、「Enter」がSpace(変換/空白)なので、
慣れるまでは、しょっちゅう間違えるかも。

↑こんな調子で練習すれば、10分もすればそこそこ打てるようになります。
ホットキーで、即座にGoogle翻訳してくれる拡張機能。
「Instant Translate」
Chromeの拡張機能ですが、Firefoxのアドオンもあります。
AndroidやiOSのアプリもあります。
=======================================
Google翻訳は、昨年末にとつぜん進化しました。
(「Google翻訳がおりこうになった」参照。)
外国語サイトも、前のようにビビらなくなりました。
ですが、
(1)外国語をドラッグして選択→(2)コピー→(3)「Google翻訳」ページへ移動→(4)貼り付け
の4ステップがめんどう。
「Instant Translate」を入れると、
(1)外国語をドラッグして選択→(2)Shift+「T」
これだけ。

元のページを見ながら、翻訳結果も見られるので、すごくラク。
対応言語や翻訳結果は、Google翻訳と同じです。
短時間の縦長動画サイト。
「C CHANNEL(シーチャンネル)」
動画サイトといったら、Youtubeやニコニコ動画。
ボクはもっぱら、調べ事に利用しています。
とっても便利だけど、とにかく「長い」のが多い。
「C CHANNEL」は、「女子向け」とのことなので、
メイクやファッションなど、若い女性向けの内容が中心。
ですが、料理やDIYや旅行など、一般向けのものもあります。

特徴は、
・スマホ向けの、縦長サイズ。
・1本が30秒前後と、短時間。
とにかく、この「短時間」がGood!
気になる情報を、あれこれ、たくさん見られます。
=======================================
トップページの左側に、「カテゴリー」があります。
最初は、気になるカテゴリーの、人気順をながめるといいかも。
こういった、生活のハウツーとか。

「かんたん料理」とか。

最近は自分で食事を作っているので、「◯分でできる」みたいなのは助かります。
つくレポもあると、うれしい。
個人向けの、無料でできるバックアップシステムです。
今日は、通信授業の日でした。
生徒さんから、こんな質問がありました。
「セキュリティソフトはNorton(有料)を使っているが、
パソコンに、「Nortonバックアップドライブ」というのがある。
これは、使えるのか。」
USBメモリに小まめにバックアップをとっているが、めんどう。
「Nortonバックアップドライブ」を使えば、簡単になるんじゃないか。
・・・ということです。
これ、たしかにめんどうではないですが、
年額6,000円以上もするんですね。
こういうの、やめるにやめられないから、半永久的に払うことになる。
無料で、自分で仕組みを作る方法もあります。
どうします?
・・・ということで、その生徒さん、「無料で」を選択されました。
金銭的なことだけでなく、バックアップって、「理解しながら実施する」べきだと思うんです。
何かのサービスに100%任せきっちゃうんじゃなく、
毎日、なにかアクションする習慣をつけたほうがいいです。
=====================================
↓仕組みの概念図。

①デスクトップやマイドキュメントなど、バックアップをとりたいフォルダを、
Googleドライブフォルダにミラーリングします。
合わせて、世代管理もするのをオススメします。
②クラウド上に、自動的にミラーリングされます。
これで、仮にパソコンが壊れても、ファイルは保護されます。
Googleドライブは、無料で15GBまで使えます。
サイズの大きなファイル(動画ファイルなど)は、クラウドにバックアップは厳しいので、
複数の外付けHDDに保存するなど、別の仕組みを作ったほうがいいです。
=======================================
先に、「Googleドライブ」アプリをインストール。
Googleアカウントを、用意しておきます。
ブラウザでGoogleドライブを開き、ログイン。
すると、左下に「~をダウンロード」があるので、クリック。

入手したファイルを実行して、「Googleドライブ」アプリをインストールするだけ。
これで、②の仕組みは完了です。
次に、バックアップソフトを使って、①の仕組みを作ります。
歴史も評判も1番といったら、「BunBackup」でしょう。
サイトからファイルを入手し、インストールします。
BunBackupを起動したら・・・
1.「設定」メニュー→「機能表示設定」で、
2.「ミラーリング」と「世代管理」にチェックして、「OK」。

3.「追加」をクリックし、
4.わかりやすい「タイトル」を入力、バックアップ元を指定し、
「Googleドライブ」フォルダ内にバックアップ先を指定します。
5.「詳細」をクリックして、

6.「ミラーリング」タブで、「ミラーリングする」にチェック。

7.「世代管理」タブで、「世代管理する」にチェック。
保存期間はお好みですが、7日ぐらいでいいんじゃないかな。

あとは「OK」で閉じていきます。
同様に、3~7を繰り返して、バックアップしたいフォルダを追加していきます。
8.「保存」で、「バックアップ」という名前を付けて、デスクトップに保存してください。

9.BunBackupは、いったん閉じてください。
デスクトップに、「バックアップ.lbk」というファイルができています。
ダブルクリックして「このファイルを開けません」エラーが出るようだったら、
BunBackup.exeに関連付けさせてください。
10.「バックアップ.lbk」を、「スタートアップ」フォルダに移動します。
これで、①の仕組みは完成です。
パソコンを起動するたびに、上図が出ます。
「バックアップ開始」をクリックすると、ミラーリングが実行され、結果が表示されます。
BunBackupはコマンドラインに対応しているので、
この作業をバッチファイル化して、自動化することも可能です。
ですが、たった1クリックですから、このバックアップ作業を毎日の習慣にして、
「みずからバックアップしている」という自覚を持つほうがいいと思います。









