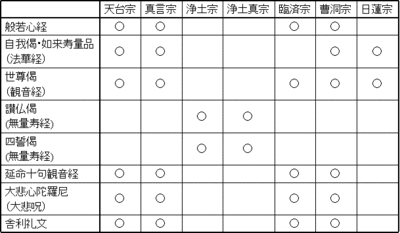自分は時刻表は、家でも出先でもB6サイズの全国版コンパス時刻表を愛用しています。携帯版にも関わらず、JRに関しては全駅掲載で、JRのみを利用するには便利です。B5サイズのJTB時刻表JR時刻表の両大型時刻表は、大きく持ち出すのに躊躇します。電車の中で大型時刻表を開いている人もたまに見ますが。
その交通新聞社の全国版コンパス時刻表は一説では、本家のJR時刻表に匹敵するぐらい売れているという説もあり、駅のキヨスクなどでは全国版コンパス時刻表が置かれているケースも多いようです。一方、JTBはJTB携帯時刻表が2011年4月に休刊となって以来、携帯サイズの時刻表を出していませんでした。

そんな中JTBが出してきたのが、JTB小さな時刻表。写真左の全国版コンパス時刻表よりも若干大きいですが、同じくB6サイズでコンパクトに収まっています。中身はというと、巻末の広告以外はB5サイズのJTB時刻表をそのまま縮小しています。


上が全国版コンパス時刻表、下がJTB小さな時刻表の中です。これだけ字の大きさが違い、さすがに見づらいのですが、鉄道ファンの年齢層を考えるとこれでも良いのかもしれません。そのまま縮小したので、新幹線と特急の乗り継ぎのページや、企画乗車券のページ、会社線のページ、編成表もそのまま掲載されています。
このJTB小さな時刻表、B5サイズのJTB時刻表の増刊扱いとなっています。どうやら完全に青春18きっぷユーザー目当てで、2012年3月にJTB時刻表4月号の臨時増刊で初めて発売され、7月には8月号臨時増刊の夏号、11月には冬号が発売予定だそうです。
その交通新聞社の全国版コンパス時刻表は一説では、本家のJR時刻表に匹敵するぐらい売れているという説もあり、駅のキヨスクなどでは全国版コンパス時刻表が置かれているケースも多いようです。一方、JTBはJTB携帯時刻表が2011年4月に休刊となって以来、携帯サイズの時刻表を出していませんでした。

そんな中JTBが出してきたのが、JTB小さな時刻表。写真左の全国版コンパス時刻表よりも若干大きいですが、同じくB6サイズでコンパクトに収まっています。中身はというと、巻末の広告以外はB5サイズのJTB時刻表をそのまま縮小しています。


上が全国版コンパス時刻表、下がJTB小さな時刻表の中です。これだけ字の大きさが違い、さすがに見づらいのですが、鉄道ファンの年齢層を考えるとこれでも良いのかもしれません。そのまま縮小したので、新幹線と特急の乗り継ぎのページや、企画乗車券のページ、会社線のページ、編成表もそのまま掲載されています。
このJTB小さな時刻表、B5サイズのJTB時刻表の増刊扱いとなっています。どうやら完全に青春18きっぷユーザー目当てで、2012年3月にJTB時刻表4月号の臨時増刊で初めて発売され、7月には8月号臨時増刊の夏号、11月には冬号が発売予定だそうです。