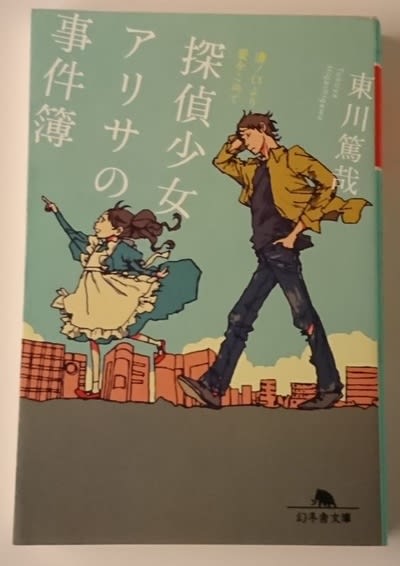城郭研究の第一人者、元奈良大学学長の千田嘉博教授の著書「城郭考古学の冒険」。城郭研究はかっては趣味の範疇でしたが、同氏はそれを学問にまでした研究者で、最近ではテレビの城郭番組にも頻繁に出演されています。
この本では、室町時代末期から戦国期から江戸期の城についての発展の過程が紹介されています。
日本の城は室町時代末期から江戸時代初期が、築城の全盛期ですが、戦国時代が終了したため、築城技術が江戸時代初期で、凍結されていると言われています。西洋の城が17世紀18世紀と戦乱が続いたため、築城技術が進化して、大砲などの砲撃に対応するため、高層建築を避けるようになったのに対して、日本の城は鉄砲の時代で、城の進化が停止して天守などの高層建築がそのまま残ったのというのは少し意外でした。
たしかに、鎖国が終わって入ってきた西洋の築城技術が五稜郭ですので、日本の城は見た目が一番美しい時期に軍事要塞から、政治的拠点に変わったのは幸運だったと同氏は述べています。