卯月の会の散策、松戸駅に9時30分集合。
今月は「お江戸日本橋散歩」。風もなくおだやかな一日だ。
<コースは>
東京駅八重洲口-④ヤン・ヨーステン記念碑-3高島屋東京店-4名水白木屋の井戸-5日本国道路元標-6日本橋魚河岸記念碑-①日本橋西河岸地蔵寺-7一石橋迷子しらせ石碑-8日本銀行本店本館-9十軒店跡-11三越日本橋本店-②奈良まほろば館-③日本橋名店街-12長崎屋跡-13宝田恵比寿神社とべったら市-14於竹大日如来井戸跡-15伝馬町牢屋敷跡-16石町時の鐘-17吉田松陰終焉の地-18馬喰町・横山町・堀留町問屋街-小伝馬町駅

ヤン・ヨーステン記念碑
JR東京駅の八重洲口からまっすぐ東へ延びる八重洲通りの日本橋通りと交叉する中央に建つ。
1989年、日蘭修好380周年を記念して建てられた。ヤン・ヨーステンは外交顧問として家康に仕えたオランダ人で八重洲の語源となった人物。

八重洲通りと、日本橋通りが交叉する地点の角に、この金属製のキリンは立っている。
何故かこの場所にアンバランスな感じがする。
四つ角の別の一つがブリジストン美術館があるブリジストンビル。
このキリンは旧社名を津村順天堂といった現ツムラ社が、目抜きの日本橋4丁目角に建設した本社ビルの入り口に、さっそうとたてられた鍛金彫刻家の安藤泉さんの作である。(1989年)

高島屋東京店
明治30年、この地に出店。もともとは、京都で天保2年(1831)創業の呉服屋であった。建物は昭和8年に建設され、この付近では有数の古さを誇っている。なお、高島屋の向かいには、洋書で知られる丸善がある。

本館エントラスホールの大理石の柱、蛇腹式扉のエレベーター、吹き抜けを囲むバルコニーなど、随所にレトロなディテールが健在している。
ちょうど雛人形が飾られていた。

1階中央エレベータ前の地下への階段の柱の大理石に、アンモナイトを見つけた。

名水白木屋の井戸 (現在地:コレド日本橋)
昭和42年までは、白木屋という屋号であった。白木屋は、寛文2年(1662)創業。越後屋と並ぶ呉服の大店。正徳2年(1712)、二代目木村彦太郎が井戸を掘ったところ、土中より観音様が現れ、清水が湧き出したと伝えられ、以後「白木名水」とうたわれた。

中央通から見た日本橋
首都高速道路の下にかくれるようにたたずんでいるのがわかる。

横から眺めた日本橋の全景

橋にかかる街燈が高速道の間を割り込んでそびえている。
日本橋の存在感を示しているかのようだ。

日本橋由来記の碑
この碑には文化財指定の理由や歴史(江戸時代の架橋から明治に造られたアーチ型の現在に橋に至る由来)などが記されている。

日本国道路元標
慶長8年(1603)、家康によって架けられた日本橋は、日本の中心、江戸繁栄の象徴となった。そして諸街道の起点と定められ、現在も、橋の中央に日本国道路元標が埋め込まれている。今日のルネッサンス式石橋は、明治44年(1911)に架設された。

日本橋魚河岸記念碑
佃島の漁師らが、幕府に日々上納する残りの鮮魚を、舟板の上に並べて売り出したのが日本橋魚海岸のはじまり。関東大震災まで、江戸及び東京の台所として活況を呈した。
中央の像は竜宮の乙姫様だそうだ。

日本橋の下を流れる神田川、川の水はかなりきれいになってきたようだ。

日本橋西河岸地蔵寺
泉鏡花の小説「日本橋」の舞台にもなった縁結びの地蔵尊。行基によって彫られたという。
地蔵尊は見れなかったが、小説「日本橋」に登場する芸者お千世の絵馬がかけられていた。

常盤橋
一石橋の親柱(写真左手にみえる柱)
一石橋迷子しらせ石碑(柱の裏手にある)
安政4年に建てられた庶民の告知板「たつぬる方」「しらす方」のそれぞれに、年頃、面体、格好、履物、衣類などを書いた紙を貼るようになっている。

常盤橋から遊覧船の風景

日本銀行本店本館
昭和29年、大判・小判を管理していた徳川氏金座跡に建てられた。以来、銀行の銀行とし ての役割をはたしている。本館の建物は、明治時代の貴重な本格的洋風建築として、重要文化財に指定されている。

日本銀行金融研究所貨幣博物館
日本の貨幣の歴史とそれにまつわるさまざまなエピソードをわかりやすく展示している。(入場無料)

<昼食:日本橋のそばや>
紅葉川( 日本橋室町1-2-4 三越SDビル1階 )
生ビールに天ざる、座席が広くゆったりした気分で食事ができた。

三越日本橋本店
延宝元年(1673)三井高利が江戸日本橋に越後屋を開業。「現銀掛値なし」という、当時としては画期的な正札販売でたちまち大呉服店となった。大正3年、東口玄関にライオン像をおき、これをシンボルとした。

三越は金メッキの装飾が随所にみられる

中央ホールの天女像

天女像わきの階段大理石、古代アンモナイトとベルムナイトの化石

中央ホールから地下1階への階段大理石にある大きなアンモナイトの化石
中央ホールには、重厚感のある大理石がふんだんに使われていて、歴史を感じさせられる。

奈良まほろば館(三越の真ん前にある)
奈良県の観光案内センタに立ち寄り資料入手。今年奈良では平城遷都1300年祭が予定されており、賑わっていた。

日本橋名店街
江戸時代から続く老舗が多く点在する。

十軒店跡
五代将軍綱吉が、京都の雛人形師10人を招き、ここにお長屋10軒を与えた。3月、5月には節句人形が軒なみ飾られ、「十軒が十軒ながら公卿の宿」とうたわれた。現在の室町3丁目付近。

長崎屋跡
寛永18年(1641)の鎖国後、オランダ商館長は、長崎出島から年一度、将軍拝謁のため上京した。その折り、長崎屋を定宿としていた。また、滞在中には、幕府の医官、蘭学者などが訪問し、新知識を吸収する場でもあった。

宝田恵比寿神社とべったら市
この神社は、毎年10月19日、20日のべったら市で有名。辻の両側せましと浅漬大根の露店が並び、大変な人出となる。今に残る江戸年中行事の一つで、このべったら市が終わると、東京に冬がくるといわれている。

於竹大日如来井戸跡
大伝馬の名主、馬込家の下女お竹は、日頃より慈悲心が深く、ある日、行者から大日如来の化身であると告げられた。多くの人がお竹を拝むために訪れ、お竹が愛用した井戸には、参拝者が市をなしたという。

十恩公園
伝馬町牢屋敷跡(写真右手)
牢屋敷は天正年間(1573~1591)、常盤橋門外におかれたのが最初。延宝5年(1677)にこの地に移された。江戸時代、全国最大の牢屋であったが、明治8年(1875)に廃止。安政大獄では吉田松陰などが投獄された。
吉田松陰終焉の地(写真左手)
兵学、洋学に通じた幕末の長州藩士・吉田松陰は、幕府の条約調印に関して閣老間部詮勝の襲撃を謀ったとして捕らえられ、安政6年(1859)伝馬町牢屋敷で処刑された。松陰直筆の辞世の歌が刻まれている。

石町時の鐘
江戸市民に親しまれた時報鐘のひとつ。現在の日本橋室町4丁目付近にあった。近くにオランダ人の定宿、長崎屋があったため、「石町の鐘はオランダまで聞こえ」とうたいはやされた。高さ1.7m、口径93cmの和鐘である。

馬喰町・横山町・堀留町問屋街
繊維や衣料、身廻品の問屋街として海外にまで知られている。江戸時代、馬喰町旅瑠籠街に投宿する旅人のために小間物問屋などが開店し、これが今日まで引き継がれている。素人お断りの店が多いが、だれでも買える店もある。
ゴールの小伝馬町駅に14時20分に到着。北千住経由で松戸へ。
いつもの居酒屋で2次会、脚より口のほうが疲れるほど議論に熱がはいる、まだまだ元気なシルバー世代である。
今月は「お江戸日本橋散歩」。風もなくおだやかな一日だ。
<コースは>
東京駅八重洲口-④ヤン・ヨーステン記念碑-3高島屋東京店-4名水白木屋の井戸-5日本国道路元標-6日本橋魚河岸記念碑-①日本橋西河岸地蔵寺-7一石橋迷子しらせ石碑-8日本銀行本店本館-9十軒店跡-11三越日本橋本店-②奈良まほろば館-③日本橋名店街-12長崎屋跡-13宝田恵比寿神社とべったら市-14於竹大日如来井戸跡-15伝馬町牢屋敷跡-16石町時の鐘-17吉田松陰終焉の地-18馬喰町・横山町・堀留町問屋街-小伝馬町駅

ヤン・ヨーステン記念碑
JR東京駅の八重洲口からまっすぐ東へ延びる八重洲通りの日本橋通りと交叉する中央に建つ。
1989年、日蘭修好380周年を記念して建てられた。ヤン・ヨーステンは外交顧問として家康に仕えたオランダ人で八重洲の語源となった人物。

八重洲通りと、日本橋通りが交叉する地点の角に、この金属製のキリンは立っている。
何故かこの場所にアンバランスな感じがする。
四つ角の別の一つがブリジストン美術館があるブリジストンビル。
このキリンは旧社名を津村順天堂といった現ツムラ社が、目抜きの日本橋4丁目角に建設した本社ビルの入り口に、さっそうとたてられた鍛金彫刻家の安藤泉さんの作である。(1989年)

高島屋東京店
明治30年、この地に出店。もともとは、京都で天保2年(1831)創業の呉服屋であった。建物は昭和8年に建設され、この付近では有数の古さを誇っている。なお、高島屋の向かいには、洋書で知られる丸善がある。

本館エントラスホールの大理石の柱、蛇腹式扉のエレベーター、吹き抜けを囲むバルコニーなど、随所にレトロなディテールが健在している。
ちょうど雛人形が飾られていた。

1階中央エレベータ前の地下への階段の柱の大理石に、アンモナイトを見つけた。

名水白木屋の井戸 (現在地:コレド日本橋)
昭和42年までは、白木屋という屋号であった。白木屋は、寛文2年(1662)創業。越後屋と並ぶ呉服の大店。正徳2年(1712)、二代目木村彦太郎が井戸を掘ったところ、土中より観音様が現れ、清水が湧き出したと伝えられ、以後「白木名水」とうたわれた。

中央通から見た日本橋
首都高速道路の下にかくれるようにたたずんでいるのがわかる。

横から眺めた日本橋の全景

橋にかかる街燈が高速道の間を割り込んでそびえている。
日本橋の存在感を示しているかのようだ。

日本橋由来記の碑
この碑には文化財指定の理由や歴史(江戸時代の架橋から明治に造られたアーチ型の現在に橋に至る由来)などが記されている。

日本国道路元標
慶長8年(1603)、家康によって架けられた日本橋は、日本の中心、江戸繁栄の象徴となった。そして諸街道の起点と定められ、現在も、橋の中央に日本国道路元標が埋め込まれている。今日のルネッサンス式石橋は、明治44年(1911)に架設された。

日本橋魚河岸記念碑
佃島の漁師らが、幕府に日々上納する残りの鮮魚を、舟板の上に並べて売り出したのが日本橋魚海岸のはじまり。関東大震災まで、江戸及び東京の台所として活況を呈した。
中央の像は竜宮の乙姫様だそうだ。

日本橋の下を流れる神田川、川の水はかなりきれいになってきたようだ。

日本橋西河岸地蔵寺
泉鏡花の小説「日本橋」の舞台にもなった縁結びの地蔵尊。行基によって彫られたという。
地蔵尊は見れなかったが、小説「日本橋」に登場する芸者お千世の絵馬がかけられていた。

常盤橋
一石橋の親柱(写真左手にみえる柱)
一石橋迷子しらせ石碑(柱の裏手にある)
安政4年に建てられた庶民の告知板「たつぬる方」「しらす方」のそれぞれに、年頃、面体、格好、履物、衣類などを書いた紙を貼るようになっている。

常盤橋から遊覧船の風景

日本銀行本店本館
昭和29年、大判・小判を管理していた徳川氏金座跡に建てられた。以来、銀行の銀行とし ての役割をはたしている。本館の建物は、明治時代の貴重な本格的洋風建築として、重要文化財に指定されている。

日本銀行金融研究所貨幣博物館
日本の貨幣の歴史とそれにまつわるさまざまなエピソードをわかりやすく展示している。(入場無料)

<昼食:日本橋のそばや>
紅葉川( 日本橋室町1-2-4 三越SDビル1階 )
生ビールに天ざる、座席が広くゆったりした気分で食事ができた。

三越日本橋本店
延宝元年(1673)三井高利が江戸日本橋に越後屋を開業。「現銀掛値なし」という、当時としては画期的な正札販売でたちまち大呉服店となった。大正3年、東口玄関にライオン像をおき、これをシンボルとした。

三越は金メッキの装飾が随所にみられる

中央ホールの天女像

天女像わきの階段大理石、古代アンモナイトとベルムナイトの化石

中央ホールから地下1階への階段大理石にある大きなアンモナイトの化石
中央ホールには、重厚感のある大理石がふんだんに使われていて、歴史を感じさせられる。

奈良まほろば館(三越の真ん前にある)
奈良県の観光案内センタに立ち寄り資料入手。今年奈良では平城遷都1300年祭が予定されており、賑わっていた。

日本橋名店街
江戸時代から続く老舗が多く点在する。

十軒店跡
五代将軍綱吉が、京都の雛人形師10人を招き、ここにお長屋10軒を与えた。3月、5月には節句人形が軒なみ飾られ、「十軒が十軒ながら公卿の宿」とうたわれた。現在の室町3丁目付近。

長崎屋跡
寛永18年(1641)の鎖国後、オランダ商館長は、長崎出島から年一度、将軍拝謁のため上京した。その折り、長崎屋を定宿としていた。また、滞在中には、幕府の医官、蘭学者などが訪問し、新知識を吸収する場でもあった。

宝田恵比寿神社とべったら市
この神社は、毎年10月19日、20日のべったら市で有名。辻の両側せましと浅漬大根の露店が並び、大変な人出となる。今に残る江戸年中行事の一つで、このべったら市が終わると、東京に冬がくるといわれている。

於竹大日如来井戸跡
大伝馬の名主、馬込家の下女お竹は、日頃より慈悲心が深く、ある日、行者から大日如来の化身であると告げられた。多くの人がお竹を拝むために訪れ、お竹が愛用した井戸には、参拝者が市をなしたという。

十恩公園
伝馬町牢屋敷跡(写真右手)
牢屋敷は天正年間(1573~1591)、常盤橋門外におかれたのが最初。延宝5年(1677)にこの地に移された。江戸時代、全国最大の牢屋であったが、明治8年(1875)に廃止。安政大獄では吉田松陰などが投獄された。
吉田松陰終焉の地(写真左手)
兵学、洋学に通じた幕末の長州藩士・吉田松陰は、幕府の条約調印に関して閣老間部詮勝の襲撃を謀ったとして捕らえられ、安政6年(1859)伝馬町牢屋敷で処刑された。松陰直筆の辞世の歌が刻まれている。

石町時の鐘
江戸市民に親しまれた時報鐘のひとつ。現在の日本橋室町4丁目付近にあった。近くにオランダ人の定宿、長崎屋があったため、「石町の鐘はオランダまで聞こえ」とうたいはやされた。高さ1.7m、口径93cmの和鐘である。

馬喰町・横山町・堀留町問屋街
繊維や衣料、身廻品の問屋街として海外にまで知られている。江戸時代、馬喰町旅瑠籠街に投宿する旅人のために小間物問屋などが開店し、これが今日まで引き継がれている。素人お断りの店が多いが、だれでも買える店もある。
ゴールの小伝馬町駅に14時20分に到着。北千住経由で松戸へ。
いつもの居酒屋で2次会、脚より口のほうが疲れるほど議論に熱がはいる、まだまだ元気なシルバー世代である。



































 神田・ニコライ堂
神田・ニコライ堂







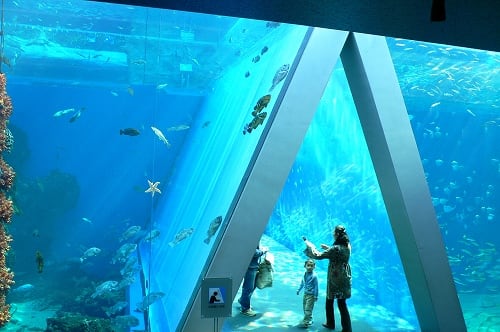

























 映画「緑の地平線」(左:原節子)
映画「緑の地平線」(左:原節子) 松平晃
松平晃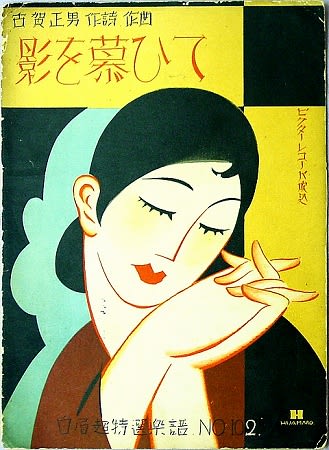



















 藤山一郎
藤山一郎
