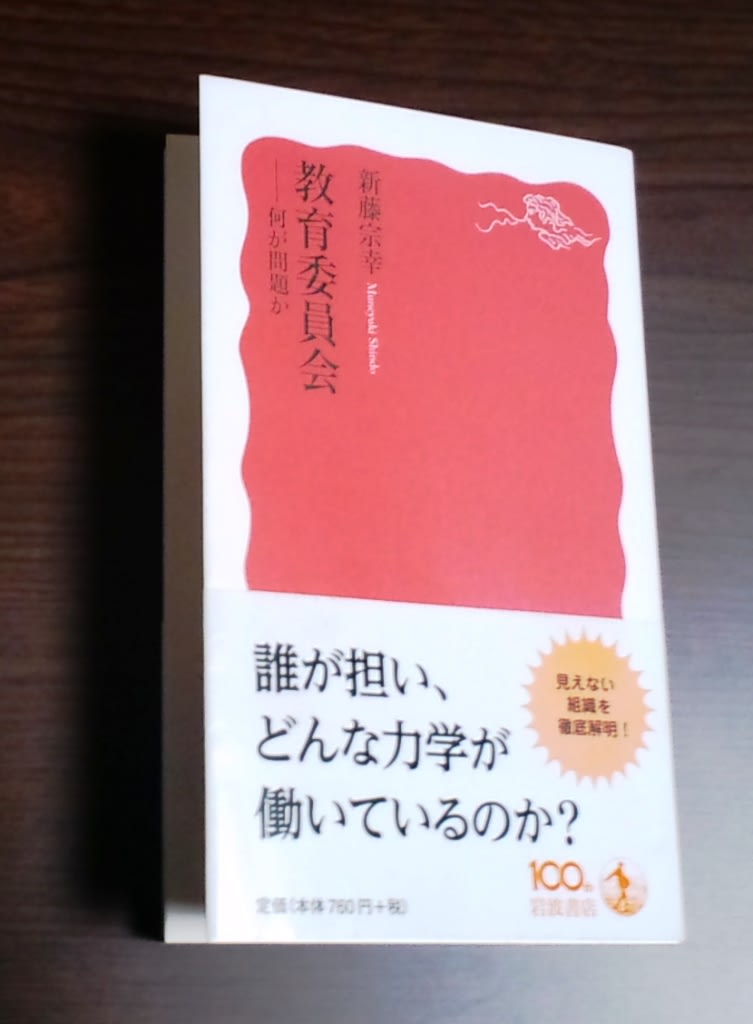
新藤先生は、自治体学会の中心人物の一人で、千葉大学の名誉教授、後藤・安田記念東京都市研究所研究担当常務理事。現在、地方分権、地方自治を論じる第一人者。
さて、教育委員会である。市町村や県という自治体のなかで、教育委員会とは何か。
教育委員会は、地方自治法に規定される行政委員会であり、市長村長などの首長とは、また別の執行機関である。同じ市町村の機関であるが、首長からは独立した権限を持っている。
この「独立した」ということは、もう一方で、国の行政のなかで、文部科学省の枠のなかにいるということ、厚労省、総務省、財務省などの他の行政部門とは違う教育の分野の中にいるということでもある。文科省、県教委、市町村教委、そして、地域の小学校や中学校というタテのピラミッド組織の真ん中にいるということ。
文科省の傘下のタテの組織の一員であることによって、他の行政分野と区別される。市長などの首長から、全く独立しているというわけではないのだが、別の執行機関として独立しているともいえるような微妙な位置づけとなっている。大雑把な言い方だが、地方自治法を読んでも、ここは、実は、どちらにも取れるようなことになっている。
ここは、法の規定がどうか、という論点でもそういうことだし、市役所の組織の中で、実際にどう機能しているか、という観点でもそうだと言える。この点、新藤先生のこの本を踏まえながら、現場のものが、現状をどう報告し、どう議論するか、そういう課題が、次に与えられるものだ。
ところで、教育委員会とは、非常勤の教育委員5名程度で構成される行政委員会である。本来は、この委員さんがたで構成されるまさしく委員会のことをさす。しかし、一般的に教育委員会というときに、教育長をトップとして、次長や課長のいる事務局、そのもとに学校や公民館、図書館がぶら下がっている組織のこととイメージすることが多いと思う。それらは、実は教育委員会の補助機関に過ぎないのだが、現実の働きとしては、それで間違いというわけでもない。さらに言えば、実質的には、つまり、実際に権力を行使しているのは、委員会事務局の課長以上の幹部である、というのがまさに正しいことだ。
そして、最近の傾向として、法的には地域の教育についての執行機関ではないはずの市長が、現実的に持つ権限は大きい、というあたりのことも論じられなければならないポイントである。予算をあつらえ、執行する権限、そして、教員以外の職員に対する人事権、この二つの権限は、市役所内で、教育委員会事務局に対しても、圧倒的な権力の源泉であることなど。もちろん、選挙で選ばれた役職であることの正統性もまた大きいことだ。(学校教育に対してもそうだだが、特に公民館など社会教育とか、あるいは、生涯学習とか言われる分野では特に。)
市長が、地域の学校の在り方、公民館の在り方について、意見を持ち、相応に責任を持った仕事を行う、というのは、一般的にいえば、当たり前のことだと思われると思う。でも、地方自治法とか、教育行政関係の法律を読むと、実はそれは当り前ではない。法的には、市長ではなくて、教育委員会が、その責任を持つべきものなのである。それは良きことなのかどうか。などというようなこと、そのあたりは、明確に論じられなければならないポイントだ。
この本を読んでいくと、まさしく、その一般的な感覚が、どう実現されるべきなのかが、問題提起されているとも言える。
おっと、ここまで、この本自体の紹介をしていなかった。
「制度上からいうかぎり教育委員会という行政委員会が教育行政の責任主体である。…教育委員会は非常勤の教育委員からなる行政委員会である。実際に教育委員会の仕事を取り仕切っているのは、都道府県であれ市町村であれ、本来、委員会の事務局である教育庁、市町村教委事務局といってよい。/ふつうに考えれば、非常勤であれ教育委員が委員会として議論をかさね、事務局に行動を指示すべきである。…/ところが、こうした行政委員会と事務局との関係は、教育委員会においては逆転しているといってよいだろう。…実態として事務局主導だという意味である。」(15~16ページ)(実のところ、選挙管理委員会であろうが、監査委員であろうが、逆転しているほうが普通だ。行政委員会ではないが、ひょっとすると、議会と議会事務局の関係も、あらかたそうなのかもしれない。しかし、これはまた別に論ずべきこと。)
市民から選ばれた教育委員なのであるが、そして、法的には、地域の教育行政に対して責任を負う立場なのであるが、実態としては、まったく権限を有していない。言ってみればお飾りの存在に過ぎない。
それで良いのか?
もちろん、それで良いわけではない。
しかし、新藤氏は、本来の教育委員会の権限を取り戻そうと主張するわけではない。もちろん、「教育を市民的に統制する」という理想を否定しているわけでもないのだ。
歴史的に、教育委員会には、教育委員もだが、市長らも積極的に関わっては来なかった。
「知事、市長村長は、議会の同意をえて教育委員を任命しているが、任命権者であるあれらも教育委員会に意見を申し出ることはなかった。」(19ページ)
一種の独立王国のような教育委員会事務局であったが、変化が見られるという。
「ところで、二〇〇〇年に始まる第一次地方分権改革は、首長たちの教育委員会観を変えたと言えるだろう。」(19ページ)
「首長たちは、この改革を機として「地域の自立」あるいは「自己決定の時代」といった言葉を多用し、自治体の中央省庁からの「自立」を強調するようになった。そして、地域社会の関心事である子どもたちの教育に首長がリーダーシップを発揮しづらいことを問題視しだした。首長が教育政策のなかみにかかわることができない…」(20ページ)
地方分権の流れ、これは大きな潮流であることはまちがいないが、その流れの中に、教育委員会も置かれている。そして、新藤氏は、この流れの中での知事や市町村長たちの主張を、とりあえずは良きものと評価している。(しかし、留保がある。一部首長の「暴走」に言及し、その危険性も語り、それを超える市民の参加、自治の実現を語っている。)
「じつはわたし(注;新藤宗幸氏)は、…直接公選で選ばれた首長が子どもたちの教育にかかわれない、文部省を頂点として下降する教育行政制度を廃止すべきだと語った。」(21ページ)
「第一次地方分権改革後…島根県出雲市長であった西尾理弘(まさひろ)…は、地方教育行政法を改正して、首長が教育行政全般を担い、教育委員会は首長の諮問委員会的なものにすべきだと折にふれて提起し、全国市長会の会議でも教育委員会制度の廃止発言をかさねた。」(22ページ)
教育の分野は、文部省を頂点として、中央集権の牙城をつくり上げてきた。厚生省や建設省などもそれぞれの中央集権の形を形成してきたわけだが、文部省もまた、独特の強固な形態をつくり上げてきた。
「地方教育行政法は国の「指導的地位」の確立、いいかたを換えれば、文部省から都道府県教育委員会-市町村教育委員会の『主従』関係ともいえるタテの行政系列を制度化したのだ。…文部省の意志がまず教育長を通じて都道府県教育委員会に端的につたわる制度となったのだ。さらに、市町村教育長…によって文部省の意思は地域末端まで教育行政を貫くことになる。」(140ページ)
教育委員会制度を置くことで、自治体内でのいわゆる「政治」からの独立を果たすということが、実は、文部省からの中央統制を貫徹する非常に有効な手段となり、中央の政治の直接の影響下に置くことになっていたというパラドクス。
「『教育行政の一般的行政からの分離・独立』…といった独特な論理をもとにして、専門職の連鎖を軸に歴史的に構成されたタテの行政系列が、揺らいだわけではない。」(147ページ)
「『教育行政の一般的行政からの分離・独立』論に当初より欠落しているのは、自治・分権のありかたや地方政府(自治体)の行政組織についての洞察ではないだろうか。」(161ページ)
それでは、住民の、地域の政治(これは本来の良き意味での政治。自治といったほうが分かりやすいか。)への参画、本来の地方政府の実現をどう図っていくのか?
「子どもたちの学習の場である学校、またそれを支える地域社会の人びとの教育への直接参加が必要であるのは、当然のことである。しかし、それが現行のタテの行政系列で可能なのかが、考えられねばなるまい。…教育委員会制度の理想主義の精神の回復や教育統治過程への『直接参加』は、すでに論じてきた中央から自治体にいたる教育行政の構造を根本から変えなければ、実現を見るものではないだろう。」(166ページ)
「端的に中央教育行政組織のありかたをいうならば、文部省初等中等教育局を廃止し、内閣からの独立性の高い行政委員会をもうけることだ。」(208ページ)
「そして、…都道府県教育委員会と市町村教育委員会を解体し、政治的代表制と正当性を持つ首長のもとに、学校教育から生涯学習までの教育行政を統合することだ。」(209ページ)
さらに、教育は、教育の分野だけで完結しているものではない。他の様々な分野と繋がっている。これは、あたり前のことだ。中央においては見えづらいかもしれないが、地域においてはあからさまなことだ。見えやすいことだ。
「本来、学校教育は地域の福祉、保健をはじめとした、ひろい意味のまちづくりと密着していよう。」(219ページ)
「学校教育は教育委員会、生活支援は首長部局といった割拠性が、首長のもとで克服され総合化されなくてはならないのである。」(221ページ)
もちろん、首長の下での統合にあたっては、学校委員会の設置などの、住民の直接参加する様々な仕組みが提案される。
新藤氏のこの本に描かれるのは、中央政府において、内閣、政治と一定程度距離を置いた行政委員会を設置し、地方政府(自治体)においては、教育委員会を廃止し、市長などの首長のもとに一元化せよという大改革。一見、中央と地方とで相反するようにも見える形態。非常に筋の通った骨太の提案。
この提案の実現は、生半可なことではない。実際にこのとおりにことが進むのかどうかは分からない。しかし、ここで、新藤氏が語るような方向にこそ、改革は進められなければならない、とわたしは思う。
さて、この本で、新藤氏は、まず、学校教育にかかわる問題を中心に取り上げている。教員が、県費負担職員というかたちで、市教委より県教委が人事権限を持つということで、市町村よりは県教委のほうがメインに語られている。
社会教育の分野は、学校教育とは微妙に状況が違っている。(根本的に違うわけではないのだが。)市町村の社会教育の分野には、首長の意向は実現されやすくなっていると言える。法的に与えられた権限よりも、実態としては権力を有していると言える。もちろん、新藤先生は、新書の分量の中で、論点を絞って書くために、社会教育の分野は後に回したということに過ぎない。
このあたりは、さらに、議論を補強すべきところである。ダイレクトに言えば、われわれ、地方自治を進展させようとし、なお学んでいこうとする市町村の職員に課せられた課題である。なおさら、市教委事務部局の管理職の一員であるわたしにとって。
それと、教員の専門性、のみに限らず、社会教育主事とか、さらにいえば、司書の専門性、個人の専門性だけでなく、業界としての専門性みたいなことも論じたいところだが、それは、今後の課題にしたい。(実は、結構「政治的」でもあるので、ことは慎重に行きたい、なんてね。)



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます